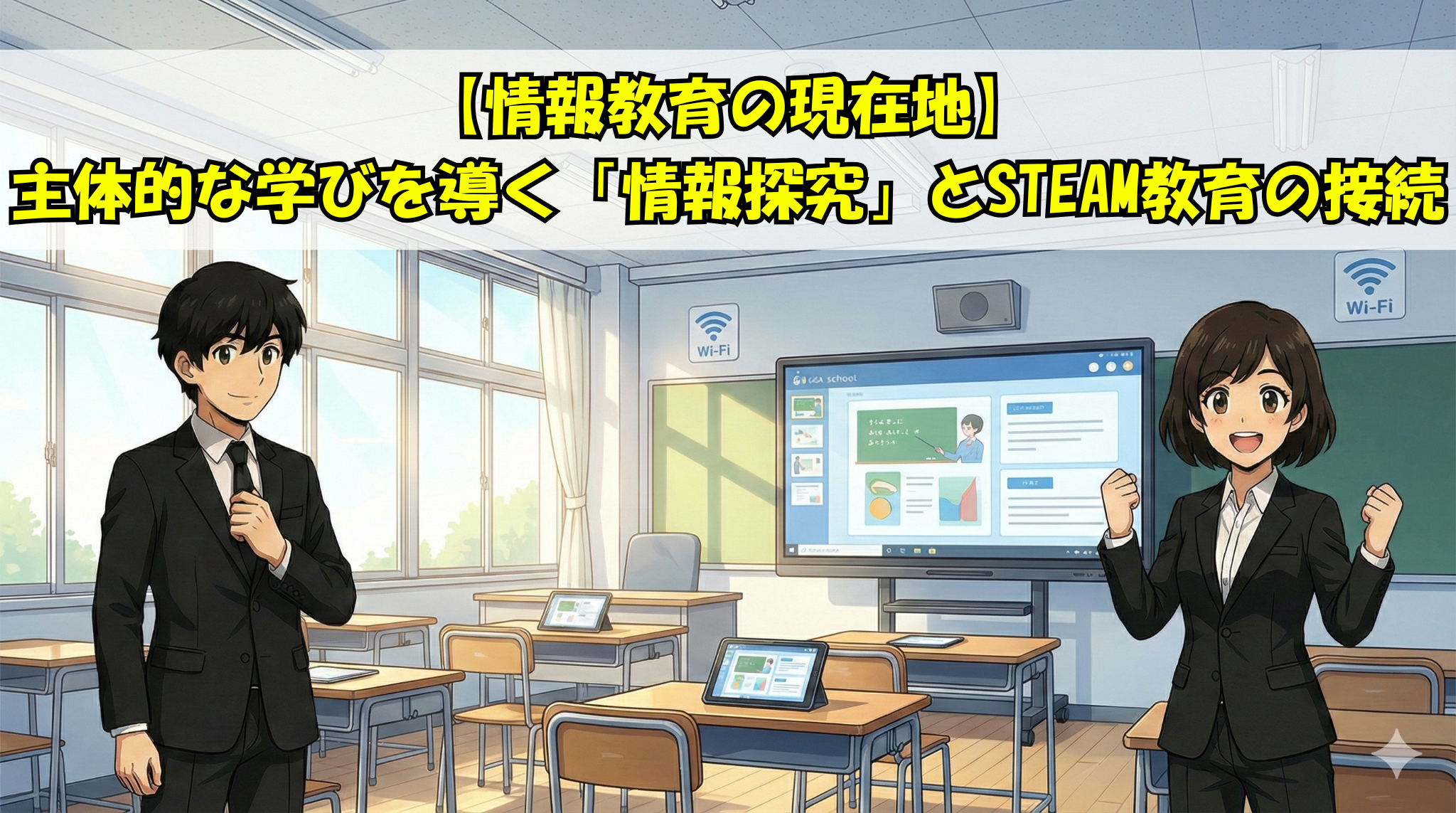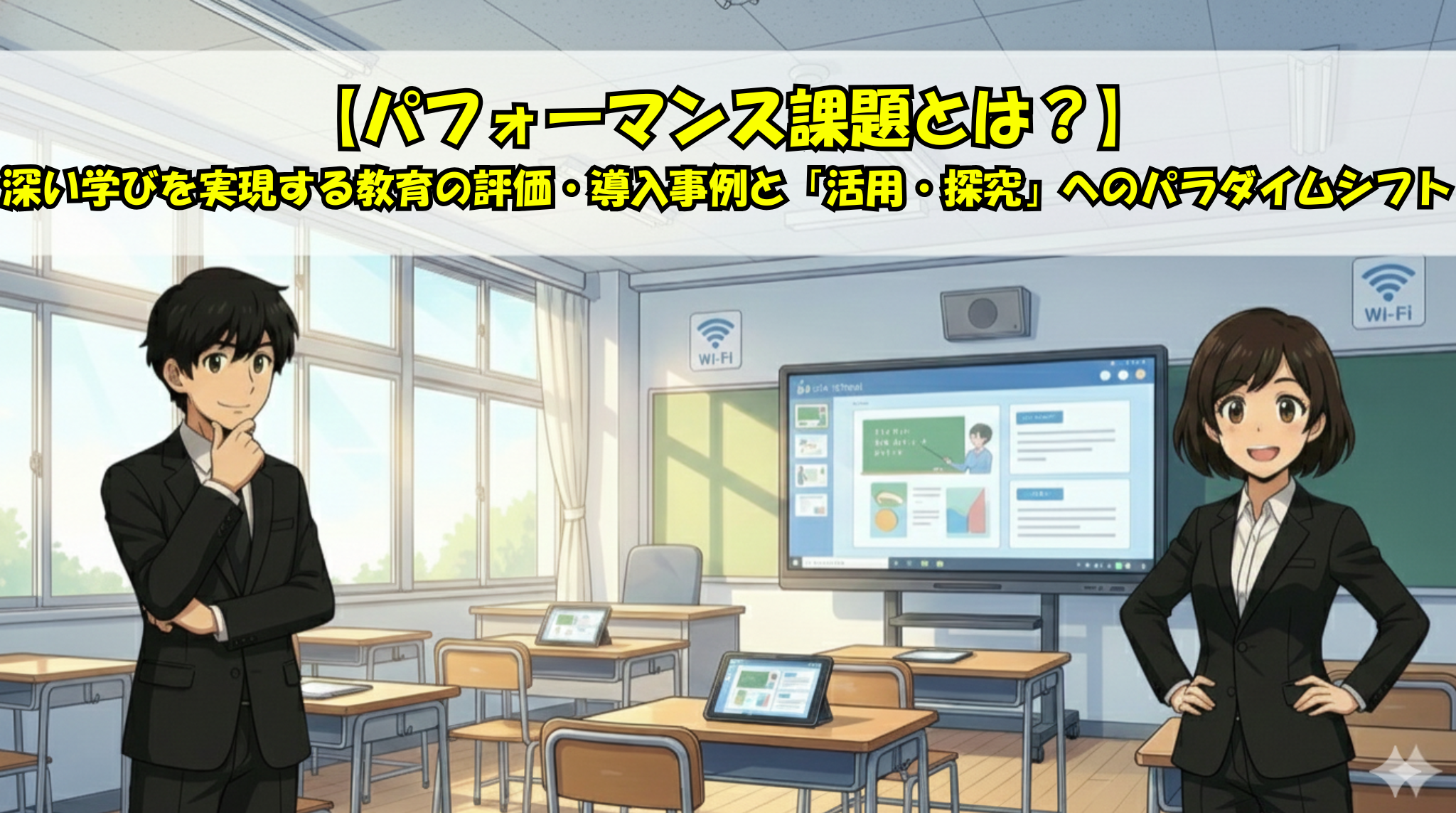先生も笑顔に!ウェルビーイングを高める学校の働き方改革事例集


そういえば先日の研修で偉い先生が「ウェルビーング」を取り入れる~とか言っていましたがこれってなんでしたっけ?私横文字苦手です……

しょっちゅうガジェットの話してるのに、この手の単語はダメなんですね(笑)ウェルビーングは簡単に言うと「心も体も満たされて、幸せに過ごせる状態」のことです。

学校を楽しい場所にしよう!ってことですか?

そうです!3割ぐらいあっています。

ほとんど不正解じゃないですか⁉
最近、「ウェルビーイング(well-being)」という言葉をよく耳にしますよね。なんだか難しそうに聞こえるけれど、簡単に言えば「心も体も満たされて、幸せに過ごせる状態」のこと。
「先生が元気な学校は、子どもも元気な学校だ!」
これって、すごく当たり前で、でもとっても大切なことだと思いませんか?
今の教育現場では、子どもたちの幸せはもちろん、先生自身のウェルビーイングも大きな課題になっています。先生自身が幸せに働けることは、子どもたちの教育の質に直結する、大切なことなんです。
この記事では、教員のウェルビーイング向上に焦点を絞り、学校全体でどんな素敵な取り組みが進められているのか、そして私たち先生自身が幸せに働くために何ができるのかを、一緒に考えていきたいと思います!
教員のウェルビーイングを支える実践
先生のウェルビーイングは、子どもたちの教育の質に直結する、大切な要素です。先生が健康的で充実した状態で働けるように、学校全体で様々な取り組みが進められています。
1. 働き方改革とメンタルヘルス対策の充実
学校の働き方改革では、教員の「働きやすさ」と「働きがい」が高い次元で両立する職場を目指すことが重要とされています。この両立が実現している学校では、先生たちの抑うつ傾向が低く、主観的な幸福感や同僚への信頼が高いことが明らかになっています。
- 「笑顔の学校」プロジェクト: 枚方市教育委員会では、教員の精神疾患による病気休暇・休職者の減少と、働きがい・働きやすさの実現を目指す、素敵なメンタルヘルス対策「笑顔の学校」プロジェクトを実施しています。
- 業務改善: 月あたりの時間外勤務時間を縮減したり、教職員の増員を図ったりして、業務の適正化・効率化・平準化を進めています。
- ワークエンゲージメントの向上: 学校教育自己診断を通じて、「意欲的に働き、自分の能力を高めることができた」「授業がわかりやすい」といった、先生たちの素敵な回答が増えることを目指しています。
- 専門家による支援体制: 保健師、産業医、臨床心理士といった専門家を「顔の見える相談員」として活用を推進し、先生たちが気軽に相談できるような雰囲気づくりをしています。
- 復職支援: 休職中の先生向けの「ひらかた復職サポートブック」を作成したり、復職後のケアも継続的に実施したりしています。復職した先生からは、「急に担任ではなく、TT(チームティーチング)でスタートできたのが心強かった」といった、細やかな配慮が助けになったという温かい声も届いています。
- 組織的な健康管理: 大規模校での衛生委員会の適切な開催を支援したり、小・中規模校でも業務改善推進委員会などを通じて、学校みんなでセルフケアを促進しています。
- 情報発信と支援体制: 学校の働き方改革やメンタルヘルスに関する取り組みについて、ホームページやブログ、冊子などを用いて積極的に情報発信し、学校内外への理解を深めることを目指しています。
2. 研修会の実施
先生向けのメンタルヘルス・マネジメント研修も実施されており、ストレスを正しく理解し、適切に対処するための研修が提供されています。
- ストレスマネジメント: ストレスの正しい理解、レジリエンス(強靭さ)の向上、マインドフルネスといった手法を学びます。
- コミュニケーション: NVC(非暴力コミュニケーション)を活用した感情理解ワークショップを通して、共感を持って臨むコミュニケーション手法を学び、ネガティブな感情を創造的に解決する手段が教えられています。
- 自己理解: MBTI性格検査などを通して自己理解を深め、自分自身のストレスへの対処法を見つける手助けとなります。
これらの実践を通じて、教員と子どもたちがともに健康で、活き活きと学校生活を送れる環境を作ることが、ウェルビーイングな学校の実現につながります。
子どものウェルビーイングを育むための実践
先生のウェルビーイングを支えるための実践と同様に、子どもたちのウェルビーイングを育む実践も重要です。
1. 非認知能力の育成を意識した活動の導入
- 外遊びの推奨: IQや学力テストでは数値化されない、やる気、忍耐性、協調性といった非認知能力の育成に、外遊びの時間が重要とされています。
- 「主体的・対話的で深い学び」の推進: 新しい学習指導要領では「生きる力」を育むために、「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」という視点での授業改善が提唱されています。
- 具体的な授業例:
- 主体的な学び: 技術・家庭科の授業で棚や椅子を設計・製作する際に、修正や改善を繰り返す活動を通じて、見通しを持って粘り強く考える力を育みます。体育の跳び箱の授業では、学習カードを活用して自分の学びを振り返り、次の学びや生活に生かす力を育むことが目指されます。
- 対話的な学び: 理科の物の溶け方に関する授業で、グループで様々な方法で調べ、考えた結果をグループ間で共有することで、議論を深め、多様な視点で考える力を養うことができます。
- 深い学び: 社会科の安土桃山時代に関する授業では、資料を読み解き、議論を通じて知識を深く理解し、考えを形成する力を育みます。
2. コミュニケーション能力の育成
- 「相手意識」の育成: 相手の状況を意識してコミュニケーションをとる能力です。神奈川県の小学校(3年生)では、友達の様子(頭痛、一人でいる、読書中など)を見て、どのように声をかけるかを考えさせる授業を行い、児童が相手の状況や気持ちを考慮した声かけの重要性に気付く機会となりました。
- 「目的意識」の育成: 目的に応じたコミュニケーションをとる能力です。同県の小学校(5年生)では、友達の情報を集めるインタビュークイズを通じて、普段関わらない友達との交流が深まり、相手の思いや考えを聞き取る力を育みました。
- 「気付き」に焦点を当てる: コミュニケーション能力の育成においては、その授業だけで「できる」ようになるのではなく、児童・生徒が自身のコミュニケーションのとり方に「気付く」ことに重点を置くことが効果的です。
- 「僕のトリセツ・私のトリセツ」の活用: 公立小学校教員の松下隼司氏の実践として、子どもたち自身に「僕のトリセツ・私のトリセツ」を書いてもらう取り組みがあります。これをクイズ形式にすると、相互理解や他者理解につながり、クラスでの安心感や居場所を得られる効果があるとされています。
3. 心のケアと日常の健康観察の徹底
- 日常からのきめ細やかな健康観察: 心身の健康問題の早期発見・早期対応のため、学級担任や養護教諭が中心となり、日頃からきめ細かな健康観察を実施することが大切です。
- 保護者との連携: 子どもの健康観察の着眼点を保護者と共有したり、学校と家庭での様子を照らし合わせたりすることで、問題の早期発見につなげます。
組織全体での取り組みの重要性
個々の先生の努力だけでなく、学校全体での組織的な取り組みが、コミュニケーション能力やウェルビーイングの育成に効果的であると強調されています。埼玉県の小学校では、ウェルビーイングを学校経営に取り入れた結果、子どもの「学校が楽しい」という回答が98%に達し、学力向上や教職員のウェルビーイング、心理的安全性も向上した事例が報告されています。
- 外部支援の検討: 「先生の幸せ研究所」のような外部団体は、先生の自己決定を起点とした「プロジェクト型業務改善」を通じて、教育現場の自立・自律を支援しています。 NPO法人「学校の話をしよう」は、対話を通じた教員間の関係性の豊かさや学校運営を支援するプログラムを提供しています。
これらの実践を通じて、教員と子どもたちがともに健康で、活き活きと学校生活を送れる環境を作ることが、ウェルビーイングな学校の実現につながります。
まとめ
日本の学校教育は、教員と生徒、双方のウェルビーイングを向上させることに取り組んでいます。教員という仕事の魅力を高め、より多くの人が教職を目指し、働きがいを感じながら教育に取り組める環境を整えること。
そして、子どもたちが、知識だけでなく、変化の激しい社会を生き抜くために必要な非認知能力やコミュニケーション能力を育み、幸せに学校生活を送れるようにすること。
教員と子どもたちが共に健康で、活き活きと学校生活を送れる環境を作ることが、ウェルビーイングな学校の実現につながります。子どもたちの「生きる力」の育成は、教員の「働きがい」と「働きやすさ」の向上なしには実現できません。
先生自身のウェルビーイングを大切にし、子どもたちと共に幸せな学びの場を築くことこそが、これからの教育の未来を拓く鍵となるでしょう。

ざっくり、認め合って、高めあって素敵な学校作ろうぜって話です。これでも少し足りないように気もしますが……

なるほど!わかった気がします。

ははは、それが重要です。