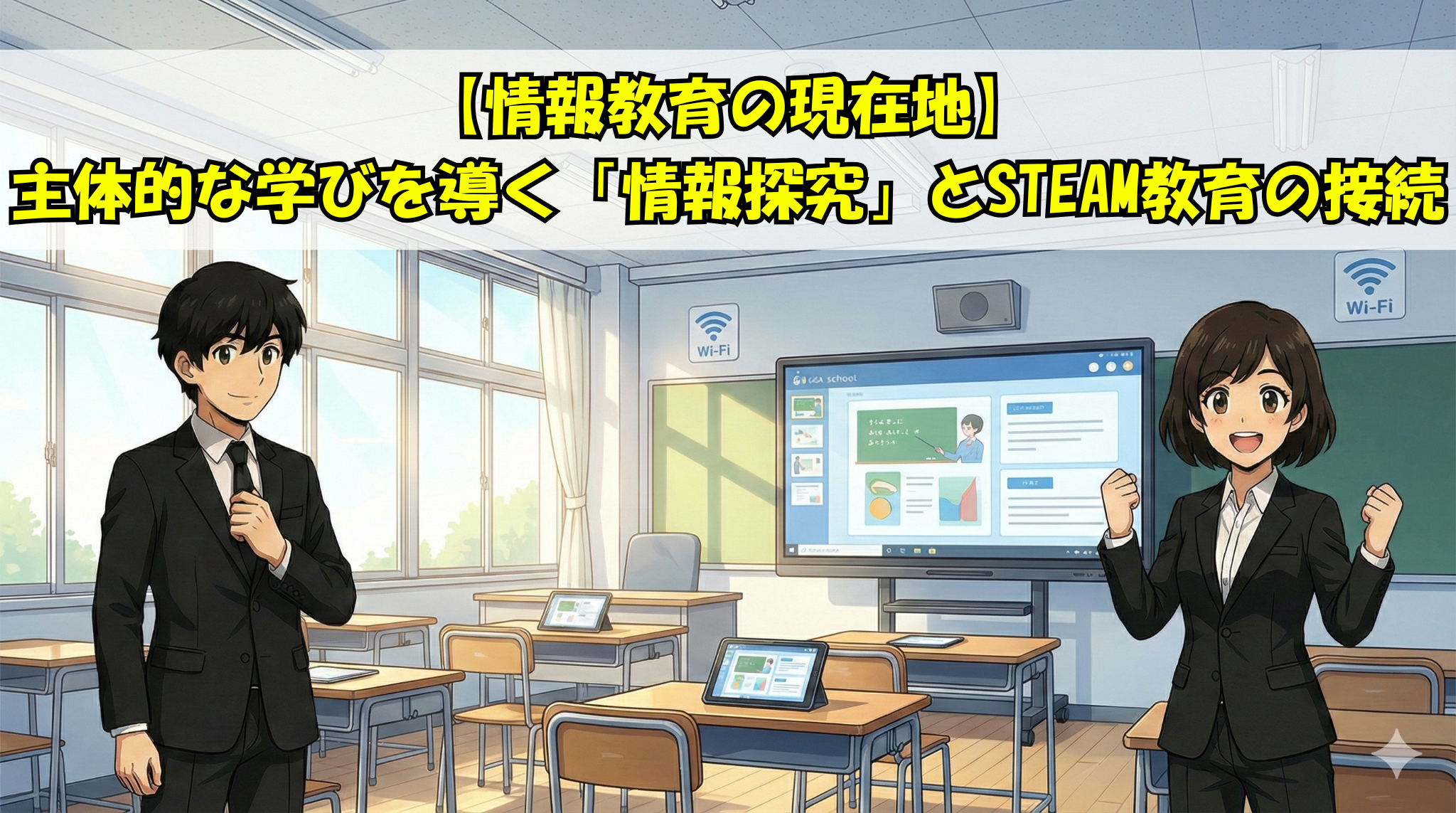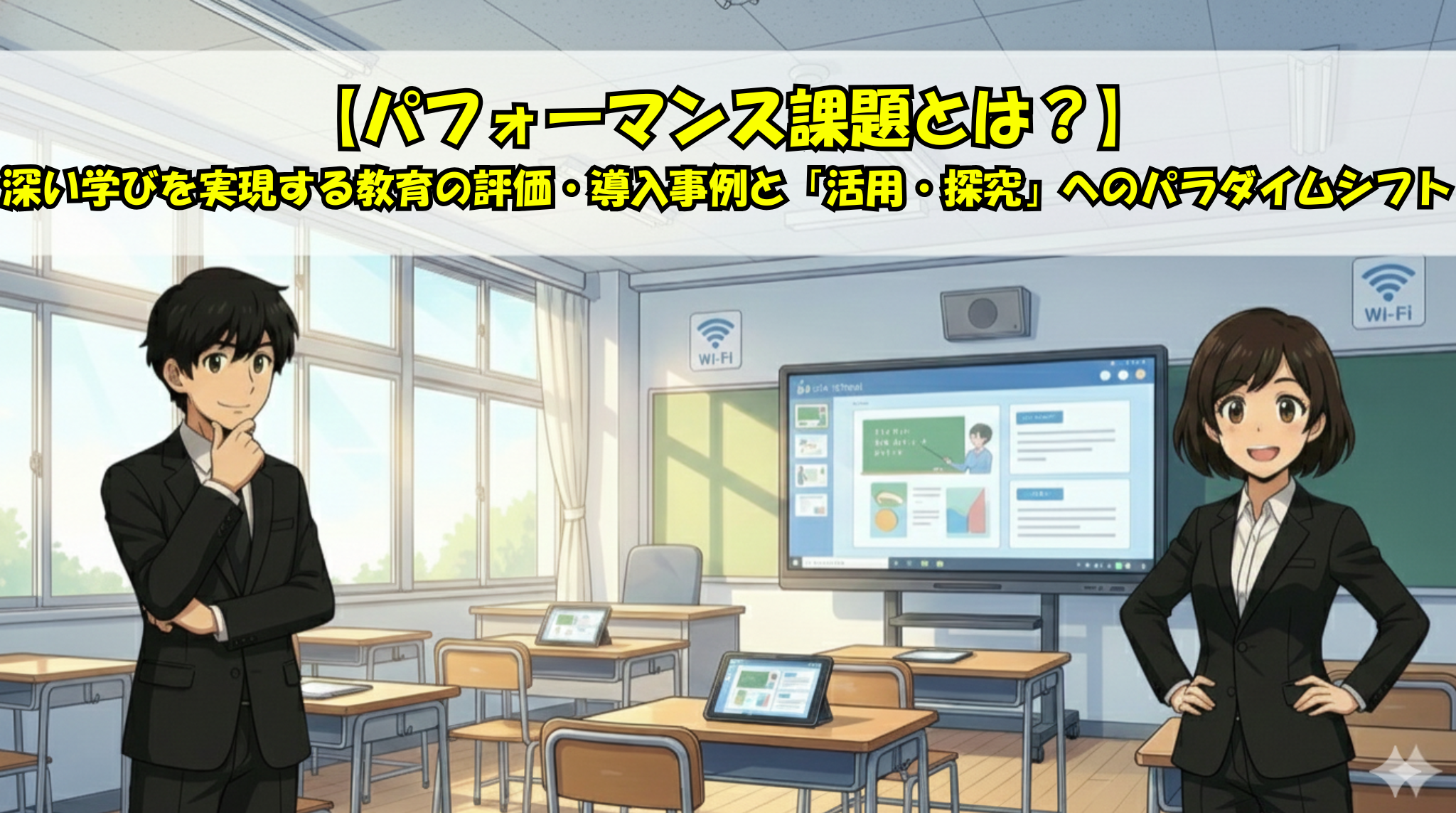学校で広がる“幸せな学び”|子どものウェルビーイングを高める実践事例集


前回の記事の「ざっくり認め合って、高めあおうぜ」の続きになるのですがこちらもまた、ふわふわした内容になってしました。

こういった概念の理解って難しいですよね。
最近、「ウェルビーイング(well-being)」という言葉をよく耳にしますよね。なんだか難しそうに聞こえるけれど、簡単に言えば「心も体も満たされて、幸せに過ごせる状態」のこと。
「子どもたちが毎日学校に行きたい、先生が働きたいと思える学校を作りたい」
これは、多くの先生や保護者が願っていることではないでしょうか。
ユニセフの報告書では、日本の子供の精神的幸福度が低いことが指摘されており、ウェルビーイングの向上が喫緊の課題とされています。この記事では、子どもの幸せを育むために、日本の学校教育でどのような素敵な取り組みが進められているのか、そして私たち大人がどう子どもたちをサポートできるのかを、一緒に考えていきたいと思います!
ウェルビーイングとは?なぜ今、学校教育で大切にされているのか
ウェルビーイングは、世界保健機関(WHO)が健康を単に病気でない状態ではなく、身体的、精神的、社会的に満たされた状態と定義していることにも示されています。近年、物質的な豊かさだけでなく心の豊かさが求められる時代の潮流や、VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)と呼ばれる不確実性の高い時代において活躍できる人材育成の観点から、その重要性が高まっています。
- 子どものウェルビーイングの現状: ユニセフの報告書「レポートカード19」では、日本の子供の「精神的幸福度」は36カ国中32位と低く、子どもの自殺率の増加や、貧困・格差の拡大が指摘されています。こうした状況を改善し、子どもたちが毎日学校に行きたい、先生が働きたいと思える学校を作ることが目指されています。
- 教員のウェルビーイングとの関連性: 子どものウェルビーイングを育むためには、まず先生自身がウェルビーイングであることが不可欠だと考えられています。先生が元気な学校は、子どもたちも元気な学校であるという認識に基づき、教員の「働きやすさ」と「働きがい」の両立を目指す取り組みが推進されています。

子どものウェルビーイングを育むための実践
子どもたちが安心して学び、自分らしく成長できる環境を整えることは、ウェルビーイング向上の第一歩です。
1. 非認知能力の育成を意識した活動の導入
子どものウェルビーイングを育むためには、IQや学力テストでは数値化されない「非認知能力」の育成が重要です。これには、やる気、忍耐性、協調性などが含まれます。
- 「生きる力」を育む授業: 文部科学省の新しい学習指導要領では、子どもたちに「生きる力」を育むことを目指し、授業改善を進めることが重視されています。
- 主体的な学び: 技術・家庭科の授業で棚や椅子を設計・製作する際に、修正や改善を繰り返す活動を通じて、見通しを持って粘り強く考える力を育みます。
- 対話的な学び: 理科の物の溶け方に関する授業で、グループで様々な方法で調べ、考えた結果をグループ間で共有することで、議論を深め、多様な視点で考える力を養うことができます。
- 深い学び: 社会科の安土桃山時代に関する授業では、資料を読み解き、議論を通じて知識を深く理解し、考えを形成する力を育みます。
2. ポジティブ心理学から学ぶ「幸せの4つの因子」
慶應義塾大学の前野隆司教授が提唱する「幸せの4つの因子」を意識することで、子どもたちは幸せをコントロールできるようになります。LCA国際小学校では、この4つの因子に関連する問いが書かれた「ダイアローグカード」を用いたワークショップを通じて、子どもたちの自己肯定感を高める取り組みを行っています。
- やってみよう: 自己実現と成長
- ありがとう: つながりと感謝
- なんとかなる: 前向きさと楽観性
- ありのままに: 独立と自分らしさ
タル・ベン・シャハー博士が提唱する「SPIREモデル」も同様に、Spiritual(スピリチャル)、Physical(身体的)、Intellectual(知性的)、Relational(人間関係的)、Emotional(感情的)の5つの要素が満たされた状態を目指す教育も取り入れられています。
| 要素 | 意味 | 学校教育における例 |
| Spiritual (スピリチュアル) | 目的や意味を見出すこと | 探究学習を通じて、自分の興味や価値観に基づいた問いを追求する時間。 |
| Physical (身体的) | 健康的な身体を維持すること | 体育の授業や休み時間の外遊び、バランスの取れた給食。 |
| Intellectual (知性的) | 知的好奇心を追求すること | 授業での「なぜ?」を大切にし、主体的に学ぶ機会。 |
| Relational (人間関係的) | 良好な人間関係を築くこと | 友達との協力、対話的な授業、お互いの強みを見つけ合う活動。 |
| Emotional (感情的) | 感情を豊かに感じ、管理すること | 感情を表現する授業や、気持ちを落ち着かせる方法を学ぶ時間。 |
3. 「強みを伸ばす教育」で自己肯定感を育む
ポジティブ心理学の知見を応用した「ポジティブ教育」では、子ども一人ひとりの「強み」(性格的な特性)を発見し、それを伸ばすことを支援します。
- 具体的な授業例: 国語の授業で登場人物の強みを探したり、歴史上の偉人が困難を乗り越えた強みを特定したり、図工で自分の強みをアート作品に表現したり、道徳の授業でお互いの強みを見つけ合う活動などが実践されています。これは、自己肯定感を高め、人生の満足度を向上させることが研究で示されています。
4. コミュニケーション能力の育成
- 「相手意識」と「目的意識」: 子どもたちが必要なコミュニケーション能力として、「相手の状況を意識する力」と「目的に応じたコミュニケーションをとる力」の二つが提唱されています。
- 具体的な授業例: 神奈川県の小学校(3年生)では、友達の様子(頭痛、一人でいる、読書中など)を見て、どのように声をかけるかを考えさせる授業を行い、児童が相手の状況や気持ちを考慮した声かけの重要性に気付く機会となりました。 公立小学校教員の松下隼司氏の実践として、子どもたち自身に「僕のトリセツ・私のトリセツ」を書いてもらう取り組みがあります。これをクイズ形式にすると、相互理解や他者理解につながり、クラスでの安心感や居場所を得られる効果があるとされています。
5. 心のケアと日常の健康観察の徹底
- 日常からのきめ細やかな健康観察: 心身の健康問題の早期発見・早期対応のため、学級担任や養護教諭が中心となり、日頃からきめ細かな健康観察を実施することが大切です。
- 保護者との連携: 子どもの健康観察の着眼点を保護者と共有したり、学校と家庭での様子を照らし合わせたりすることで、問題の早期発見につなげます。
組織全体での取り組みの重要性
個々の先生の努力だけでなく、学校全体での組織的な取り組みが、コミュニケーション能力やウェルビーイングの育成に効果的であると強調されています。埼玉県の小学校では、ウェルビーイングを学校経営に取り入れた結果、子どもの「学校が楽しい」という回答が98%に達し、学力向上や教職員のウェルビーイング、心理的安全性も向上した事例が報告されています。
まとめ:子どもの「生きる力」を育むウェルビーイング教育
日本の学校教育は、子どもたちのウェルビーイングを向上させることに取り組んでいます。
- 子どものウェルビーイング: 非認知能力の育成、新しい学習指導要領に基づく授業改善、心のケア体制の強化を通じて、子どもたちが安心して学び、自分らしく成長できる環境を整えています。
- 教員のウェルビーイング: 教員が働きがいを感じ、苦しい時にも耐えられるような「心理的安全性」の高い職場を作ることが不可欠です。
子どもたちが、知識だけでなく、変化の激しい社会を生き抜くために必要な非認知能力やコミュニケーション能力を育み、幸せに学校生活を送れるようにすること。教員と子どもたちが共に健康で、活き活きと学校生活を送れる環境を作ることこそが、ウェルビーイングな学校の実現につながります。

私の理解ではありますが、なんだかマザー・テレサさんの言葉を思い出しますね。
「思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。」
「言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。」
「行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。」
「習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。」
「性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。」
ってやつなんですけど。

その言葉は素敵だと感じます。どこまで気を付けられたのでしょうかね。

なんだか含みのある言い方ですね。

まぁ、子どもたちの環境を整えるという意味でも、認め合える環境。笑いあえる環境。失敗できる環境。そういった整備整備が我々の仕事です。