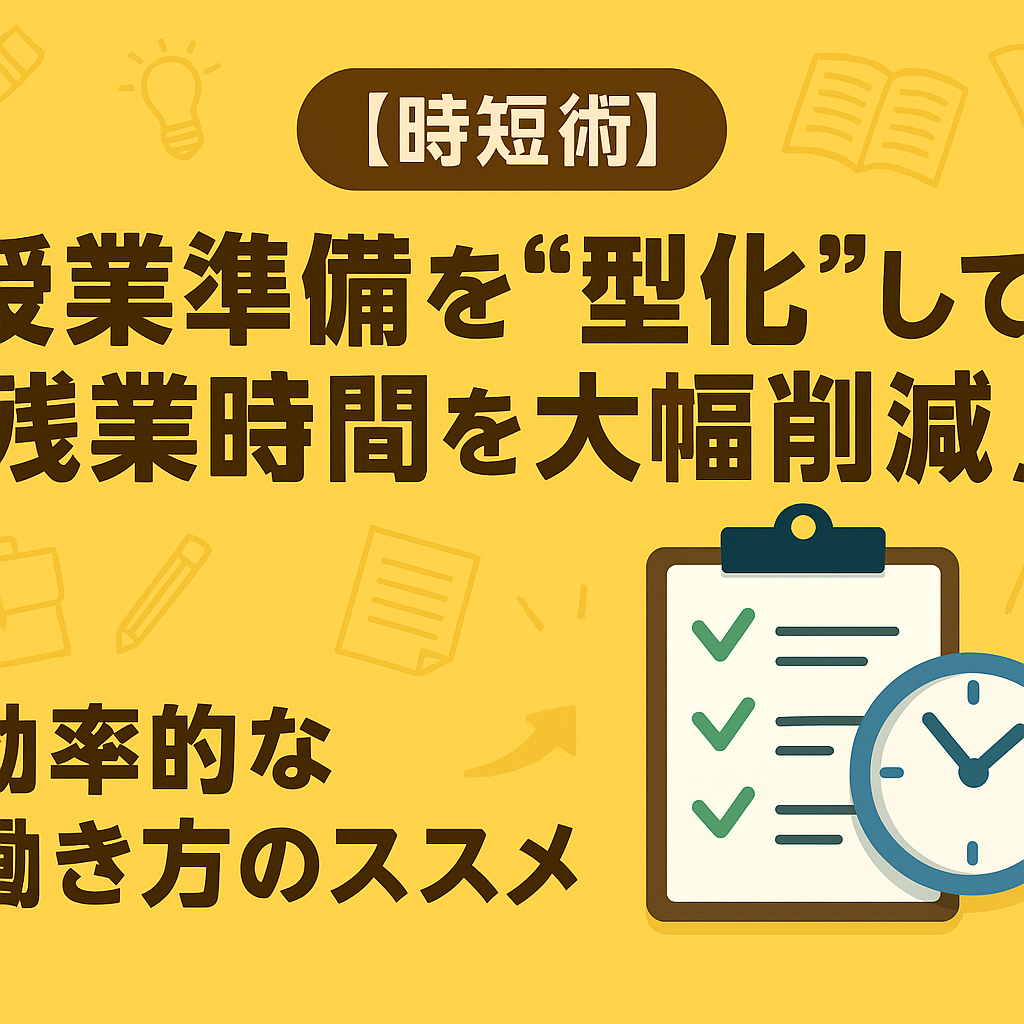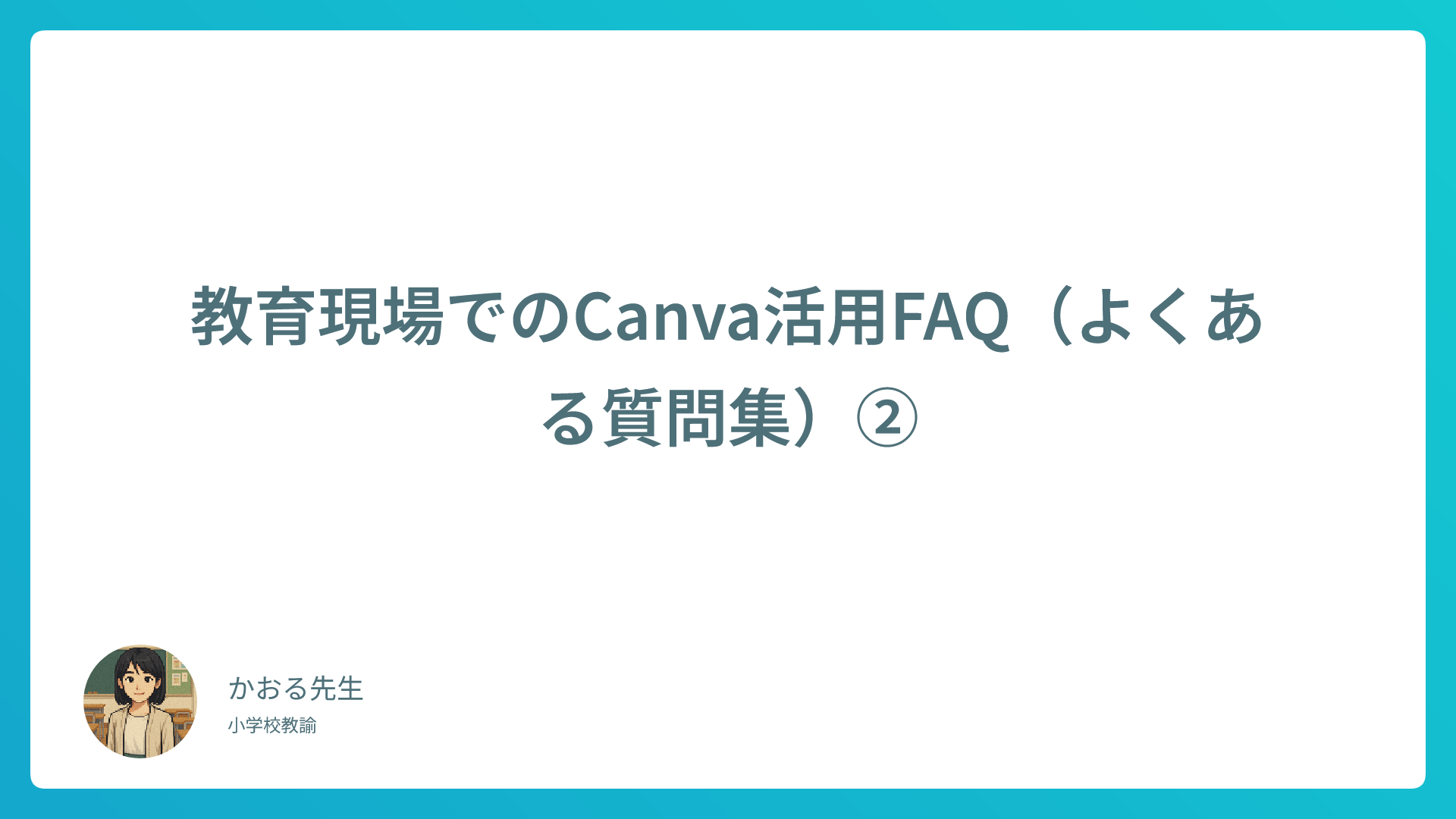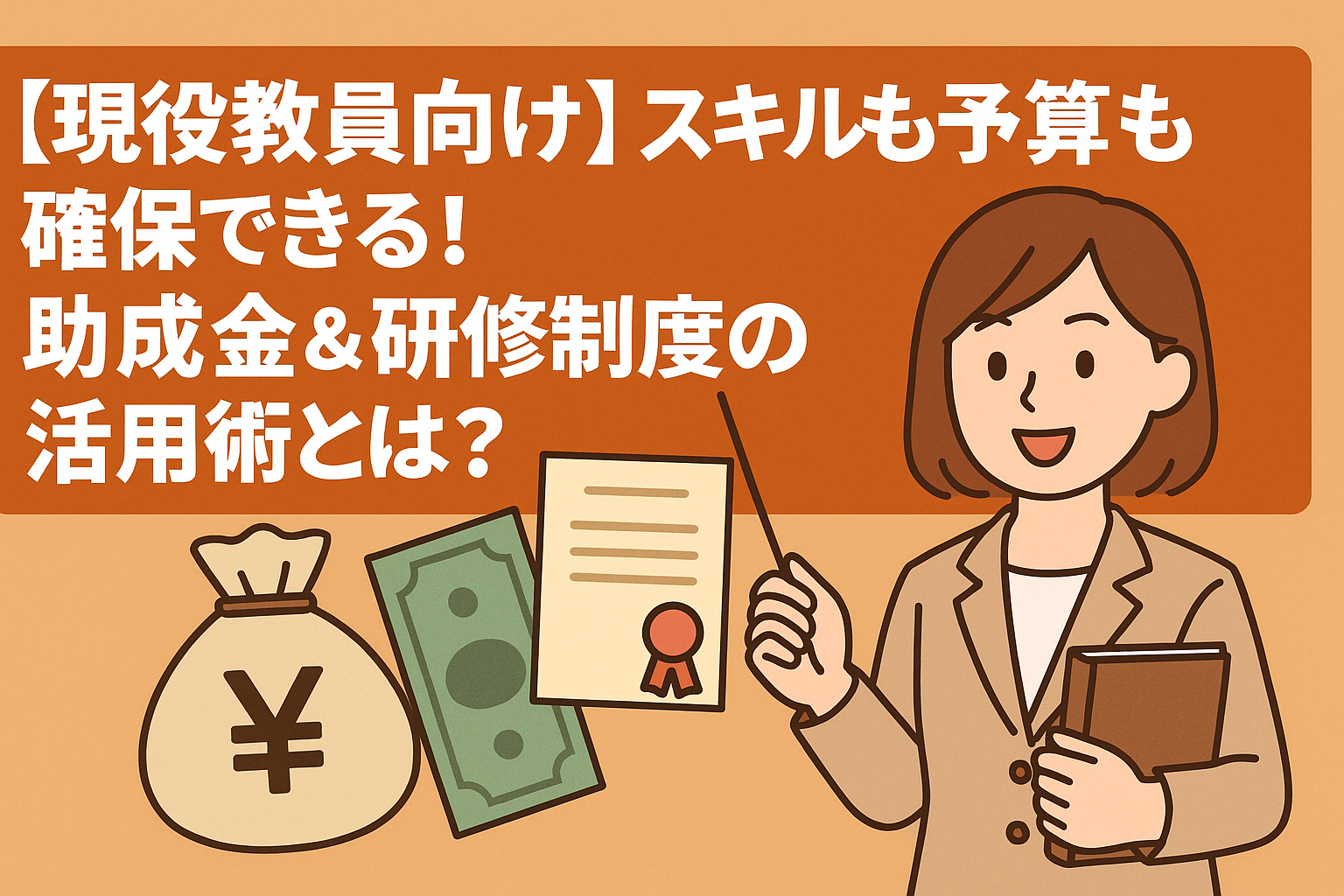【2025年版】教師の時短術|AI活用で業務をスマート化
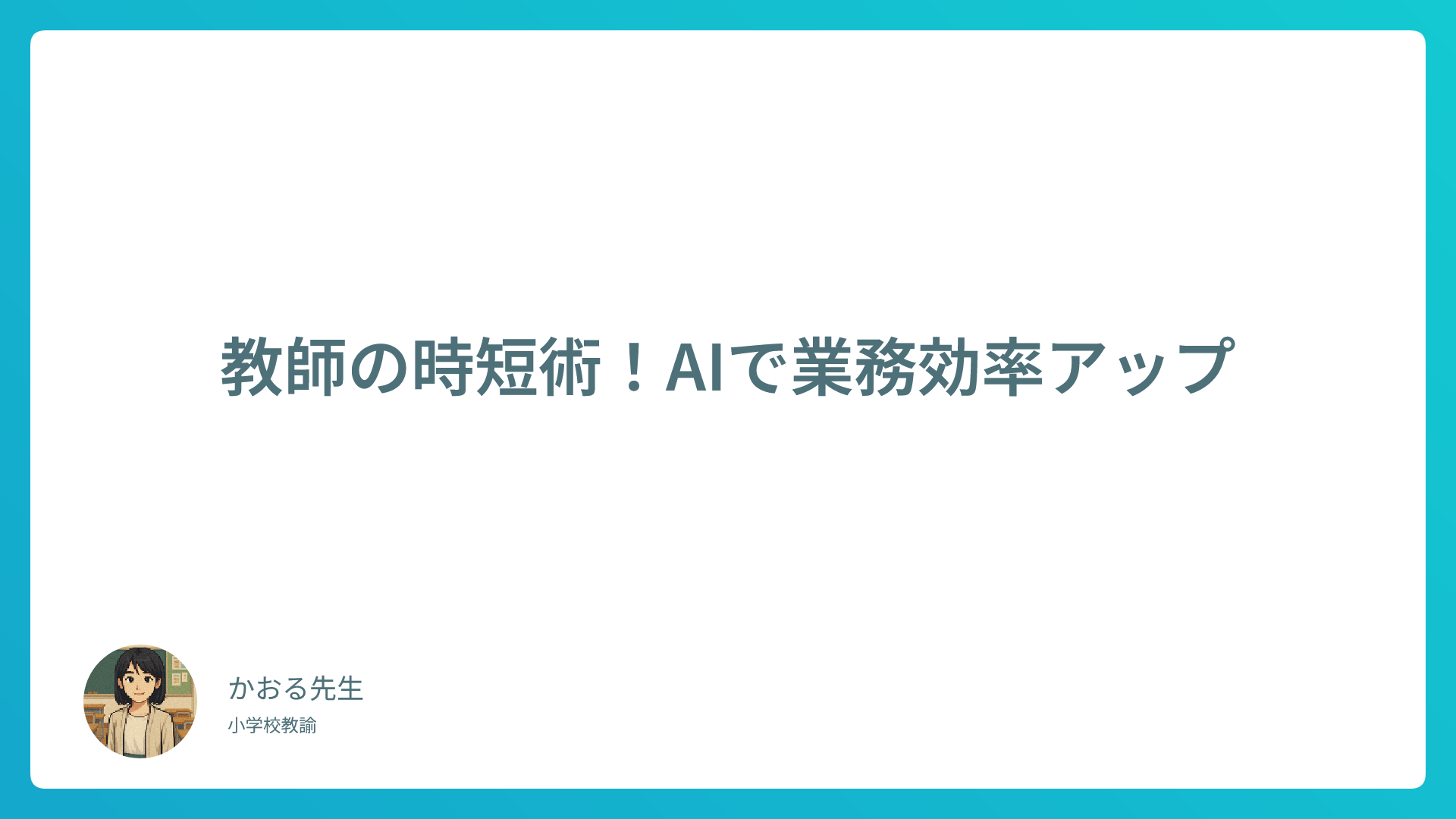
1. 教材作成の自動化
毎日の教材作りが変わった!
正直に言います。私も最初は半信半疑でした。「AIで教材?本当に使えるの?」と。でも、実際に使ってみて…これはまさに革命でした。
ある日の夜、いつものように翌日の算数プリントを作成していたとき、ふと思い立ってChatGPTに「小学4年生向けの掛け算の筆算プリントを10問作って」と依頼してみたのです。すると、たったの3分で完成。いつもなら1時間はかかっていたのに。
その瞬間、「ああ、時代が変わったんだな」と強く感じました。
実際の活用例
朝のプリント作成
コーヒーを飲みながらパソコンに向かい、「今日は分数の約分ね」と思いながら次のように入力します。
「小学5年生向けの分数の約分プリントを12問作成してください。基本問題8問、少し難しい問題4問でお願いします。答えも一緒に作ってください。」
15分後には印刷して配布できる状態に。児童が登校する前に、余裕をもって準備が整います。
理科の実験記録シート
これまでは単元ごとに手作りしていた実験記録用紙。「観察項目は?」「記入欄の大きさはどうする?」と、毎回悩んでいました。
今では「小学6年生の『水溶液の性質』実験記録シート。観察項目:色・におい・リトマス紙の変化・考察欄も含めて」と指示するだけ。あとは印刷するだけです。
実際に、6年担任の田中先生はこう話してくれました。
「理科の実験レポート用紙を作るのに毎回1時間かけていたけど、今は10分で完成。その分、実験の安全確認に時間をかけられるようになりました。」
試行錯誤してつかんだコツ
最初からうまくいったわけではありません。「算数のプリント作って」だけでは、期待する内容にはなりませんでした。
何度かやりとりを繰り返す中で、次のようなコツが見えてきました。
- 具体的に伝えることが重要
×「算数のプリント作って」
○「小学3年生向けの時計の読み方プリント。○時○分の問題8問、○時半の問題4問、基礎レベルで答えも作成してください」 - 段階的に指定することもポイント
はじめは基礎問題だけにし、慣れてきたら「基礎8問、標準4問、発展2問」と段階的に指定することで、児童の実態に合わせた調整ができます。
時間の使い方が大きく変化
以前は教材作成に週5時間かかっていましたが、今では1時間半で済んでいます。浮いた3時間半はどう使っているかというと——
児童一人ひとりのノートを丁寧に見られるようになったのです。「ここでつまずいてるな」「この子、すごく工夫した解き方をしてるな」そんな発見が増えました。
その結果、授業の内容も以前より充実してきたと実感しています。
2. コメント生成の時短術
通知表の季節も、もう怖くない
3学期末の通知表作成。以前は毎年この時期が憂鬱でした。30人分の所見欄を書き分け、しかも保護者に失礼のないよう細心の注意を払わなければならない。土日返上で、夜中まで机に向かっていました。
でも、今年は違いました。AIの力を借りることで、効率的に、かつ心のこもったコメントを作成できるようになったのです。
私の通知表作成法
まず、児童一人ひとりについて印象に残ったエピソードをメモします。
例:太郎くんの場合
- 算数の発表で独自の解法を説明
- 困っている友達を自然にサポート
- 持久走で自己ベスト更新
- 忘れ物が多いが、チェック表で改善中
このメモをもとにAIに依頼します。
「小学5年生の通知表所見を200文字程度で、成長が感じられる内容にしてください」
すると、次のような文が出力されます。
「算数では独自の解法を堂々と発表する姿が印象的でした。友達が困っているときに自然にサポートする優しさも光っています。体育の持久走では自己ベストを更新し、努力の成果を実感できたようです。忘れ物についても、チェック表を活用して改善に取り組む前向きな姿勢が素晴らしいです。」
もちろん、最終的には本人らしさを出すために手を加えますが、骨格があるので作業は大幅に短縮されます。
連絡帳コメントも効率化
毎日の連絡帳も、かつては1人5分×30人=2時間半もかかっていました。しかし今は、メモを簡単にまとめ、AIに文章化してもらうだけです。
例:花子ちゃんの場合
- メモ:「図工で集中して作品作り。友達と協力。完成を喜んでいた。」
生成結果:
「今日の図工の時間、花子さんがとても集中して作品作りに取り組んでいました。友達と協力しながら進める姿が微笑ましく、完成したときの嬉しそうな表情がとても印象的でした。」
これなら1人2分で済み、全体で1時間。1時間半の短縮です。
佐藤先生の実践
5年担任の佐藤先生も、最初は「AIに頼って大丈夫かな」と心配していたそうです。でも今ではこう話しています。
「むしろ児童のことをより深く観察するようになった。以前は『何を書こう』と悩んでいたけれど、今は『この子の良いところをどう伝えよう』と考えるようになった。観察がより具体的になったんです。」
コメント作成で大切にしていること
AIを使う際、私が特に注意しているのは次の3点です。
- 事実の正確性の確認:特に学習評価では慎重なチェックが欠かせません。
- その子らしさの表現:AIの文は整いすぎることがあるため、本人らしい表現を加えます。
- 保護者目線の意識:「この表現でどう受け取られるか」を常に考え、最終調整を行います。
時間は短縮されましたが、一人ひとりへの愛情はむしろ深まったと感じています。
個別面談の準備が「楽しみ」に変わった
かつて、保護者面談の準備は「何を話そう…」と悩む時間でした。特に、特に目立ったトラブルも課題もない児童の場合、話題に困ってしまうことも多々ありました。
しかし今では、日頃の観察メモをもとに、AIに面談資料の下書きを作ってもらっています。
例:
「学習面では計算力が安定している一方、文章題の読解に課題があります。生活面では友達への思いやりが深く、クラスのムードメーカーとして活躍しています。最近は発表にも積極的になってきました。」
このように整理された情報があることで、面談で伝えるべきポイントが明確になります。
保護者の方からも「先生、よく見てくださってるんですね」と感謝の言葉をいただくことが増えました。
同僚との情報共有も活発に
AIを使い始めてから、同僚の先生方との情報交換がより活発になりました。
「このプロンプトが使いやすかった」
「こういう指示の出し方は失敗だった」
といった知見を、月に一度の学年会で共有しています。
みんなで試行錯誤を重ねることで、学年全体の業務効率が着実に向上。新任の先生からは「こんなに余裕を持って仕事ができるとは思わなかった」という声も聞かれます。
数字で見る「変化」
具体的に、どれだけの時間が削減できたのか——週単位で記録を取っています。
週ごとの変化(概算):
| 項目 | 以前 | 現在 | 削減時間 |
|---|---|---|---|
| 教材作成 | 5時間 | 1.5時間 | 3.5時間 |
| 事務作業 | 8時間 | 3時間 | 5時間 |
| 評価業務 | 4時間 | 2時間 | 2時間 |
| 合計 | 17時間 | 6.5時間 | 10.5時間 |