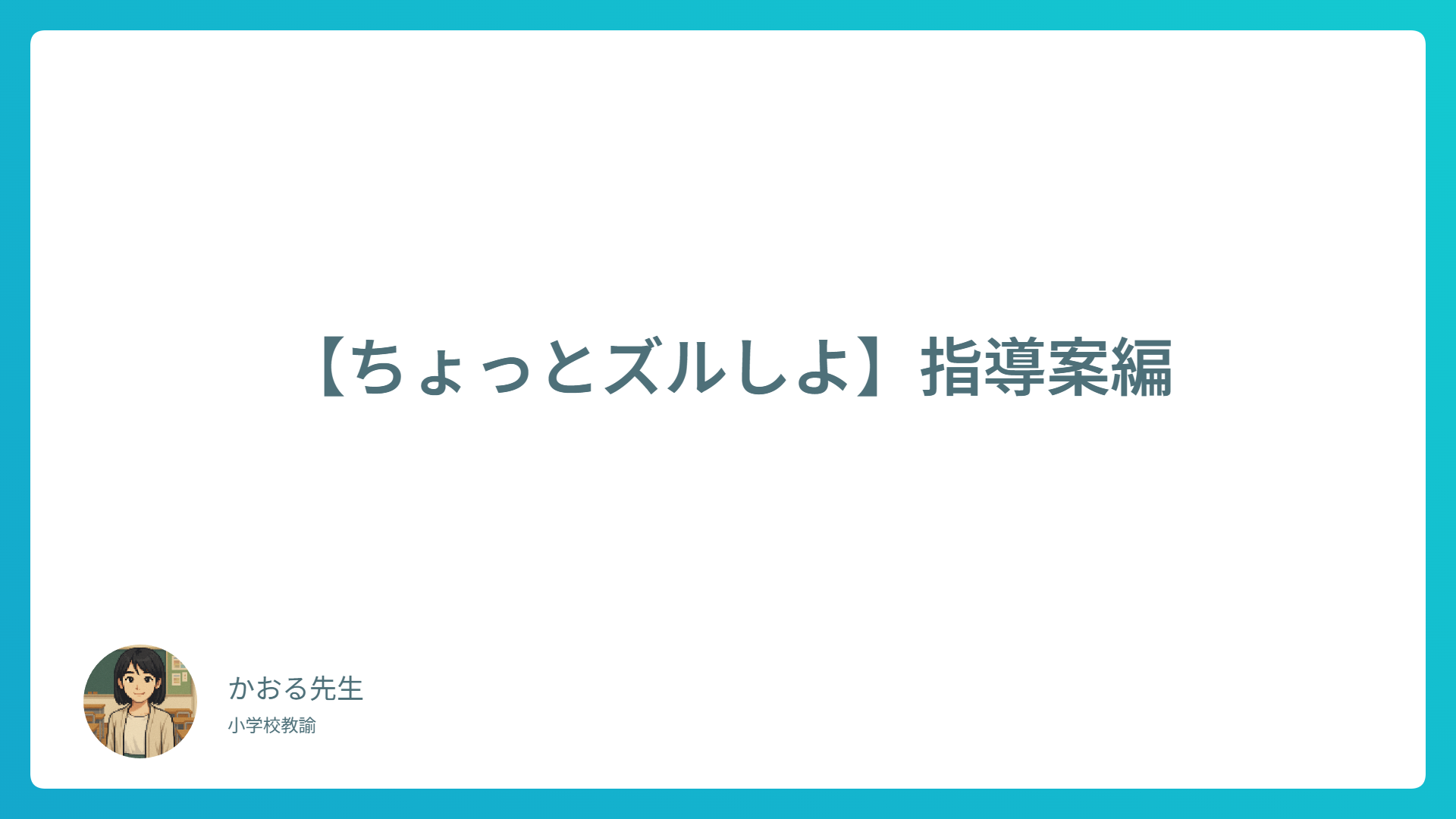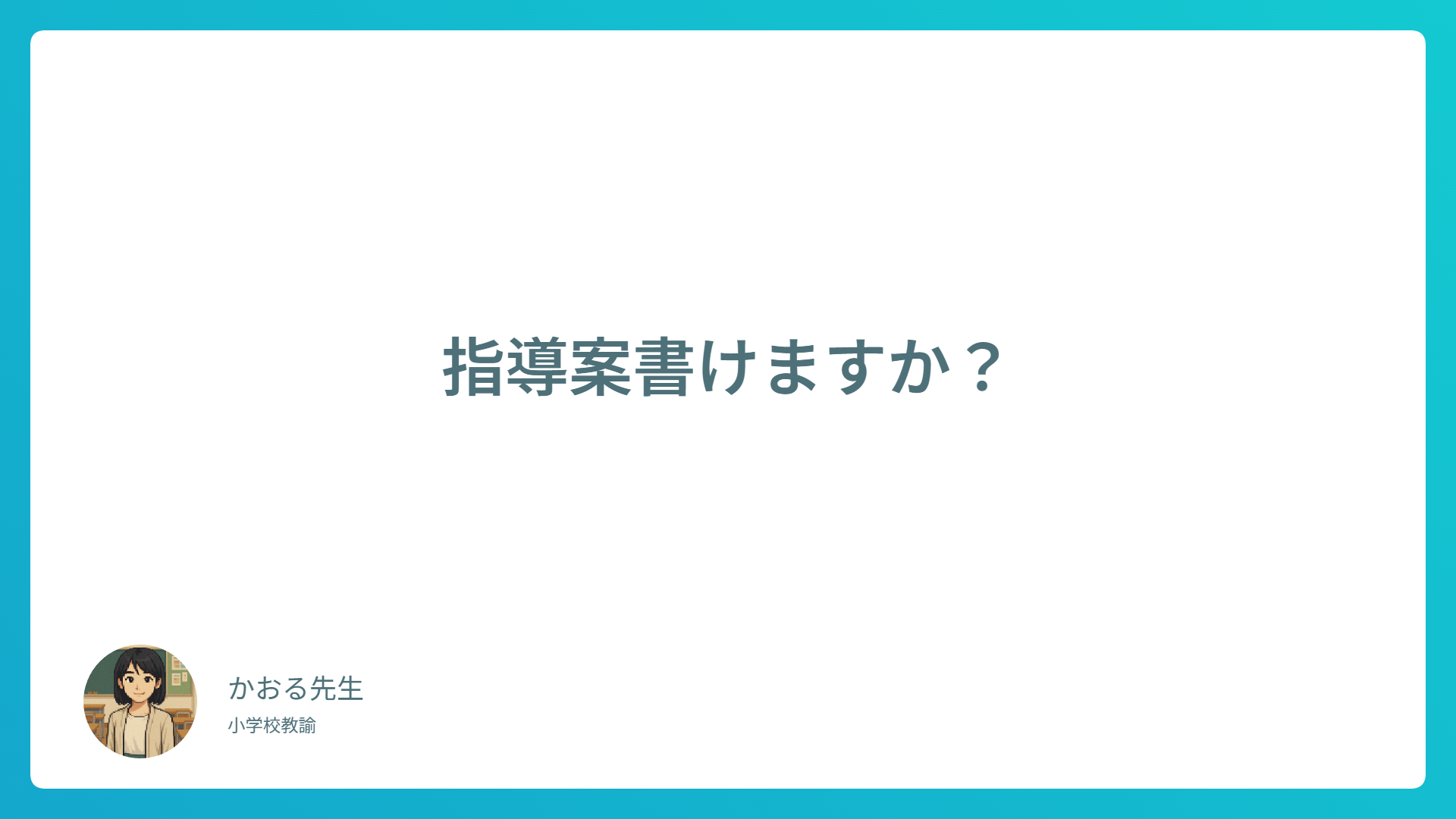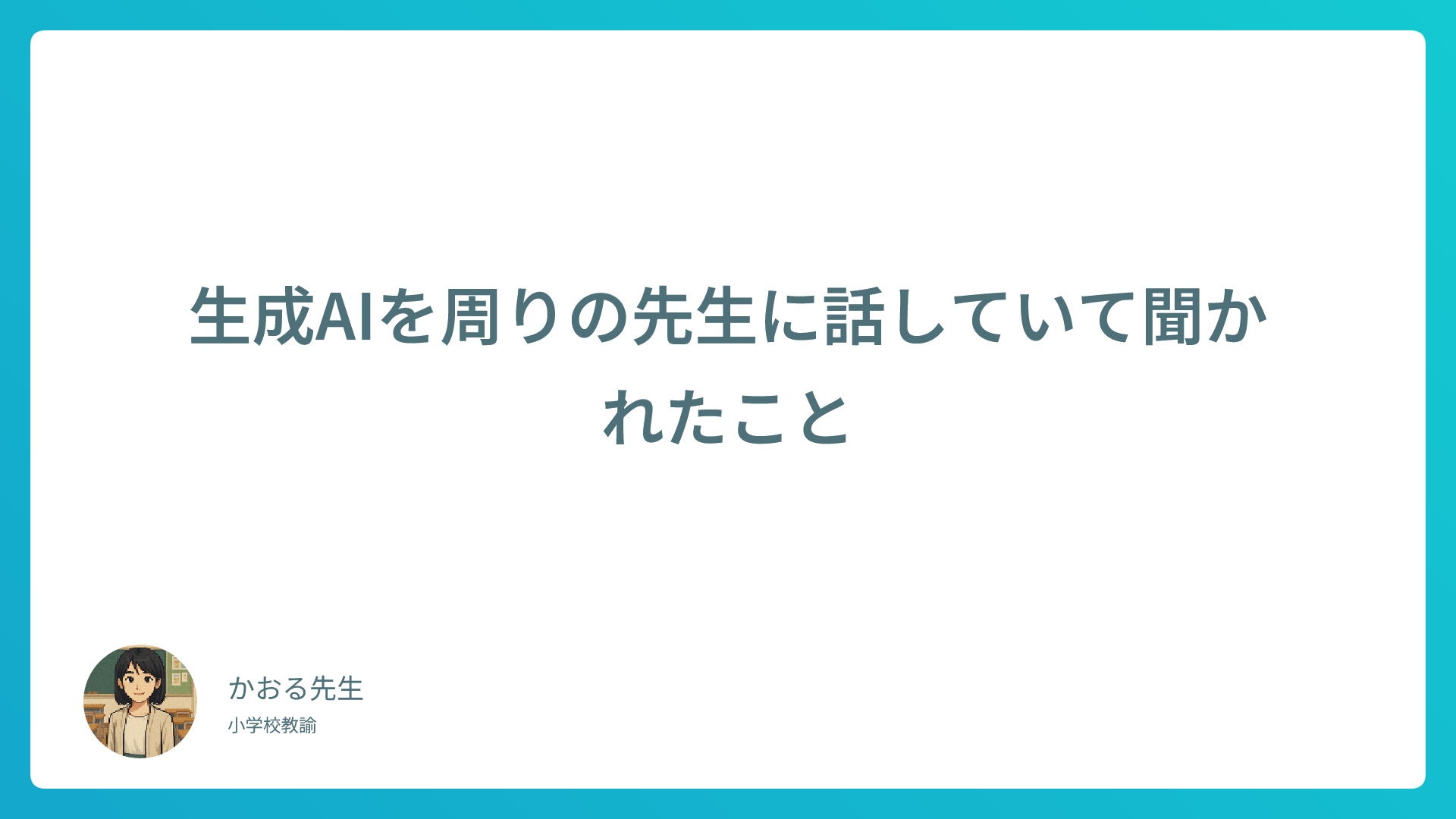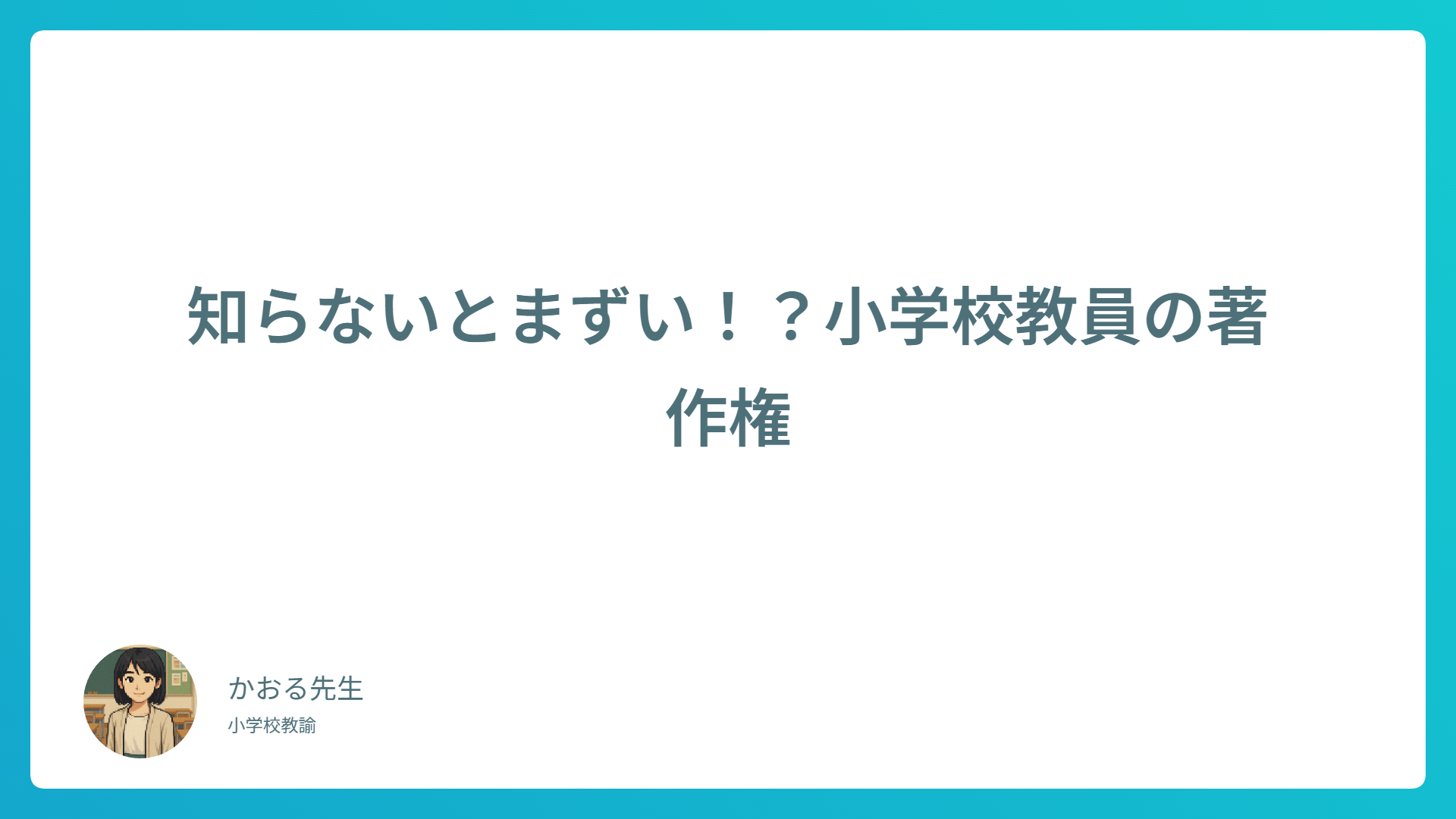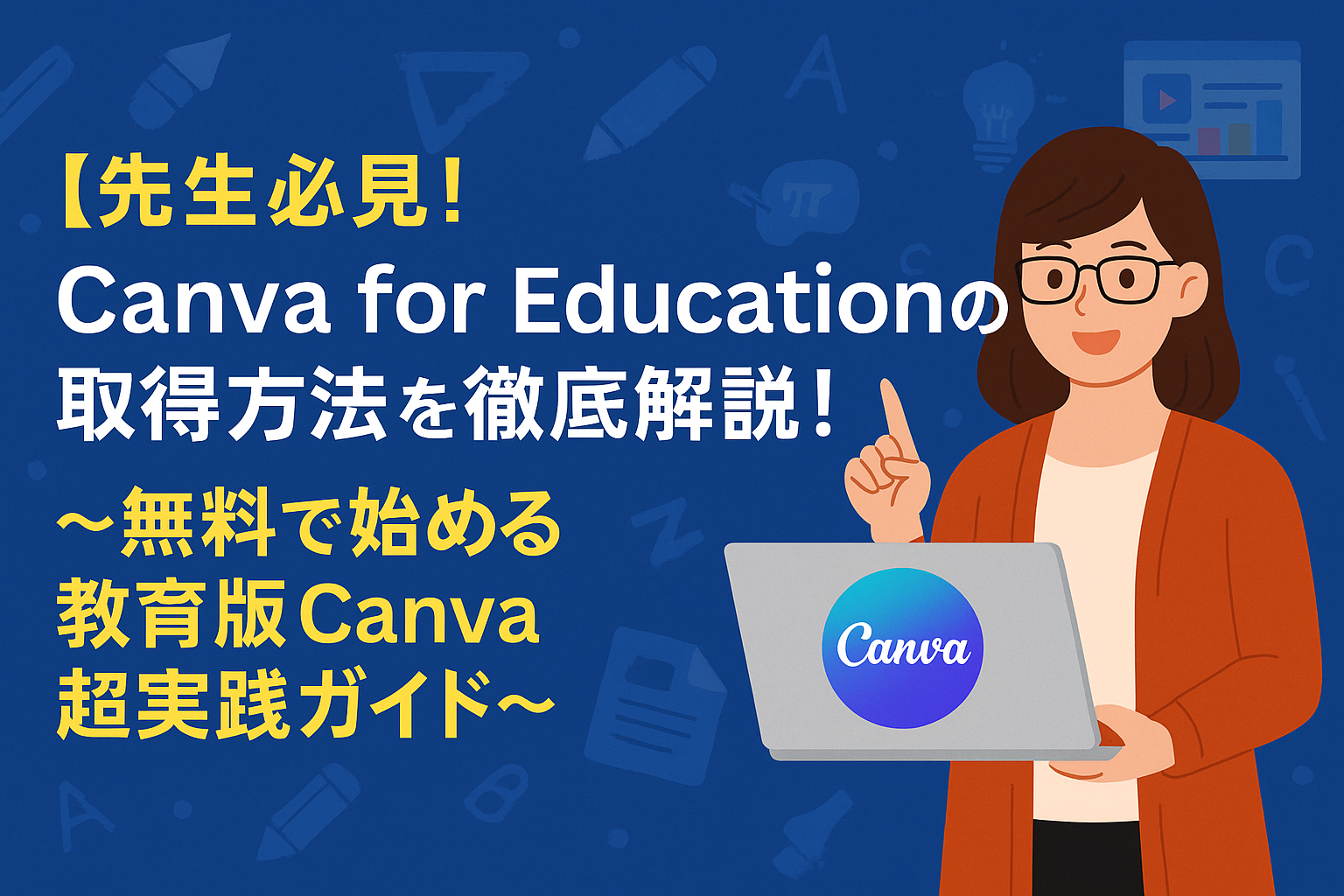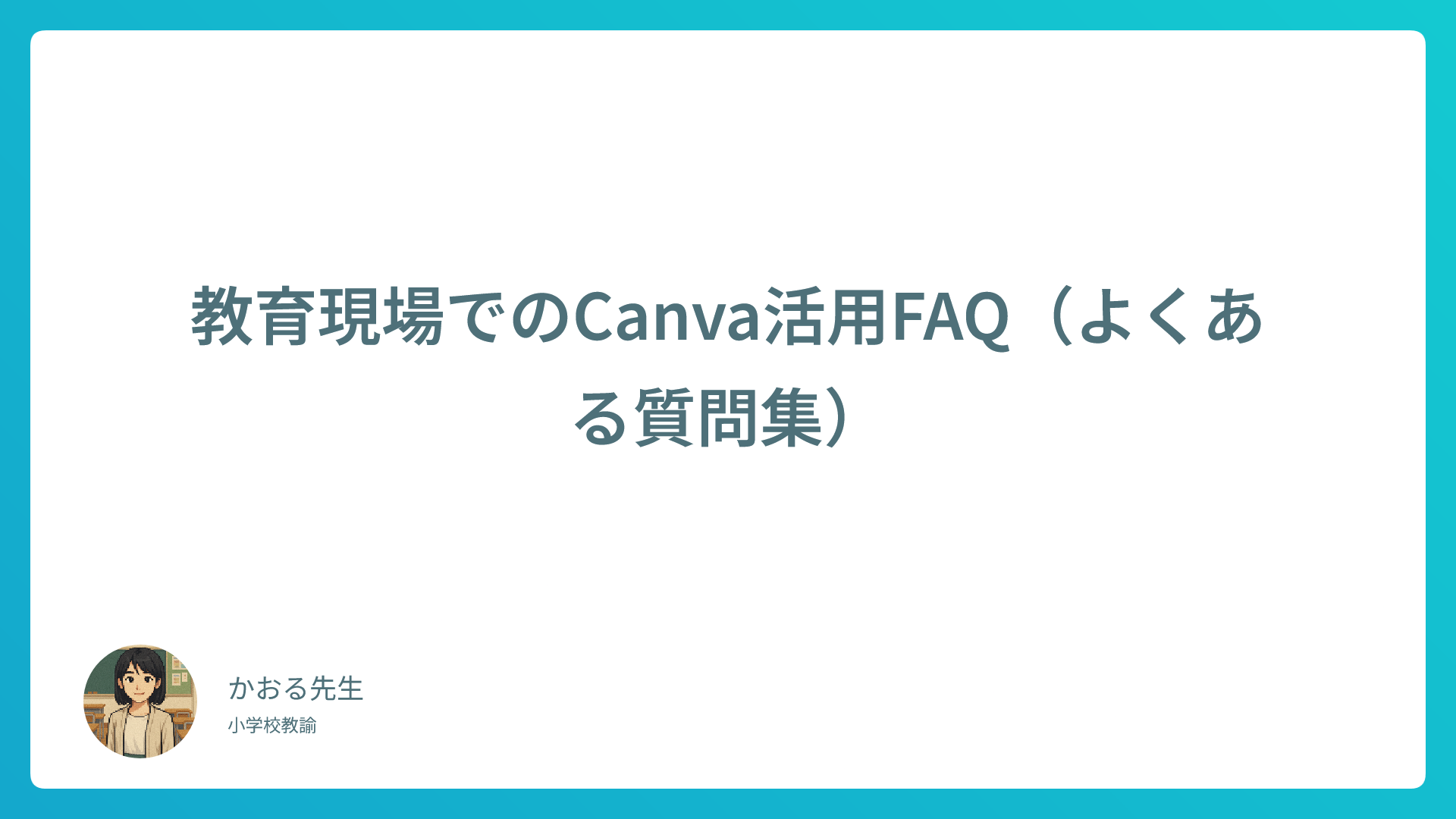【保存版】著作権法のよくある質問(FAQ)|教育・AI・ネット利用者向けに解説
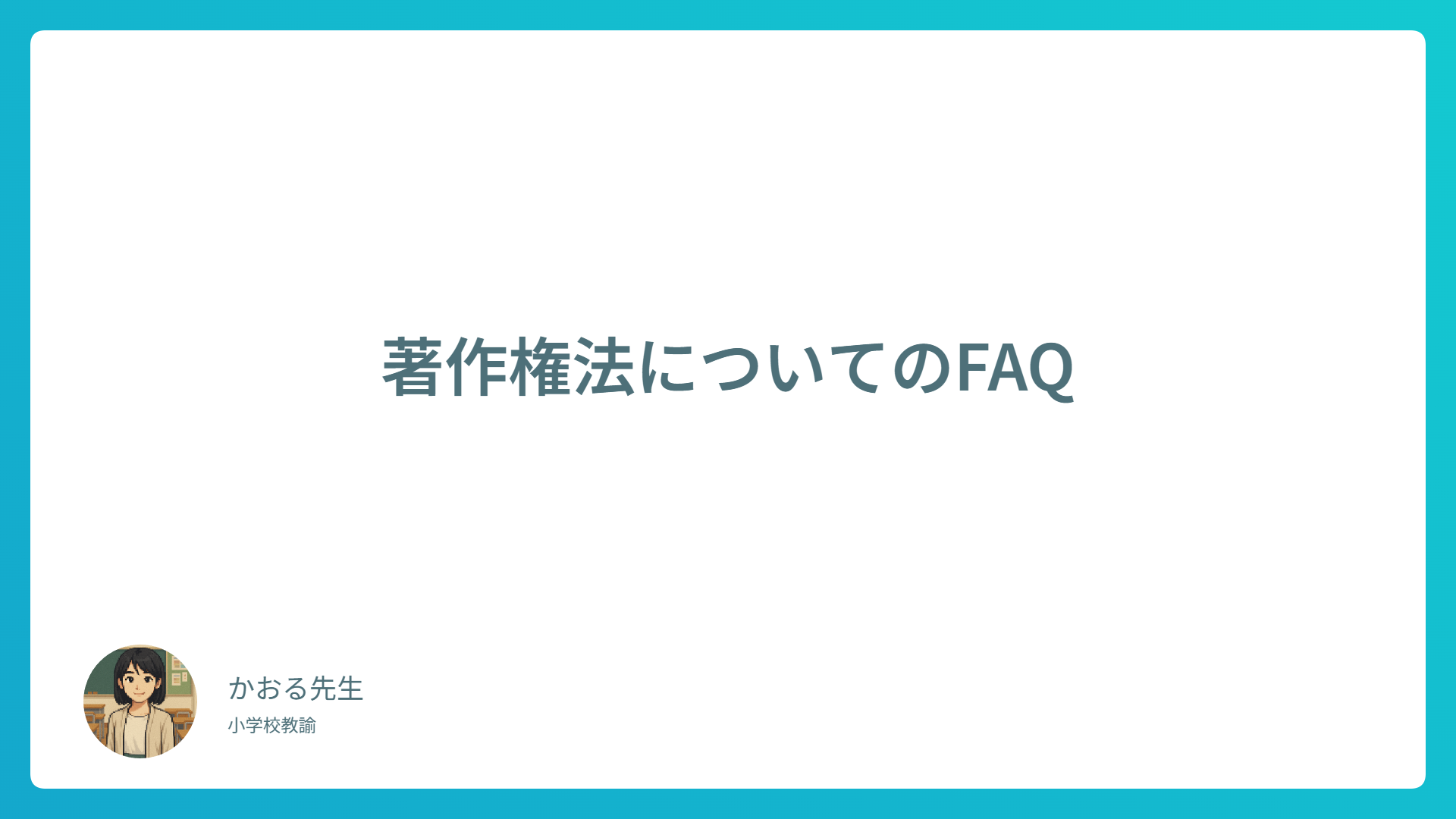
- Q1. 著作権法第30条の4における「非享受目的」とは何ですか?
- Q2. 海賊版などの違法コンテンツをAIが学習に使うことは合法ですか?
- Q3. 「作風」や「画風」は著作権で保護されますか?
- Q4. AI利用者が著作物を知らなくても、著作権侵害になることがありますか?
- Q5. RAG(検索拡張生成)は著作権上どのように扱われますか?
- Q6. 著作権者の「利益を不当に害する」とは具体的にどういうことですか?
- Q7. robots.txtなどの技術的措置で学習禁止を示している場合、法的効果はありますか?
- Q8. AIが作成した生成物は著作物として保護されますか?
- Q9. AIが著作権を侵害した場合、学習済みモデルを「廃棄」させることは可能ですか?
- Q10. なぜ日本レコード協会は著作権法第30条の4の現状に懸念を示しているのですか?
Q1. 著作権法第30条の4における「非享受目的」とは何ですか?
A:
「非享受目的」とは、著作物を自ら楽しんだり、他人に楽しませたりすること(鑑賞、視聴、読書など)を目的としない利用を指します。
AIの学習や情報解析など、内容そのものを鑑賞する意図がない技術的・実用的な利用が該当します。
Q2. 海賊版などの違法コンテンツをAIが学習に使うことは合法ですか?
A:
原則としてNGです。
素案では「厳に慎むべき」とされていますが、法的な明確性に欠けています。
権利者団体(日本映像ソフト協会など)は、明確な禁止と罰則の導入を強く求めています。
Q3. 「作風」や「画風」は著作権で保護されますか?
A:
現行の著作権法では、「作風」や「画風」は保護されないアイデアの領域とされています。
一方、権利者団体は「作風も経済的価値を持つ」として、保護の拡大を求める声が強まっています。
Q4. AI利用者が著作物を知らなくても、著作権侵害になることがありますか?
A:
はい。AIが学習段階で当該著作物を使っていた場合、AI利用者が認識していなくても「依拠性」が推定される可能性があります。
これは、AIの出力が著作物に類似していた場合に問題となります。
Q5. RAG(検索拡張生成)は著作権上どのように扱われますか?
A:
RAGは、検索結果を取り込み生成AIが回答を作る仕組みです。
この出力が創作的表現を含む著作物の一部である場合、「非享受目的」には当たらず、著作権者の許諾が必要になる可能性があります。
Q6. 著作権者の「利益を不当に害する」とは具体的にどういうことですか?
A:
以下のような場合が該当します:
- 作風が似たAI作品が大量に生成され、需要が代替される
- 将来販売予定の情報解析用データベースの内容を、無断でAIが複製して学習
- 海賊版であることを知りながらAIに学習させる行為
Q7. robots.txtなどの技術的措置で学習禁止を示している場合、法的効果はありますか?
A:
素案では、robots.txtのような技術的措置が講じられており、かつ将来の販売予定があると推認される場合は、そのデータの無断学習は違法と判断される可能性があるとされています。
ただし、単なる「意思表示」だけでは権利制限の対象から除外されるとは限りません。
Q8. AIが作成した生成物は著作物として保護されますか?
A:
場合によります。
AIに対する指示の工夫、出力の取捨選択など、人間の創作的寄与が十分にある場合には著作物性が認められる可能性があります。
Q9. AIが著作権を侵害した場合、学習済みモデルを「廃棄」させることは可能ですか?
A:
原則として学習済みモデルは廃棄対象にはなりません。
著作権法112条第2項にある「侵害の行為によって作成された物」には該当しないと解釈されています。
Q10. なぜ日本レコード協会は著作権法第30条の4の現状に懸念を示しているのですか?
A:
同協会は、2018年の法改正(第30条の4)は「市場に影響を与えない」利用を前提にしたが、生成AIは膨大な著作物を学習して短時間で類似コンテンツを量産できるとし、改正趣旨と現状が乖離していると懸念しています。