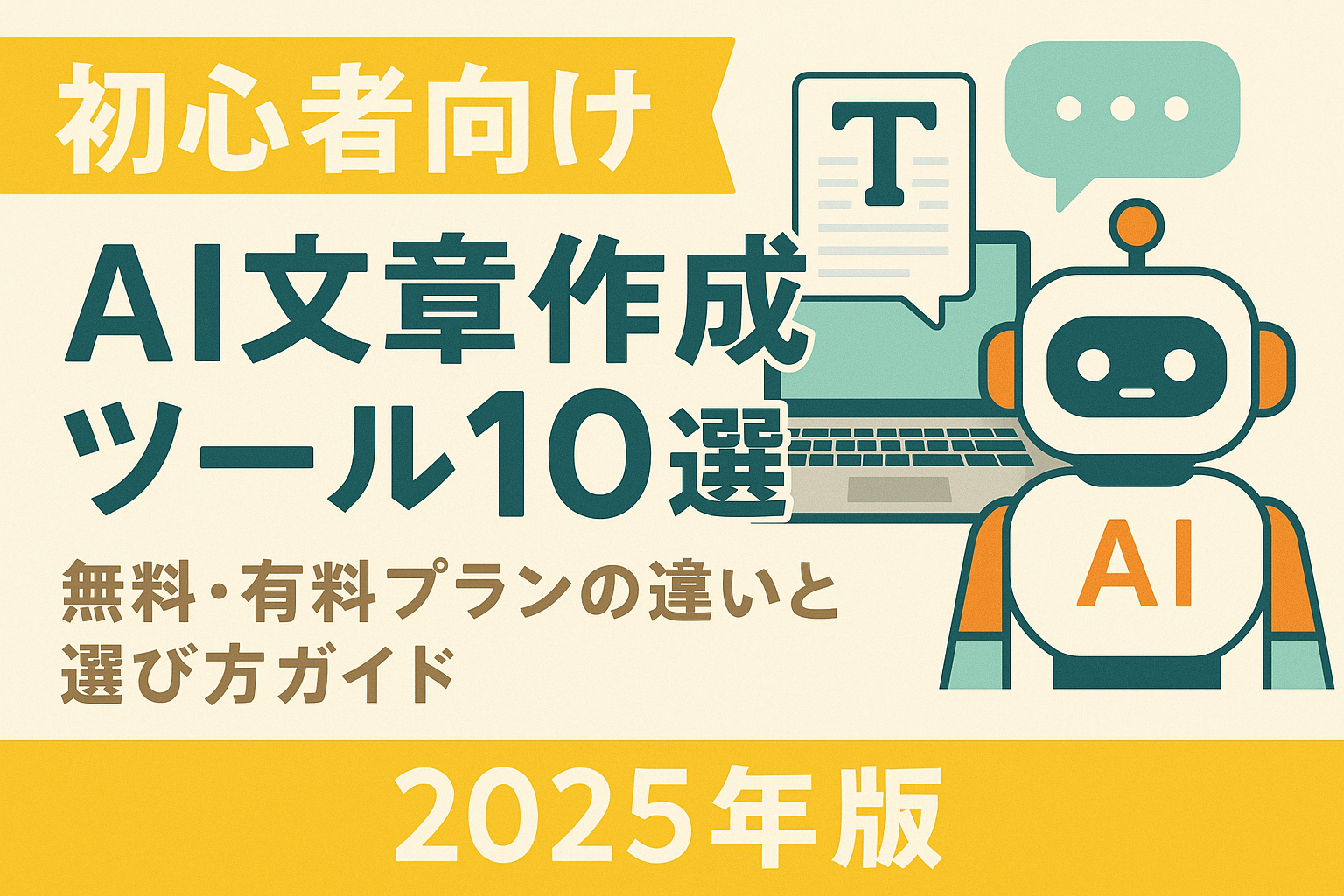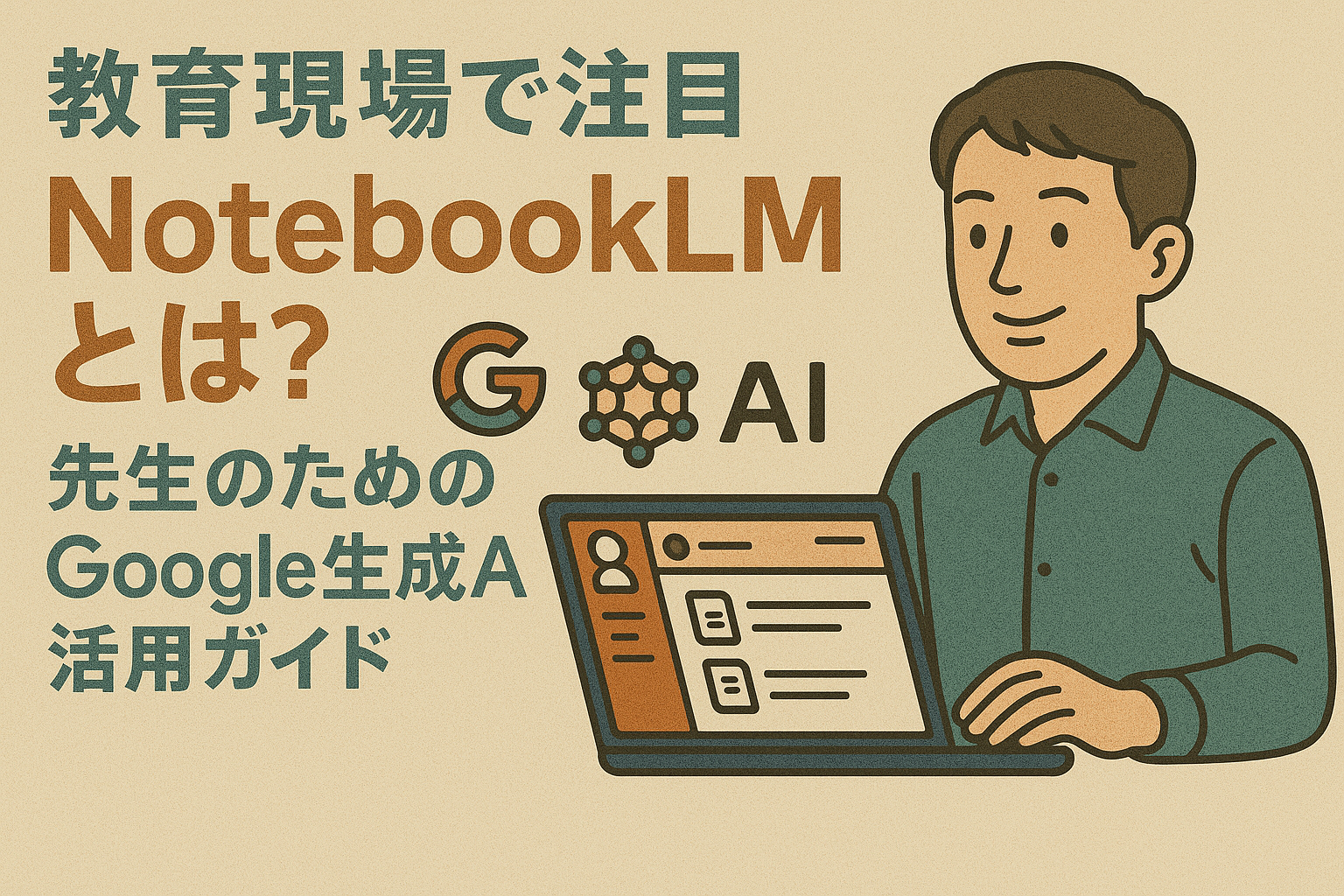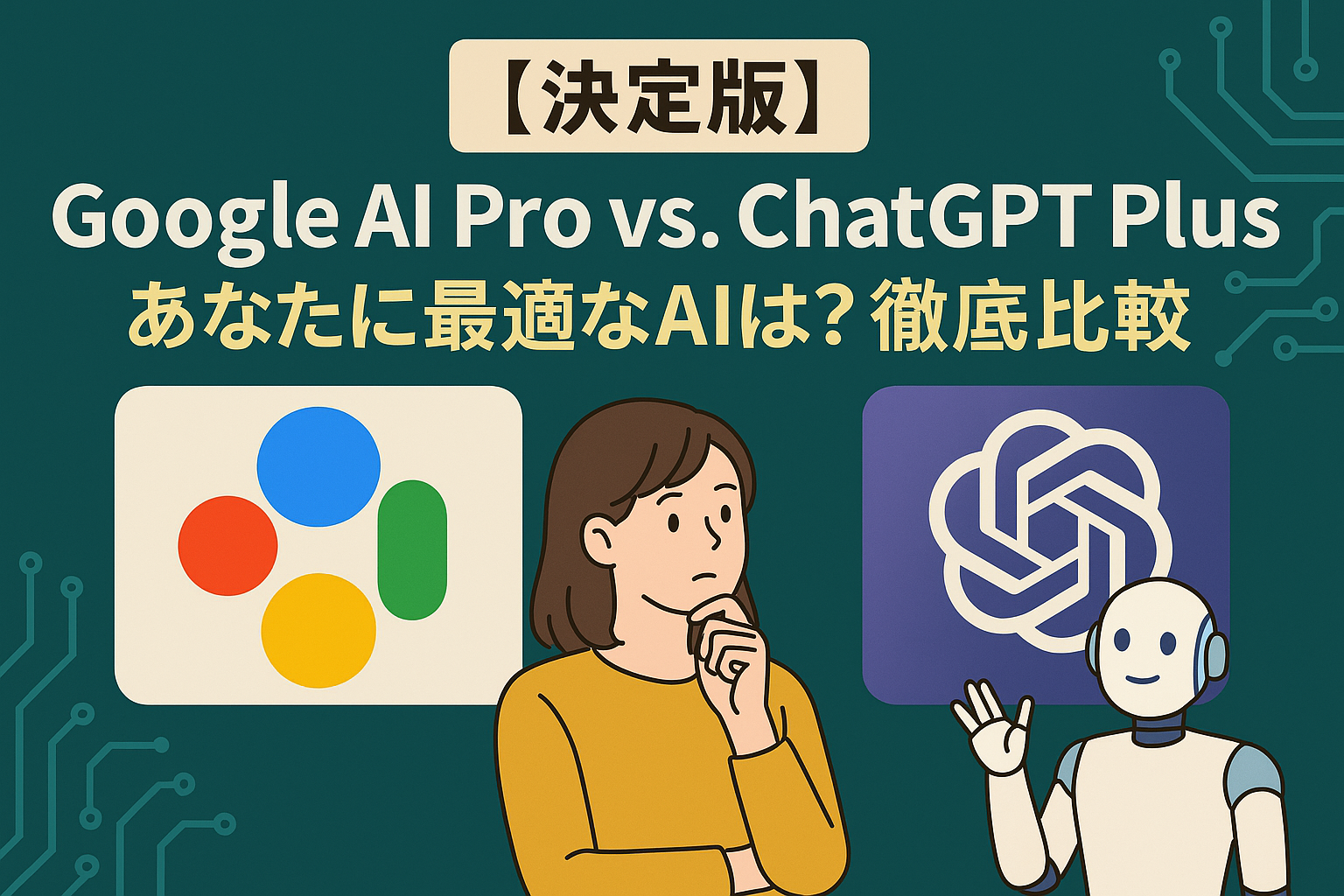教育現場で注目のNotebookLM活用術|教材研究・授業準備が驚くほど効率化!
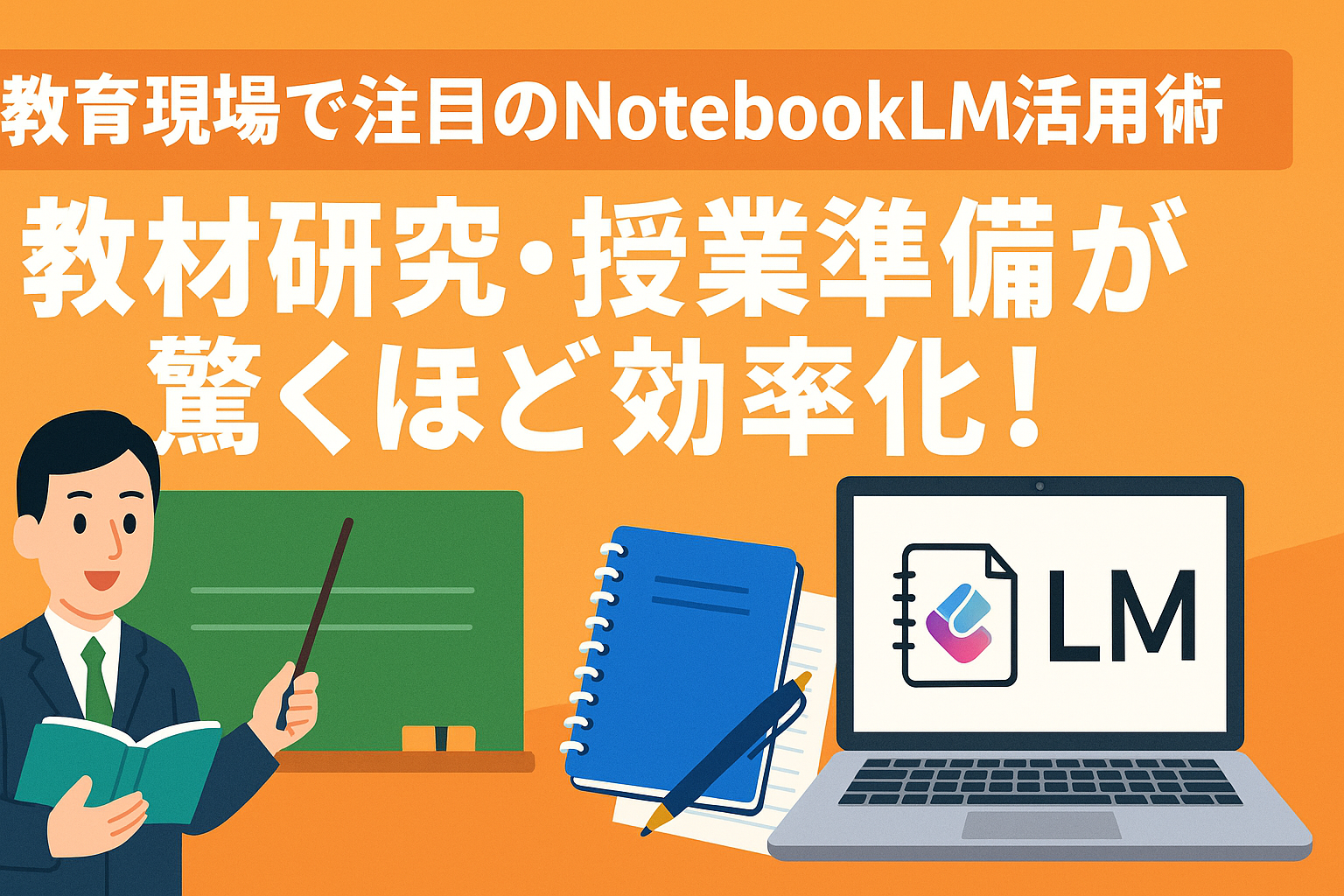

あーまた教科書やってるだけの授業になっちゃう……

教科者の内容をしっかりできているのであれば全く問題ないように思いますが……

ちがうんですそうじゃないんです。子どもたちが学びやすく興味を持てるように、より楽しく学べるようにしたいんです‼

なるほど、ではこれを紹介します!
先生方、日々の教材研究、本当にお疲れ様です。新しい単元の準備、既存教材の深掘り、生徒の興味を引くアイデア探し…限られた時間の中で、質の高い授業を準備するのは至難の業ですよね。
「もっと効率よく、しかも深く教材研究ができたら…」
そう思っている先生に朗報です!Googleが開発した新しいAIツール、NotebookLM(ノートブックLエム)が、皆さんの教材研究を劇的に変える可能性を秘めています。
NotebookLMって何?教材研究にどう役立つの?
NotebookLMは、皆さんがアップロードしたPDFファイル、Googleドキュメント、テキストファイル、ウェブサイトなどの情報を読み込み、それらを元に質問に答えたり、要約したり、新しいアイデアを生成したりできるAIツールです。
「それって、ただの要約ツール?」と思った方もいるかもしれません。いえいえ、NotebookLMの真価は、複数の資料を横断的に分析し、先生の「思考」をサポートしてくれる点にあります。
教材研究において、NotebookLMはこんな場面で強力な味方になります。
- 資料の整理と把握の高速化: 大量の参考資料や指導要領、教科書などをアップロードするだけで、AIが内容を瞬時に把握し、必要な情報を見つけやすくしてくれます。
- 多角的な視点の獲得: 特定のテーマについて、複数の資料から関連する情報を抽出し、新たな切り口や論点を提案してくれます。
- 発問や導入アイデアの創出: 教材の内容に基づいて、生徒の思考を深めるような発問や、授業の冒頭で生徒の関心を惹きつける導入アイデアをブレインストーミングできます。
- 宿題や課題作成のヒント: 単元内容から派生する演習問題や、探究活動のテーマなどを提案してもらうことも可能です。
NotebookLMを教材研究で使ってみよう!具体的な活用例
では、実際にNotebookLMを教材研究でどのように活用できるのか、具体的な例を見ていきましょう。
1. 資料の要約と情報整理で教材の全体像を掴む
新しい単元の準備や、複雑な専門資料の理解に時間がかかっていませんか?NotebookLMを使えば、膨大な資料を素早く整理し、必要な情報を効率的に把握できます。
【準備するもの】
- 指導要領(該当学年・教科の部分)
- 教科書(単元の該当ページ)
- 教師用指導書
- 参考となる専門書やウェブサイトの記事(PDF化またはテキストコピー)
- 通知・通達資料、研修資料など
これらの資料をすべてNotebookLMにアップロードします。
【プロンプト(指示)の例】
- 「この単元(例:『物語の読み深め方』)の学習指導要領における目標は何ですか?」
- 「この教科書では、この単元をどのような流れで教えていますか?主要な活動と評価ポイントを教えてください。」
- 「複数の資料を統合し、この単元で生徒に身につけてほしい最も重要な力は何だと思いますか?」
- 「この複雑な学習指導要領を、小学校教員向けに分かりやすく要約してください。」
2. 発問と導入アイデアを練り、授業を魅力的にする
生徒の関心を引きつけ、深い思考を促す発問や導入アイデアは、授業の質を大きく左右します。NotebookLMが、先生のアイデア出しを強力にサポートします。
【準備するもの】
- 教材として使用する文章や図、写真など
- 単元目標
【プロンプト(指示)の例】
- 「この文章(アップロードした教材の一部)を読んだ生徒に、思考を深めさせるための発問を5つ提案してください。特に、多様な意見を引き出すような問いをお願いします。」
- 「この単元(例:『生物の多様性』)の導入で、生徒が興味を持つような具体的な例や、導入活動のアイデアを3つ提案してください。身近な例を交えてください。」
- 「この単元に出てくる〇〇(キーワード)について、生徒が『なぜ?』と疑問を持つようなトリビアを教えてください。」
- 「この作品のテーマや登場人物について、生徒に考えさせるためのディスカッション用質問を生成してください。」
- 「この内容に関する確認テストやクイズ(例:Kahoot!)の問題を自動で作成してください。」
3. 宿題や発展的な学習活動を考える
授業内容をさらに深めたい時や、個別最適化された学びを提供したい時にも役立ちます。
【準備するもの】
- 授業で使用した教材や板書内容(写真やPDFでも可)
- 単元目標
【プロンプト(指示)の例】
- 「この単元(例:『日本の地形』)の学習内容を踏まえ、生徒が家庭で取り組めるような探究活動のテーマを3つ提案してください。」
- 「この単元の内容を応用した、実践的な課題を考えてください。例を挙げながら具体的に記述してください。」
- 「このテーマ(例:『食料問題』)について、生徒がさらに深く学ぶためのおすすめの書籍やウェブサイトをいくつか教えてください。」
4. 多様な形式のコンテンツを活用する
NotebookLMは、テキストだけでなく、YouTube動画や音声データも活用できます。
【活用例】
- オンライン研修や講演会の要約: 1時間以上あるオンライン研修のアーカイブや、スマートフォンの録音データをアップロードし、要点を短時間でまとめることができます。忙しい放課後に全て見返す手間が省けます。
- 「Audio Overview(音声概要)」の活用: アップロードした資料から、ポッドキャスト風の音声コンテンツを生成できます。これは授業後の復習教材として生徒に配布したり、反転授業の予習教材として活用したりするのに便利です。
5. 教科別の具体的な活用例
NotebookLMは、どの教科でも強力なツールになります。
- 国語: 複数の物語の比較分析、児童文学作品の読解指導、あらすじの要約、登場人物の心情分析、質問生成、単元計画や各時間の詳細な授業計画の作成など。
- 社会: 授業内容に関連する資料の要約、キーワード抽出、地理情報の活用、複数の資料からの情報統合、学習計画の作成(時間配分、発問、指示、留意事項を含む)。
- 算数: 教科書と参考書の単元解説の比較、過去のテスト問題分析、難解な問題の解説作成。
- 理科: 複数の科学論文の要約と比較、実験手順書の作成補助、実験結果データの解析。
NotebookLM活用のコツと注意点
- 質の良い情報をインプット: AIの回答は、インプットされた情報に大きく左右されます。信頼性の高い資料をアップロードすることが重要です。
- 具体的なプロンプトで精度アップ: 漠然とした質問よりも、「〇〇について、△△の視点から〇字程度で」といった具体的な指示を出すほど、求めている回答に近づきます。
- ソースの明示を確認: NotebookLMは、回答の根拠となる元の資料の箇所(ページなど)をリンクで示してくれます。AIの回答が本当に合っているか、簡単に検証できるので、必ず確認しましょう。
- 生成された内容は必ず確認・修正: NotebookLMはあくまでAIです。生成された内容が必ずしも完璧とは限りません。必ず先生ご自身の目で内容を確認し、必要に応じて加筆修正を行ってください。特に、誤情報が含まれていないか、指導要領に沿っているかなどは入念にチェックしましょう。
- 個人情報や機密情報のアップロードは避ける: 生徒の個人情報や、外部に公開すべきではない機密性の高い情報は絶対にアップロードしないでください。
- アクセスと費用: 2025年4月3日からは、Google Workspace for Educationの「Core Service」として提供されており、エンタープライズグレードのデータ保護が施されています。現在(2025年7月26日時点)は18歳以上が利用可能ですが、2025年8月13日にはすべての年齢の教育ユーザーに拡大予定です。基本機能は無料で利用できますが、将来的な有料化の可能性も示唆されています。また、個人アカウントでのログインが必要な場合があるので、自治体から貸与されたアカウントではログインできないケースもあります。
まとめ:NotebookLMで「考える時間」を増やそう
NotebookLMは、先生方の「資料を読む」「情報を整理する」「アイデアを出す」といった時間を大幅に削減し、本当に「考えるべき時間」を創出してくれる強力なツールです。
もちろん、AIが先生の代わりになるわけではありません。しかし、AIを上手に活用することで、教材研究の質を高め、先生自身の負担を減らし、最終的には子どもたちへのより良い学びへと繋がります。
ぜひ、今日からNotebookLMを皆さんの教材研究に活用して、新しい可能性を探ってみてください!きっと、日々の業務がもっと豊かになりますよ。