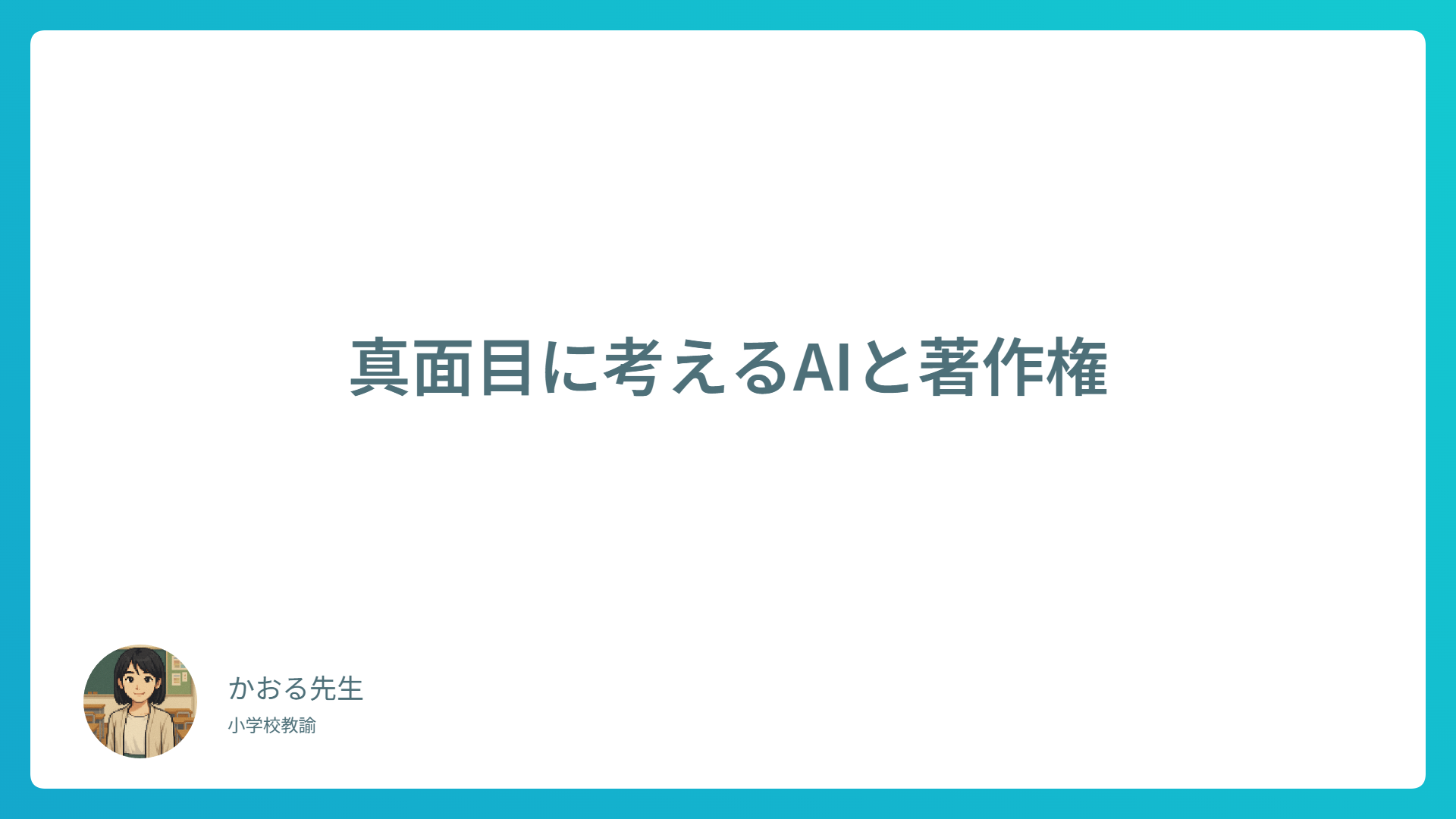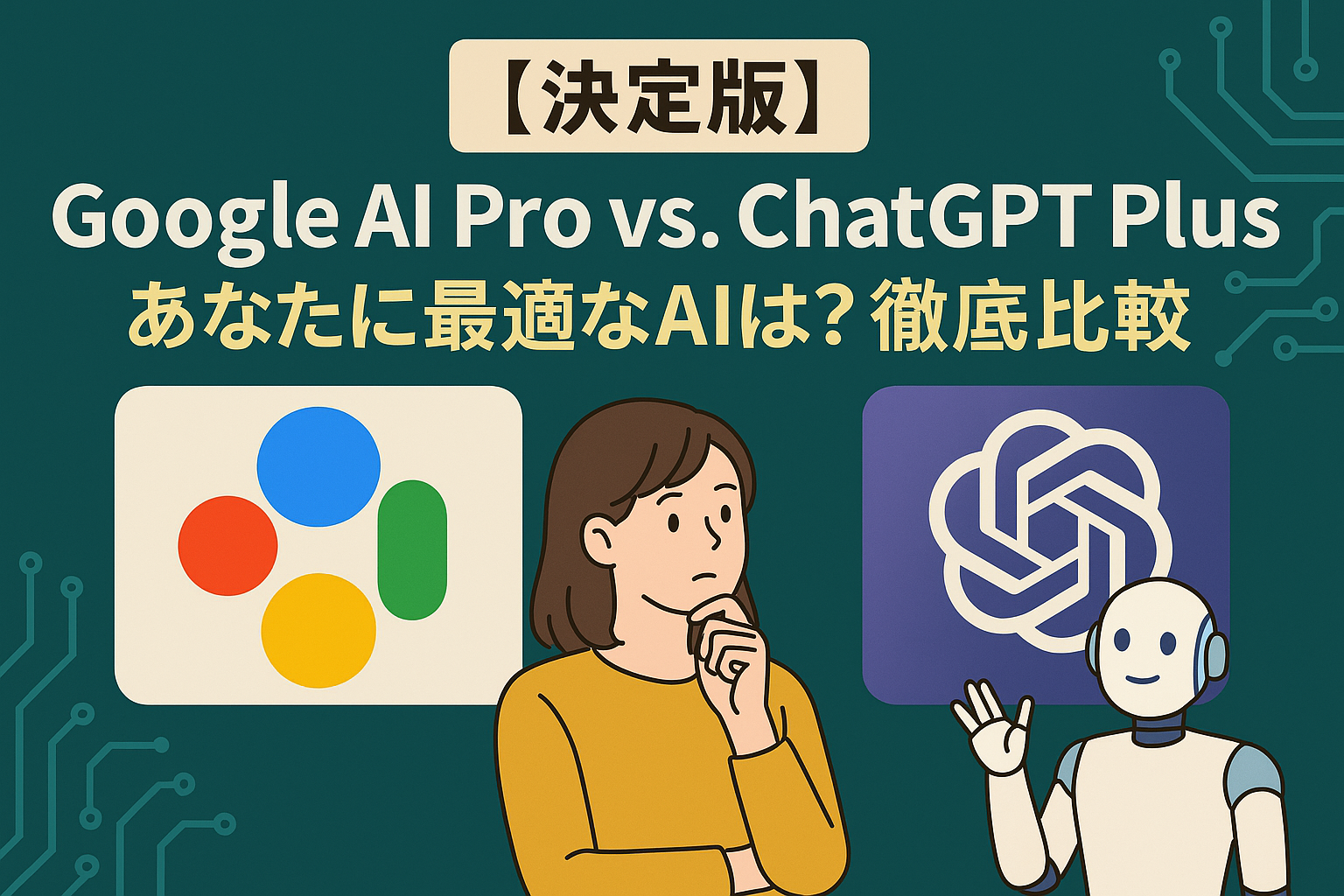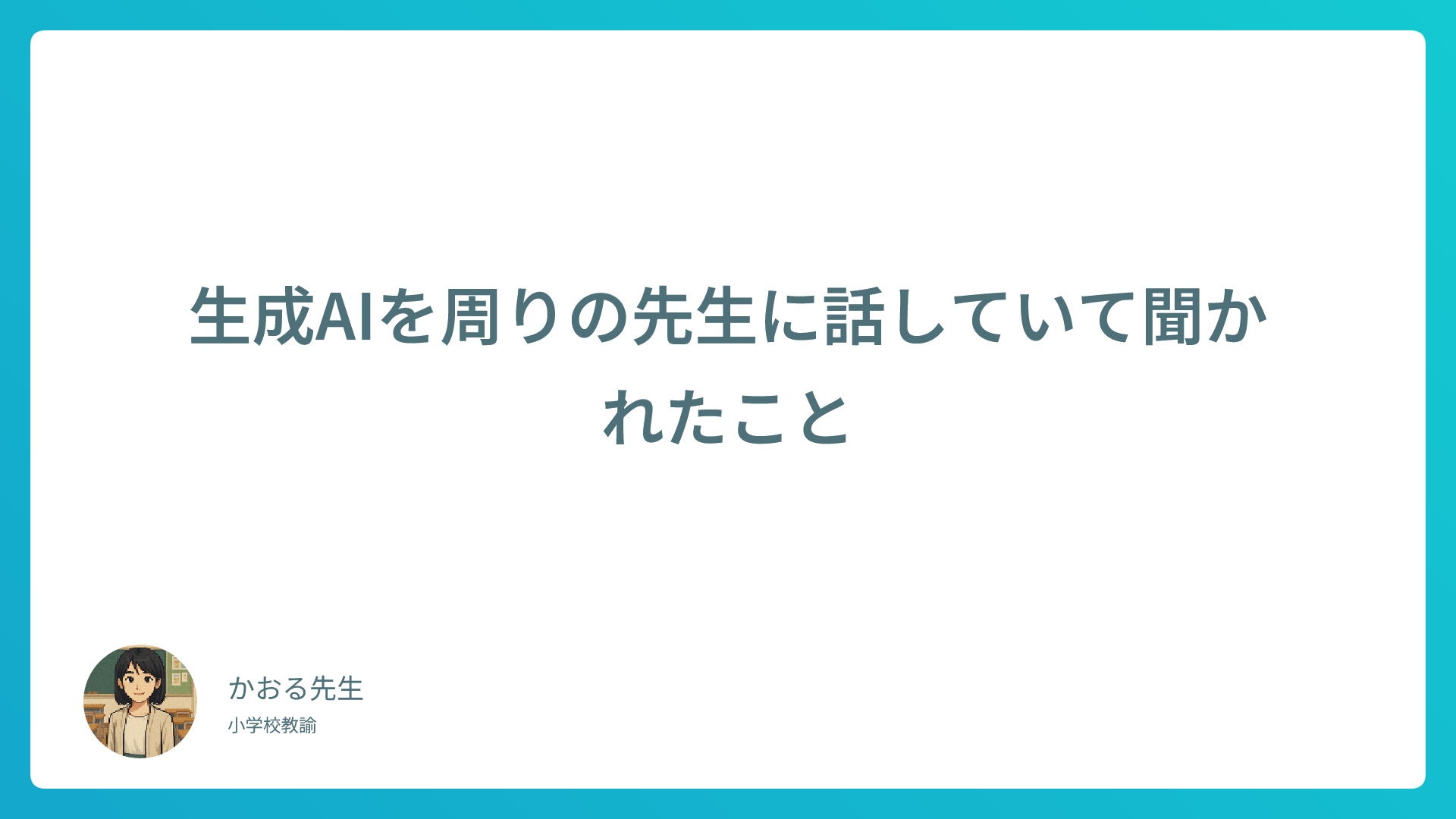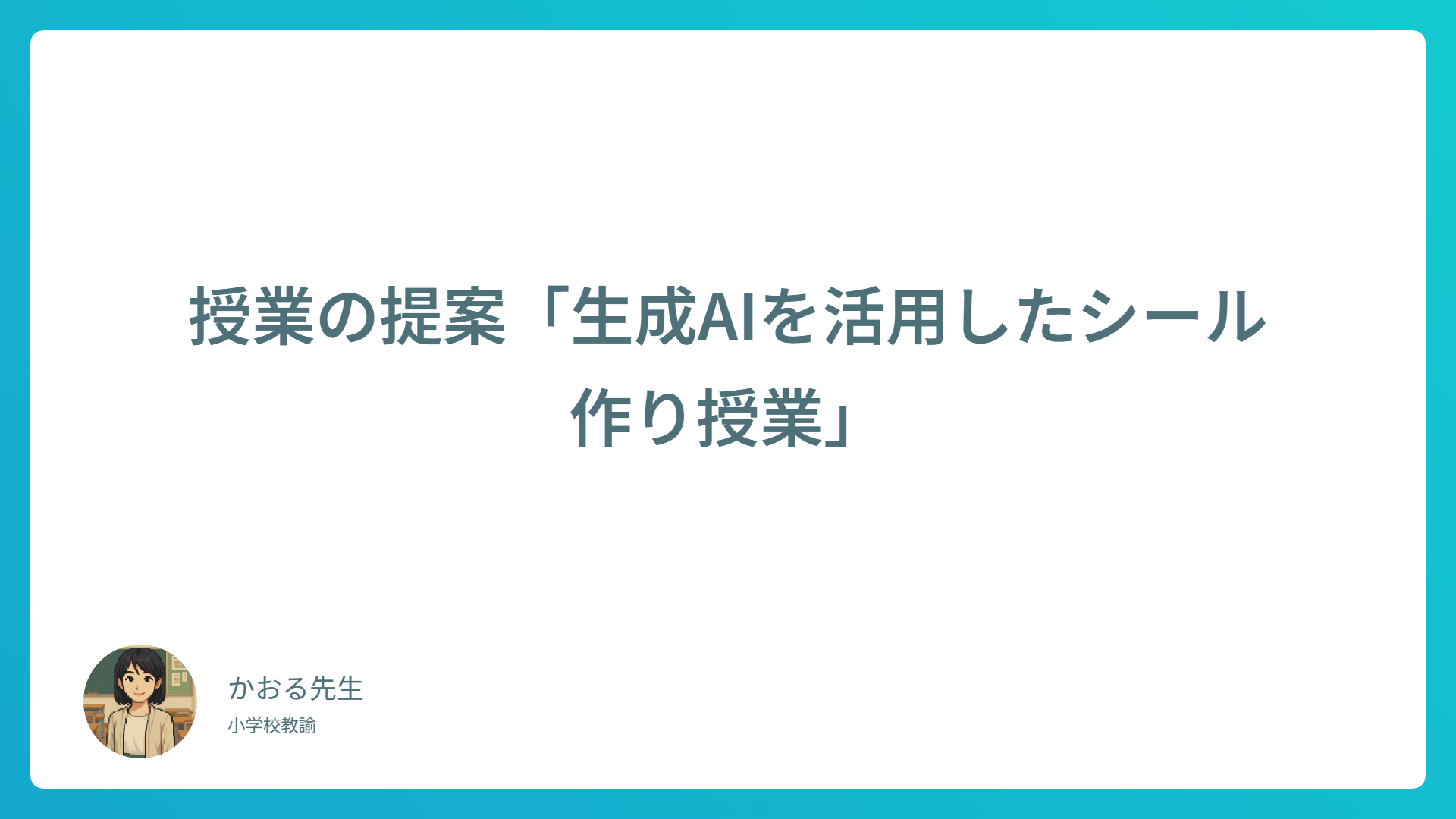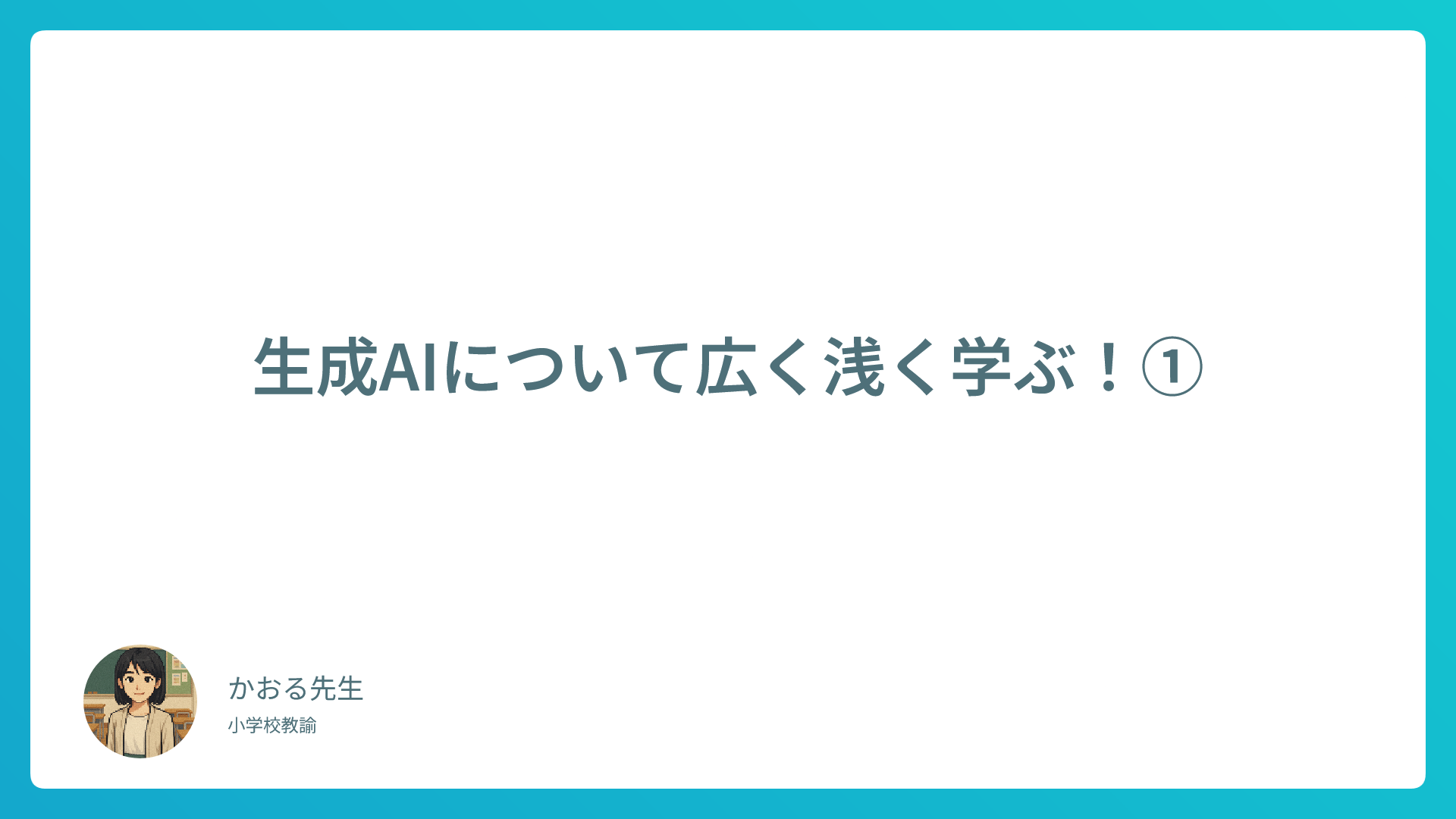kaorusensei06
1. AIと著作権を巡る現状と本素案の目的
- 本素案は、生成AIと著作権の関係における解釈を示すものであり、司法判断に代わるものではなく、文化審議会法制度小委員会の見解を示す資料。
- 目的:著作権者・AI開発者・利用者間での認識の共有と懸念の整理。
- 一部の団体からは、議論の不十分さや、特定ステークホルダーへの偏り、内容の複雑性について懸念の声も。
- JDLA、LLM-jpなどは、過度に権利者寄りの解釈がAI開発を萎縮させると警告。
2. 主要な論点と争点
2.1 「享受目的」と「非享受目的」の解釈
- 著作権法第30条の4は「享受を目的としない利用」(=非享受目的)に限定して権利制限を認める。
- AI開発側(JDLA等)は、**統計的処理による学習は「非享受」**と主張。
- 一方で、生成結果が元著作物と類似する場合の解釈基準が不明確との指摘あり(学術著作権協会、アニメフィルム文化連盟など)。
2.2 作風・画風と著作権保護の境界
- 作風は「アイデア」と「表現」の中間にあり、法的保護の範囲が曖昧。
- 権利者側:作風は人格と結びついた重要な財産であり、保護対象とすべき(JASRAC、アニメフィルム文化連盟など)。
- 開発者側:著作権法の原則(アイデア非保護)を逸脱すべきでないと反対。
2.3 海賊版からの学習と法的責任
- 権利者側:海賊版データからの学習は違法とし、明確な禁止・規制を求める。
- 開発者側:海賊版と正規版の識別は困難であり、現実的運用を考慮すべき(JDLA、Algomatic等)。
- 「通常有すべき認識」の法的判断基準が曖昧で、過剰な萎縮を招く可能性。
2.4 依拠性・技術的措置・責任の所在
- AI生成物が著作物に似ている場合の**「依拠性(依存の証明)」の判断が困難**。
- 素案:学習データに含まれていれば推認されうる。
- 利用者に過度な立証責任を負わせることへの懸念(印刷産業連合会、AIガバナンス協会等)。
- 技術的措置(類似生成の防止策)による責任軽減案も提示されているが、実装のコストや限界への懸念も強い。
2.5 データベース著作物とrobots.txtの法的意味
- 新聞協会などは、情報解析用に整備されたデータベースは保護すべきと主張。
- 開発者側は、robots.txtに過度な法的効果を持たせることに反対。
- 議論の中心は、「サイトのアクセス制限設定」が明示的な意思表示として権利制限を排除するかどうか。
3. その他の重要論点
3.1 補償金制度の導入
- AI開発側(AIガバナンス協会、JDLA等):補償金制度導入には理論的根拠が乏しく、開発意欲を削ぐと反対。
- 権利者側(アニメフィルム文化連盟、日本新聞協会等):「タダ乗り」状態を放置せず、著作権者への対価還元を求める。
3.2 ディープフェイクと肖像・声の保護
- アーティスト・俳優団体などからは、AIによる声・容貌の模倣による被害に対する早急な法整備の要望。
- 「声や作風は商品である」として、パブリシティ権や人格権的保護の必要性を強調。
3.3 AI生成物の著作物性
- 素案:プロンプトの工夫や試行錯誤など、創作的寄与があれば著作物性が認められる可能性。
- 一部団体(AI未来会、俳優連合など)は、「AI生成物には人間の創造性が介在していないため、著作権を与えるべきではない」と主張。
3.4 透明性と情報開示の義務
- 多くの団体(IFPI、日本レコード協会等)が、学習データの記録・開示義務の法制化を求める。
- 国際規制(EU AI法案)に対応し、透明性確保の制度整備が急務とされる。
4. 今後の課題と提言
- 明確で予見可能性の高いガイドラインの整備
- EU規則等、国際動向との調和
- 継続的かつ多角的な議論の推進
- イノベーションと権利保護の両立(著作権法改正の視野も)
- ディープフェイクなど非著作権領域への法的対応
- 透明性・説明責任の確保
結論
本素案は、日本におけるAIと著作権の制度設計に向けた重要な出発点です。
今後は、利害関係者全体が納得可能なバランスある制度設計と、国際競争力を損なわない環境整備が求められます。
ABOUT ME
大学・大学院では教育や技術について学び、小学校教諭免許に加えて、中学校(技術)および高等学校(情報・工業)の専修免許も取得しました。
「知ることの入り口」に立つ児童たちに、わかりやすく伝えることに大きなやりがいを感じ、現在は小学校の教員として日々子どもたちと向き合っています。またこの場では、日々の教育現場で役立っている業務効率化や時短の工夫、ちょっとした小技に加えて、趣味でもあるガジェットについての話題も交えながら、さまざまな情報をまとめていきたいと考えています。