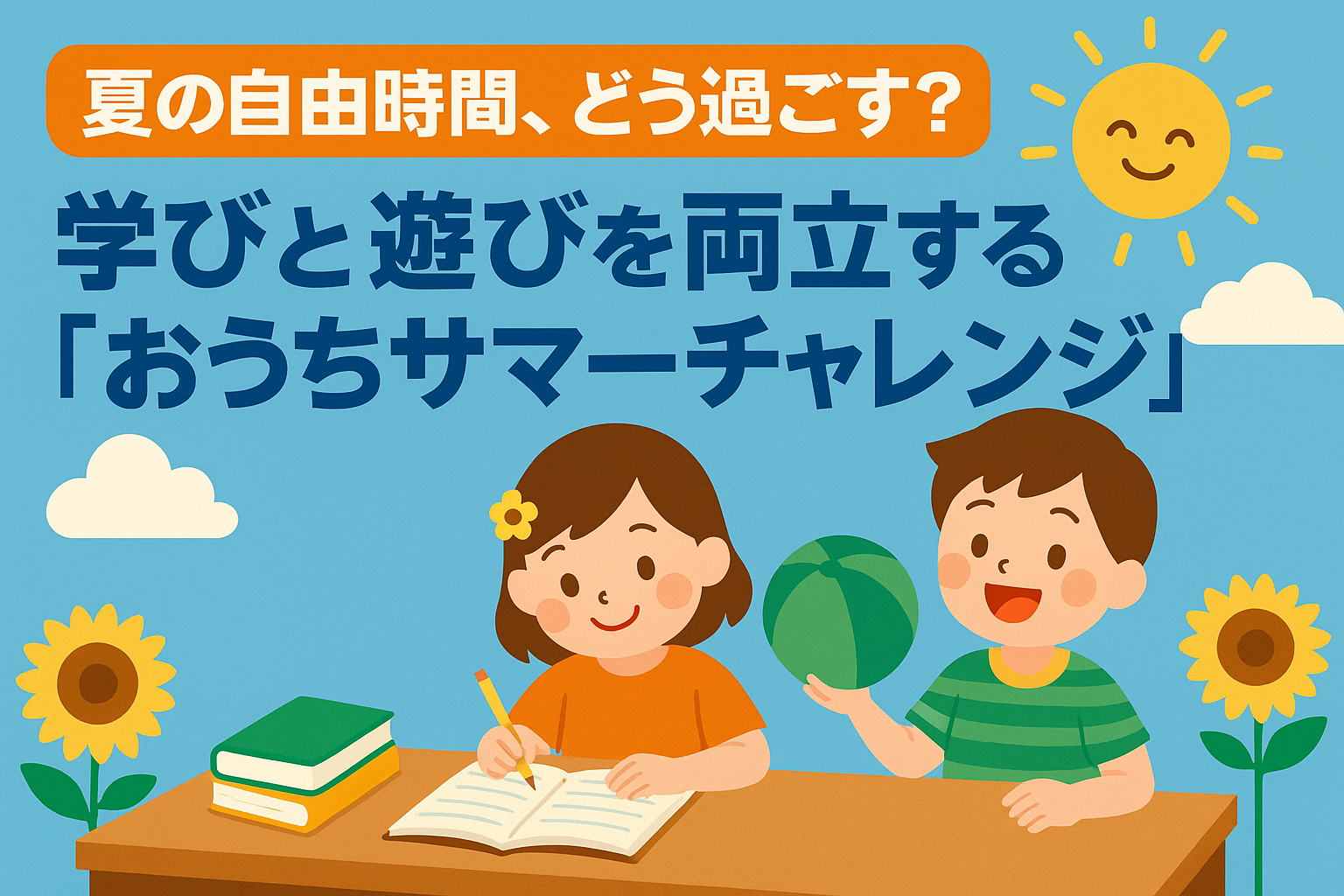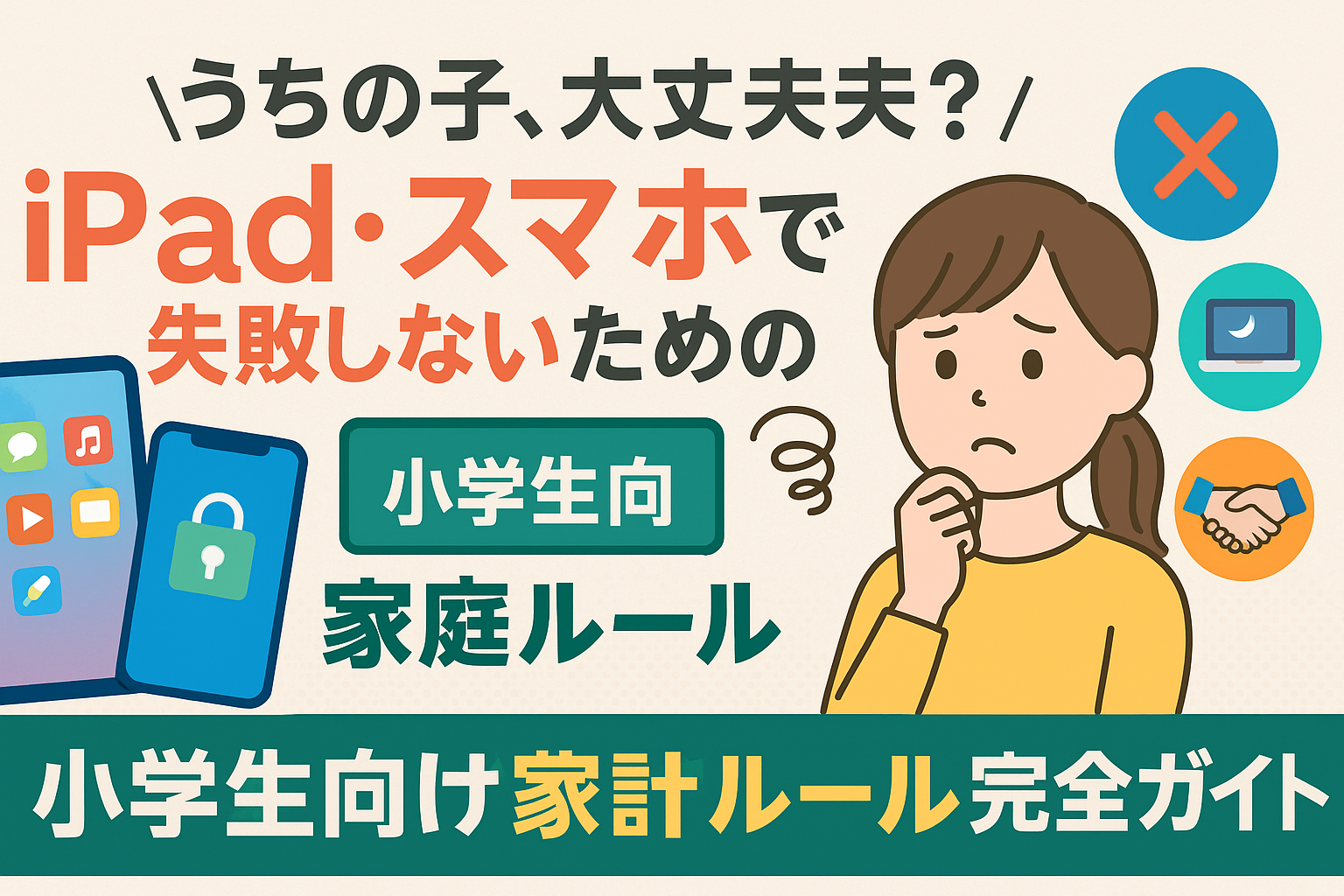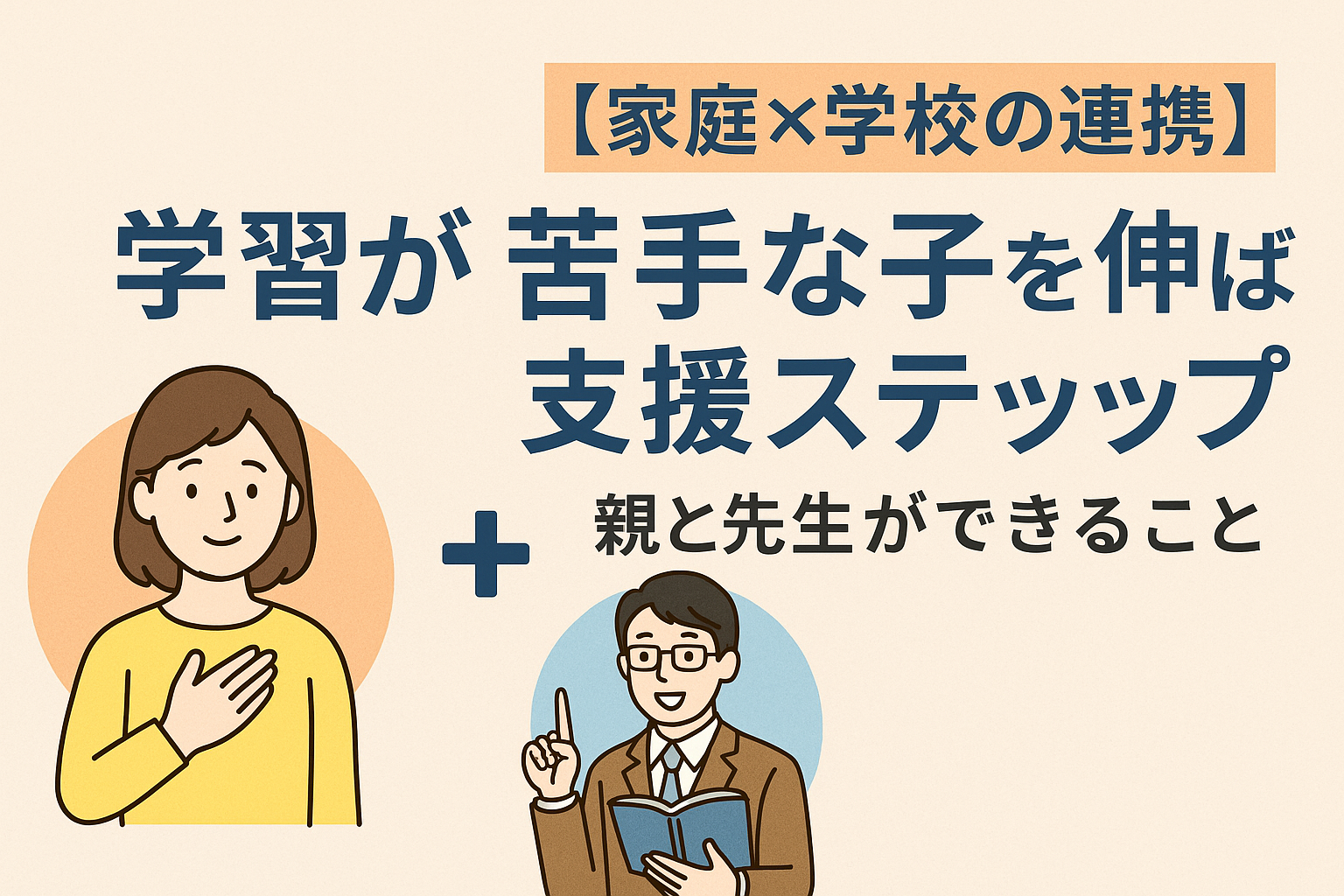【登校拒否・不登校】「学校に行きたくない」子どもの心のサインと親ができること
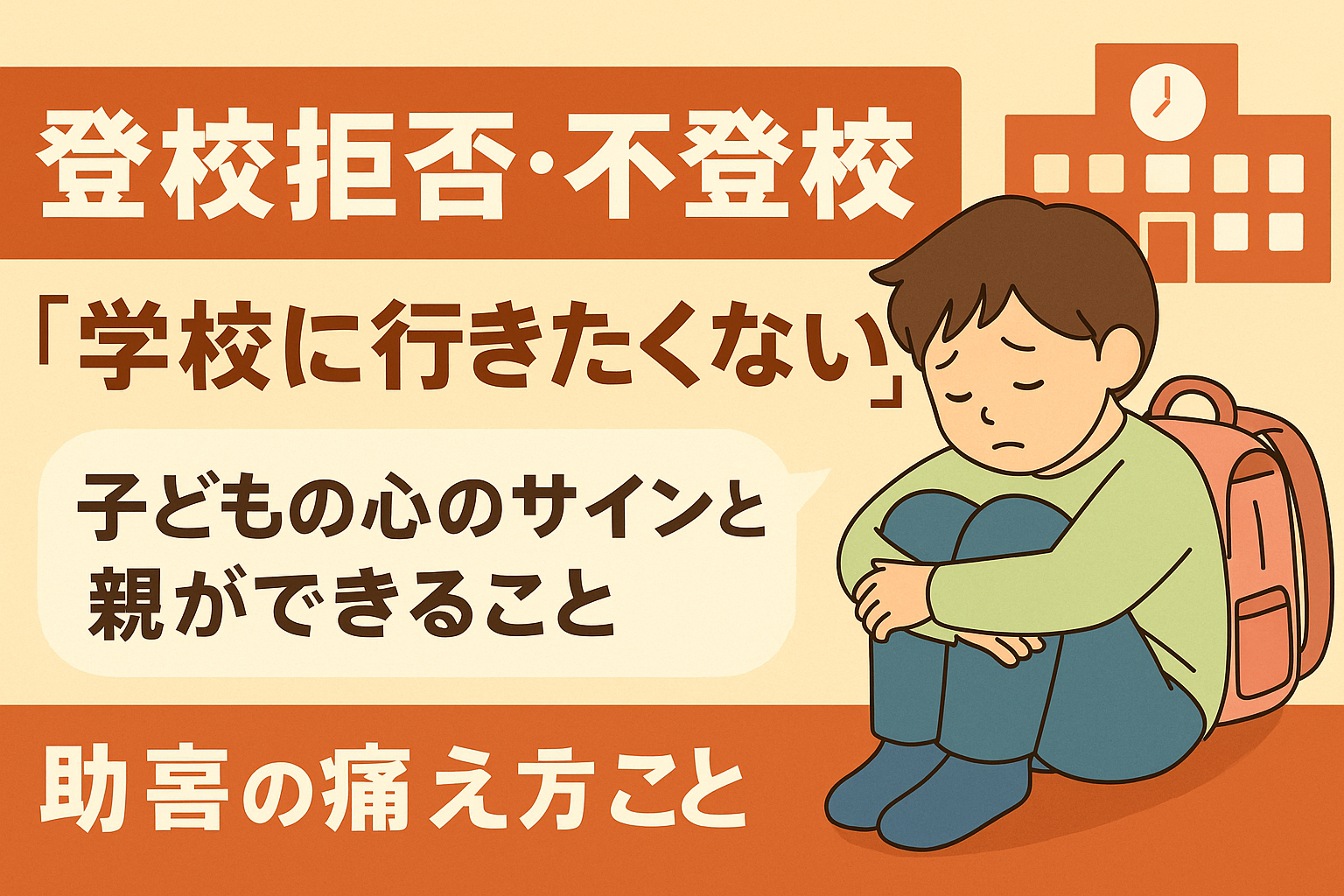
ある朝、子どもの口から「学校に行きたくない」という言葉が出た時、保護者の方は大きな不安に襲われることでしょう。何度も「どうしたの?」と聞いても答えてくれなかったり、体調不良を訴えたり…。
「甘えているだけなのかな?」 「どうにかして学校に行かせなきゃ…」
そう思ってしまうかもしれません。しかし、「学校に行きたくない」という言葉は、子どもが発する心からのSOSです。不登校は、子どもたちの心や体が限界を迎えているサインであり、決して「甘え」ではありません。
この記事では、小学校の現場で増えつつある登校拒否・不登校の背景にある子どもの心のサインを具体的に解説し、保護者の皆さんができる最初の対応、そして学校や専門機関との連携の重要性について、小学校教員の視点からお伝えします。
「学校に行きたくない」は子どものSOS!その背景にある多様な要因
子どもが学校に行きたがらない背景には、単一の原因ではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。
- 友達関係の悩み: 友達とのケンカ、仲間外れ、いじめの経験、人間関係のトラブル。
- 学業のつまずき: 授業についていけない、宿題が進まない、テストの点が取れないといった学習面での困難。
- 先生との関係: 先生との相性、叱られた経験、コミュニケーションがうまくいかないと感じている。
- 生活リズムの乱れ: 夜型の生活習慣、睡眠不足による体調不良。
- 発達特性: ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などの発達特性が、学校の集団生活での困り感につながっている。
- いじめ: 物理的・心理的ないじめ、ネットいじめなど。
- 家庭環境の変化: 親の病気や転勤、引っ越し、きょうだい関係の変化、家庭内でのストレスなど。
- 漠然とした不安: 何が原因か特定できないが、学校に行くことへの不安やストレスを感じている場合もあります。
これらの要因は、子ども自身が言葉で説明できないことも多く、「なんとなく行きたくない」としか言えない場合も珍しくありません。
保護者が気づく「心のサイン」〜子どものSOSを見逃さないために〜
子どもが「学校に行きたくない」と口にする前に、あるいは言葉にできなくても、体や行動でSOSを発していることがあります。普段と違う様子に気づくことが、早期対応の第一歩です。
- 身体症状を訴える
- 朝になるとお腹が痛い、頭が痛い、吐き気がするといった身体の不調を訴える。
- 発熱はないのにだるそうにしている。
- 病院に行っても「異常なし」と言われることが多い。
- 言動の変化
- イライラしやすくなる、怒りっぽくなる。
- 無気力で、何もやる気を見せない。
- 口数が減る、あるいは逆に過剰におしゃべりになったり甘えたりする。
- 特定の話題(学校、友達、先生など)を避けるようになる。
- ゲームや動画視聴に極端に没頭するようになる。
- 睡眠・食欲の変化
- 夜なかなか寝付けない、寝ても疲れが取れない。
- 夜中に目が覚める、うなされる。
- 食欲がない、あるいは逆に過食になる。
- 朝の準備に時間がかかる・学校の準備ができない
- 着替えや身支度に時間がかかる。
- 忘れ物が多くなる、自分で準備ができない。
- 登校時間が近づくと、急に体調が悪くなる。
- 特定の場所や話題を避ける
- 登校中、急に足が止まる、回り道をする。
- 学校に関する話題を避ける、先生や友達の悪口を言うようになる。
- 特定の場所に近寄ろうとしない。
親ができる最初の対応〜「受け止める」ことから始めよう〜
子どもの「学校に行きたくない」という言葉やサインに直面した時、親としてどのように対応すれば良いのでしょうか。
1. 「行きたくない」という子どもの気持ちを「受け止める」
- 感情を否定しない傾聴の姿勢: 「どうして?」「甘えているんじゃないの?」と理由を問いただしたり、否定したりせず、まずは子どもの気持ちを共感的に聞くことに徹しましょう。「そうだったんだね」「つらかったね」「嫌な気持ちなんだね」と、子どもの感情を言葉にして返すことが大切です。
- じっくりと話を聞く: 親が焦って強い口調で聞くと、子どもは心を閉ざしてしまいます。子どもが話したがらない場合は無理強いせず、話せるタイミングを待ちましょう。
2. 「休ませる」判断も視野に入れる
- 無理に登校させることが、かえって子どものストレスを増やし、事態を悪化させる場合もあります。子どもの心身が限界を迎えているサインだと感じたら、思い切って休ませることも大切な選択肢です。
- 休ませることで、子どもは「自分の気持ちを受け止めてもらえた」「休む権利がある」と感じ、安心感を得られることがあります。
3. 家庭を「安心できる居場所」に
- 学校に行けない間も、家庭が子どもにとって「心の安全基地」であることを常に意識しましょう。
- 家では、リラックスして過ごせる雰囲気を作り、子どもが安心して過ごせる環境を整えてあげましょう。
- 「学校に行かなくても、あなたは大切な家族だよ」というメッセージを、言葉や態度で伝え続けることが大切です。
4. 生活リズムの維持に努める
- 学校に行けないからといって、昼夜逆転の生活にならないよう、できる範囲で規則正しい生活リズムを維持する工夫をしましょう。
- 例えば、朝は決まった時間に起こす、日中は学習以外の活動(読書、お手伝い、散歩など)を促す、夜は就寝時間を守るなどです。
学校との連携の重要性〜一人で抱え込まないために〜
子どもの不登校問題は、家庭だけで抱え込まず、学校や専門機関と連携することが非常に重要です。
1. 早めに学校に相談することのメリット
- 情報共有の重要性: 家庭での子どもの様子を学校に伝えることで、先生は学校での子どもの行動(授業中の様子、友達関係、言動の変化など)と結びつけて理解しやすくなります。
- 早期対応の可能性: 問題が小さいうちに連絡することで、先生も早期に介入し、対応策を検討することができます。
- 学校内の支援体制: 担任の先生だけでなく、養護教諭(子どもの心身の健康サポート)、スクールカウンセラー(SC)(心理的な相談)、スクールソーシャルワーカー(SSW)(家庭と学校、地域との連携支援)など、学校内の専門家と連携してサポートが受けられます。
2. 学校への相談方法
- 具体的な状況を伝える: 「最近、朝になるとお腹が痛いと言って学校に行きたがりません」「以前は〇〇だったのですが、最近は〇〇な様子です」など、具体的な症状や言動の変化を伝えましょう。
- 連絡のタイミング: 連絡帳、電話、面談の申し出など、状況や緊急度に応じて適切な方法で連絡を取りましょう。特に緊急性が高い場合は、直接電話で伝えるのが確実です。
3. 外部専門機関との連携も視野に
学校内での対応が難しい場合や、より専門的な支援が必要な場合は、外部の専門機関との連携も検討しましょう。
- 児童相談所: 子どもに関するあらゆる相談に応じ、支援計画を立ててくれます。
- 医療機関: 心身の不調や、発達特性が背景にある可能性が疑われる場合は、小児科、心療内科、精神科などを受診し、専門的な診断や治療を受けることができます。
- フリースクール・適応指導教室: 学校以外の学びの場として、子どもの状況に応じた支援を提供しています。
まとめ:「安心」の土台を築き、子どもと共に歩む
子どもの「学校に行きたくない」という言葉は、親にとって胸が張り裂けそうな思いを伴います。しかし、これは子どもが頑張り続けている証拠であり、親に助けを求めているSOSです。
- 子どもの心のサインを見逃さない。
- 「行きたくない」という気持ちを否定せず、受け止める。
- 家庭を「安心できる居場所」にする。
- 早めに学校に相談し、連携する。
- 必要であれば、外部の専門機関の支援も頼る。
これらの行動が、子どもたちの「安心」の土台を築き、再び自分らしく輝けるようになるための大きな一歩となります。保護者の皆様、決して一人で抱え込まず、学校や専門家を頼りながら、子どもたちと共にこの道を歩んでいきましょう。

もし何かございましたら、学校を頼ってください。

ぜひ我々も一緒に考えさせてください。