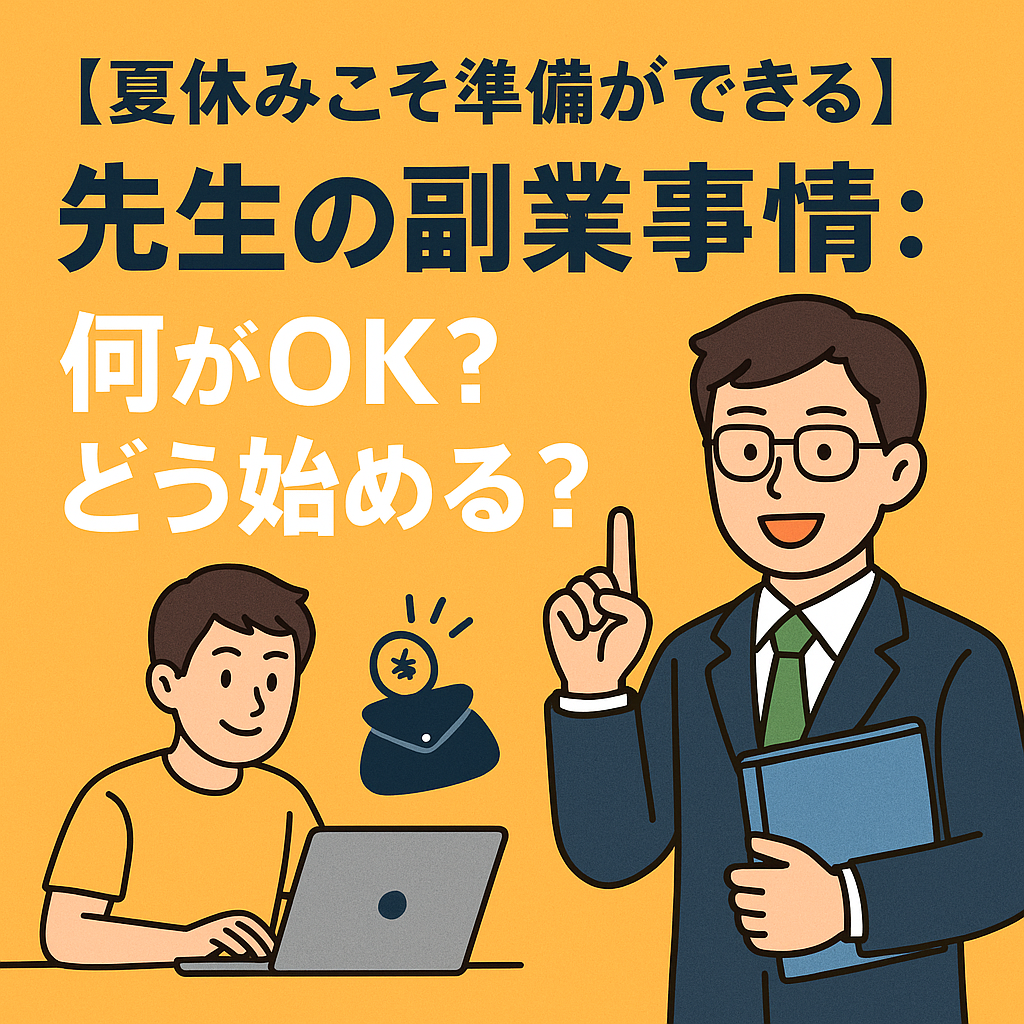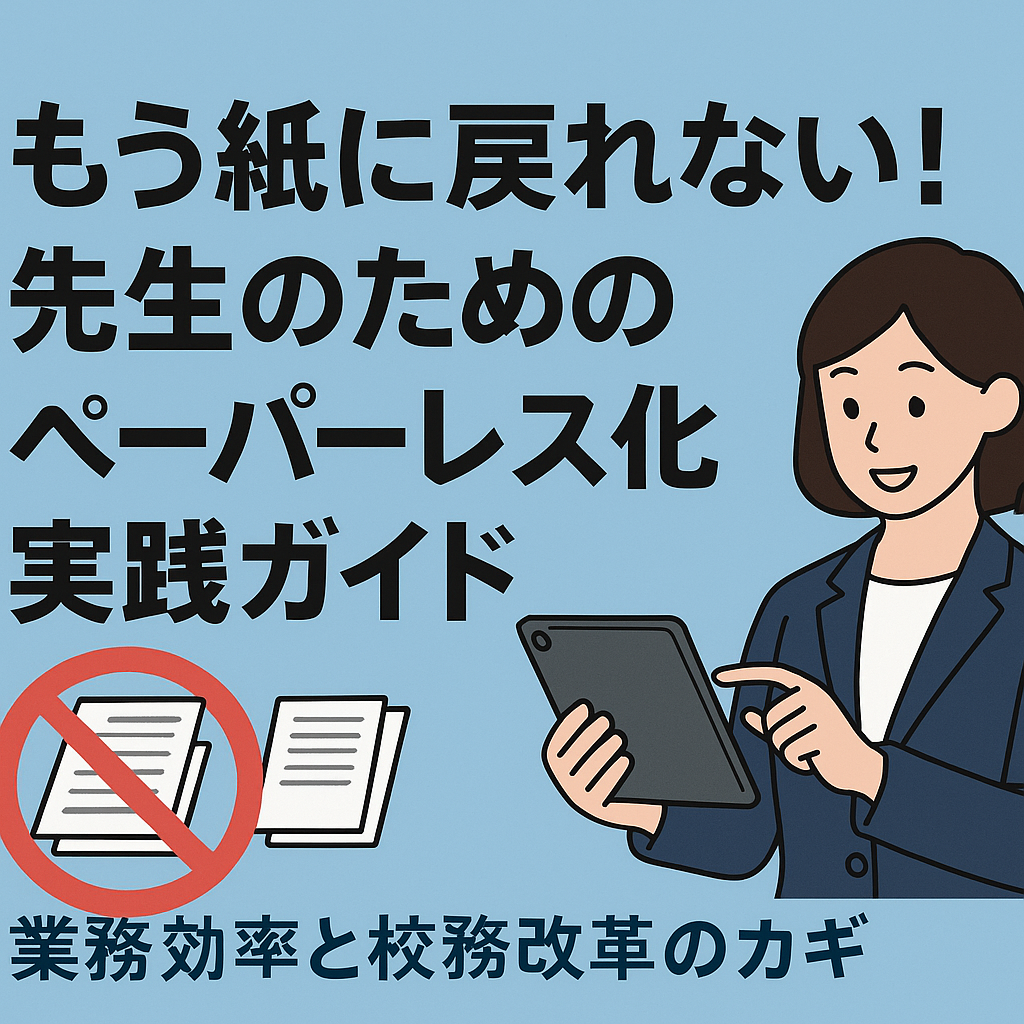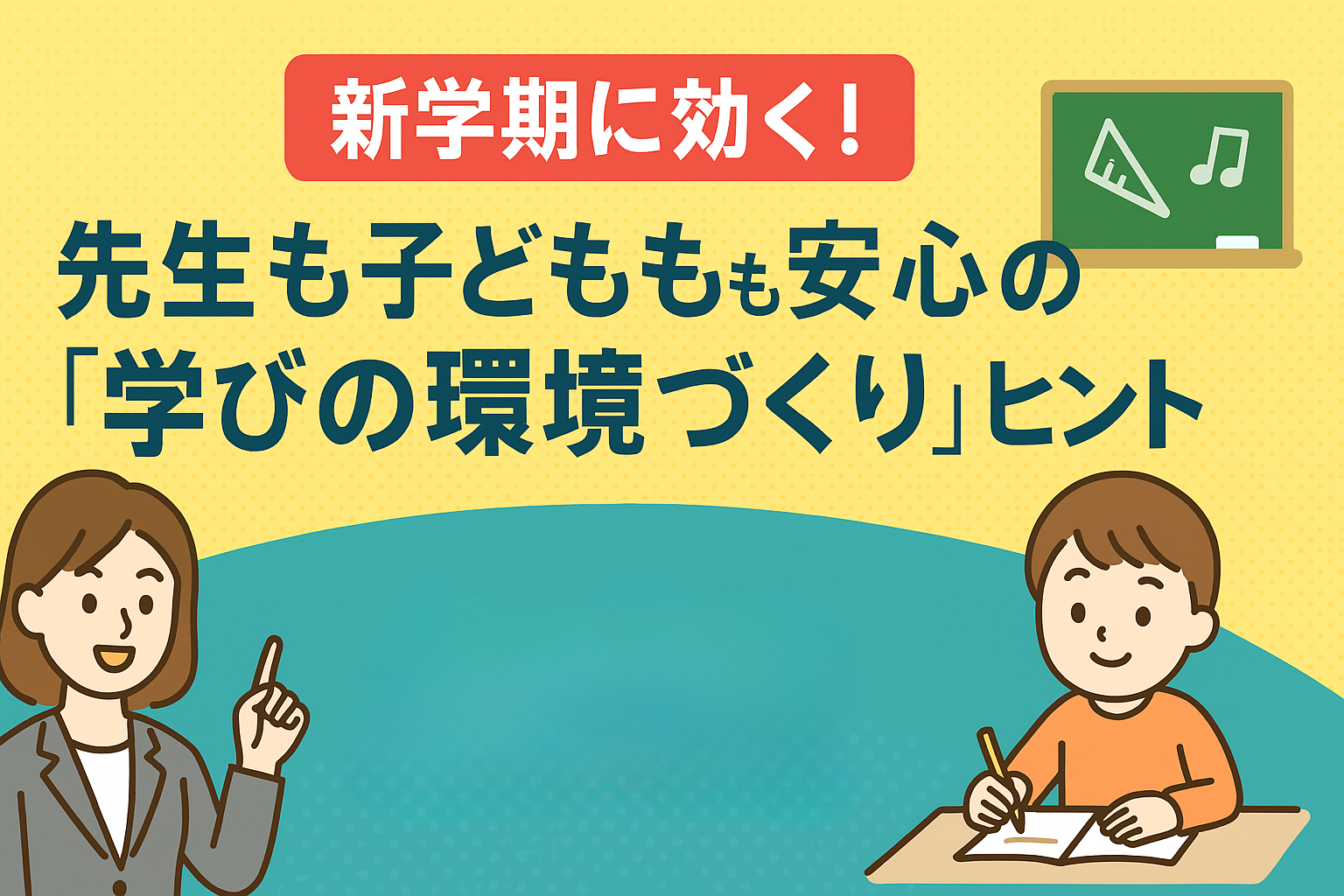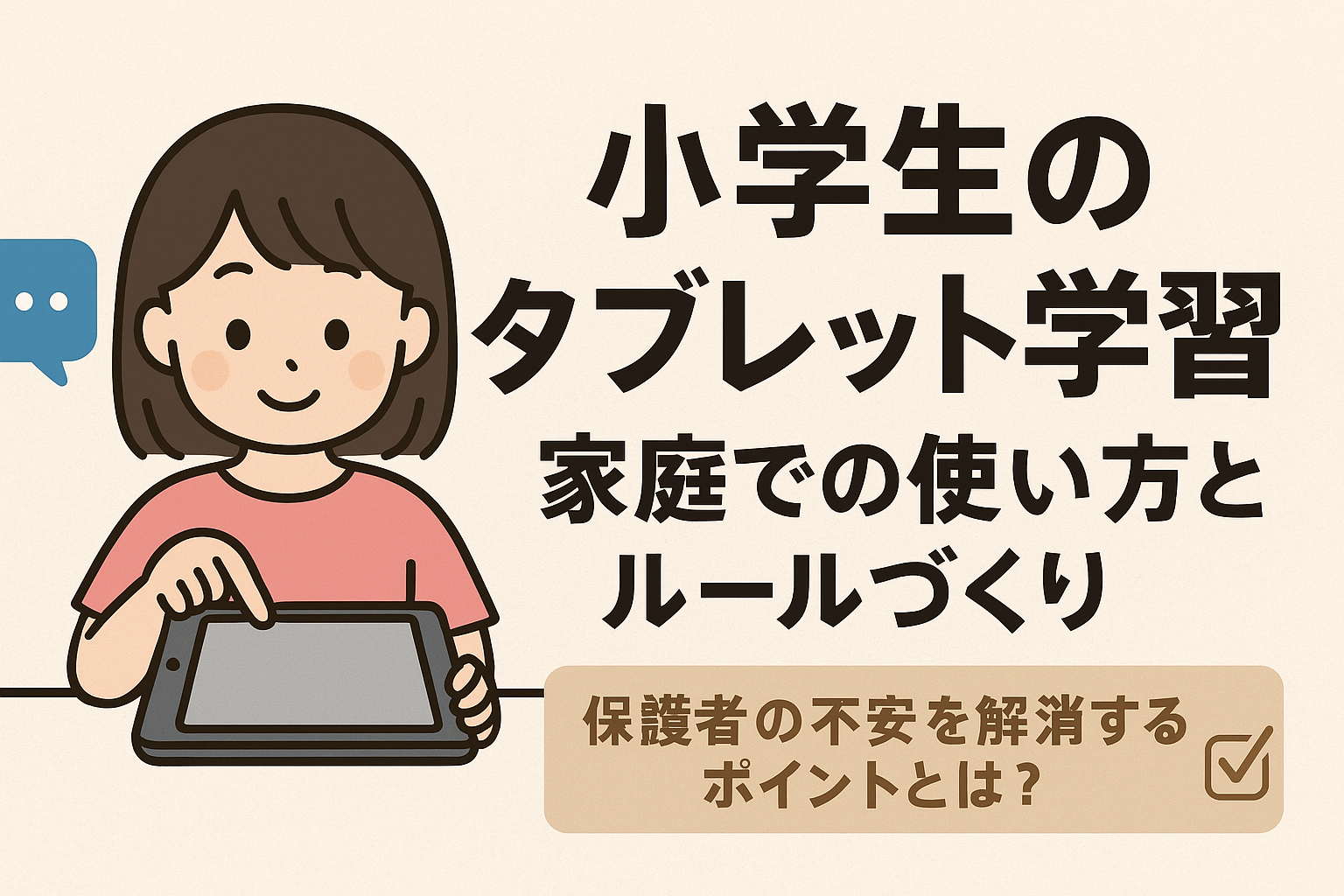「学校に行きたくない」子どもの心のサイン:担任として、私たちにできること

「朝、教室に来ていない子がいて、連絡帳も電話もつながらない」 「休み時間になると一人でいることが増えた」「授業中にうつむいている」 「最近、特定の友達との会話を避けているようだ」
子どもたちのちょっとした変化に、私たちは日々、神経を研ぎ澄ませていますよね。特に「学校に行きたくない」というサインは、担任として最も心が痛むものではないでしょうか。
不登校は、子どもが発する心からのSOSであり、その背景にはさまざまな要因が複雑に絡み合っています。担任として、私たちはどのようにそのサインを受け止め、子どもたちに寄り添い、そして保護者の方々と連携していくべきでしょうか。
この記事では、小学校教員の視点から、不登校のサインに気づいた時に私たちが学校現場でどのように考え、行動し、保護者と連携していくかについて、具体的な対応ステップを解説します。
「行きたくない」は子どものSOS!担任として見つけるサインと背景
子どもたちが発する「学校に行きたくない」というサインは、決して「甘え」ではありません。それは、心や体が学校生活のストレスや困難に耐えきれなくなっている、限界のサインであることがほとんどです。
私たちは、日々の学校生活の中で、子どもの様々なサインを見つけることができます。
- 体調の変化:
- 朝の会で顔色が優れない、頻繁に腹痛や頭痛を訴える(特に月曜日など)
- 授業中にうつ伏せになっている、保健室に行くことが増える
- 以前より食欲がない、給食をなかなか食べられない
- 言動・態度の変化:
- 普段より口数が減る、あるいは不自然に多弁になる、興奮しやすくなる
- 先生や友達の誘いを断ることが増える、反抗的な態度が見られる
- 授業中、ぼーっとしている、集中力が続かない
- 忘れ物や提出物が極端に増える
- 特定の場所(教室の隅、保健室など)にいることが増える
- 登校時、表情が硬い、親と離れるのを嫌がる
- 人間関係の変化:
- 特定の友達を避けるようになる、休み時間を一人で過ごすことが増える
- 友達とのトラブルが頻繁になる、逆にトラブルから身を引くようになる
- 以前は仲が良かった友達との関係がぎくしゃくしている
これらのサインの背景には、実に多様な要因が考えられます。
- 友達関係の悩み: いじめ、仲間はずれ、特定の友達との関係性の難しさ
- 学業のつまずき: 授業内容の理解が難しい、宿題が終わらない、テストへのプレッシャー
- 先生との関係: 指導への反発、コミュニケーションのすれ違い、不安感
- 生活リズムの乱れ: 家庭での夜更かし、睡眠不足
- 発達特性: ADHD、ASDなど、発達上の特性による集団生活や学習での困難
- 家庭環境の変化: 親の転勤、引っ越し、家族関係の変化、家庭内のストレス
- 漠然とした不安: 具体的な原因が特定できない、言語化できないストレス
私たちは、これらのサインを見逃さず、背景にある子どもの心の叫びを理解しようと努める必要があります。
担任としてできること:初期対応と見守りのステップ
子どもが「学校に行きたくない」というサインを出した時、担任としてどのような対応をとるべきでしょうか。
ステップ1:小さなサインに気づき、まずは「担任の目」で観察する
- 日々の観察の徹底: 授業中、休み時間、給食時、清掃時間など、日常のあらゆる場面で子どもの表情、言動、行動パターン、友達との関わり方を注意深く観察し、記録を残します。
- 行動の背景を推測する: 「なぜこの行動をとるのだろう?」「どんな気持ちが隠されているのだろう?」と、表面的な行動だけでなく、その背景にある子どもの感情や状況を推測する視点を持ちましょう。
- 子どもへの声かけの工夫:
- いきなり「どうしたの?学校来ないの?」と問いただすのではなく、「最近、少し元気がないように見えるけど、何かあったかな?」のように、子どもの体調や気持ちに寄り添う言葉をかけましょう。
- 子どもが話したがらない場合は無理強いせず、「先生はいつでも話を聞く準備ができているよ」という安心感を伝え、見守る姿勢が大切です。
- 休み時間や放課後など、落ち着いて話せる機会を設けるのも有効です。
ステップ2:情報共有と校内連携を図る
担任一人で抱え込まず、学校全体で子どもを支える体制を構築しましょう。
- 学年内での情報共有: 学年の先生方と子どもの様子を共有し、複数担任で共通理解を図ります。「他の先生の授業ではどうか」「休み時間や給食時はどうか」など、多角的な視点から情報を集めます。
- 校内専門機関との連携:
- 養護教諭: 子どもの体調の変化や、保健室での過ごし方などの情報を共有し、連携して健康面からのサポートを検討します。
- スクールカウンセラー(SC): 子どもの心理的な背景を探るための専門的な見立てや、具体的な面談、支援の方向性について相談します。保護者面談への同席を依頼することもあります。
- スクールソーシャルワーカー(SSW): 家庭環境や地域との連携が必要な場合、SSWの専門性を活かして、より広い視点から支援を検討します。
- 管理職への報告: 子どもの様子が気になる、または欠席が続いている場合は、速やかに教頭先生や校長先生に報告し、学校としての対応方針を協議しましょう。
ステップ3:保護者との「早期連携」と「情報共有」
保護者の方からの情報は、学校での子どもの姿を理解し、支援を進める上で不可欠です。
- タイムリーな連絡: 子どもの欠席が続く場合や、学校での様子に大きな変化が見られる場合は、早めに保護者に連絡を取りましょう。
- 事実を冷静に伝える: 「最近、〇〇な様子が見られます」「〇月〇日以降、欠席が続いています」など、主観を交えず、客観的な事実を伝えます。
- 家庭での様子を尋ねる: 「ご家庭ではいかがでしょうか?」「気になることはありませんか?」と、家庭での子どもの様子を尋ね、情報共有を促します。
- 「一緒に考えたい」という姿勢を示す: 「私たちも〇〇さんが学校で安心して過ごせるよう、一緒に考えたいと思っています」というように、学校と家庭で協力していく姿勢を明確に示しましょう。
- 相談の場を設ける: 必要に応じて、個人面談の機会を設け、じっくりと話を聞き、今後の支援の方向性や、学校でできることを具体的に伝えましょう。
ステップ4:具体的な支援計画の策定と実行
情報が集まったら、子ども一人ひとりに合った支援計画を立て、実行します。
- 個別の指導計画・教育支援計画の検討: 子どもの特性やニーズに応じた学習・生活上の配慮を盛り込んだ計画を策定し、教職員間で共有します。
- 段階的な学校復帰の支援:
- まずは登校できる時間や曜日を限定する。
- 特定の教科や活動から参加を促す。
- 保健室登校や別室登校から始める。
- フリースクールや適応指導教室との連携も視野に入れる。
- 学びの保障: 学校に来られない期間も、できる範囲で学習内容に触れられるよう、教材の提供やオンラインでのフォローなども検討します。
- 「できた!」の経験を大切に: 小さな一歩でも、学校に来られたこと、友達と話せたこと、何か課題ができたことなど、ポジティブな経験を認め、具体的に褒めることで、子どもの自信を育みます。
まとめ:担任は「伴走者」。学校全体で子どもと家庭を支える
子どもたちの「学校に行きたくない」というSOSは、私たち担任にとって、本当に心を揺さぶられるものです。しかし、このサインにいち早く気づき、適切に対応することで、子どもたちは再び笑顔を取り戻し、学校生活へと歩み出すことができます。
- 日常の小さなサインを見逃さない観察力。
- 担任一人で抱え込まず、校内連携を図る。
- 保護者の方々と早期に情報共有し、連携する。
- 子ども一人ひとりに寄り添った支援計画を立てる。
私たちは、子どもたちの「伴走者」として、決して一人で走らせません。そして、保護者の皆様も一人で悩みを抱える必要はありません。学校全体で、子どもと家庭を支えるチームとして、共に手を取り合っていきましょう。

担任だからと一人で背負い込む必要はありません。
学校、家庭そして地域、すべてで連携し子どもたちにとっての最善、最良を目指しましょう。

我々は大人として、目の前にいる子どもたちの10年後を見据えその子にとってのベストをその子と一緒に模索していきましょう。