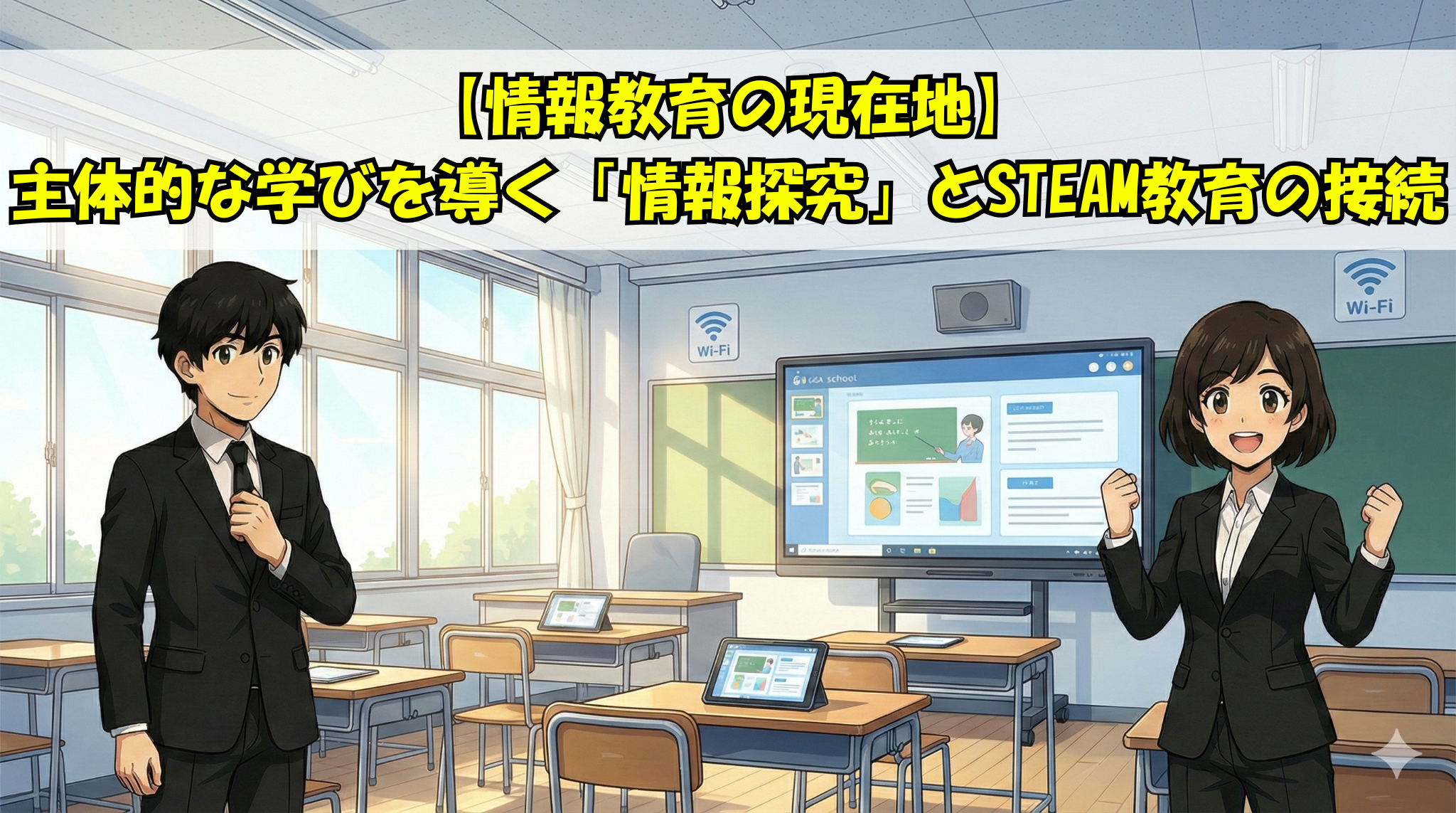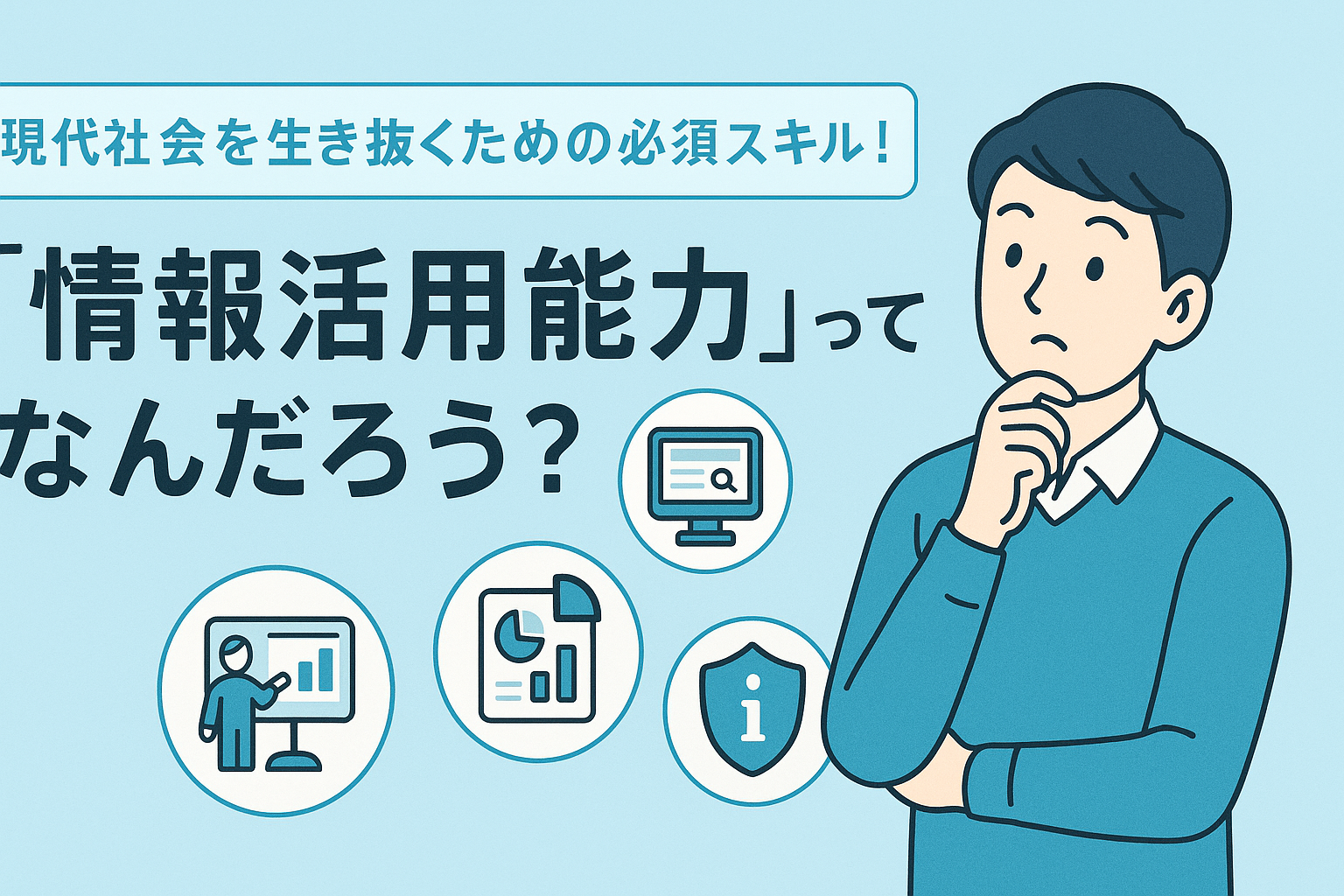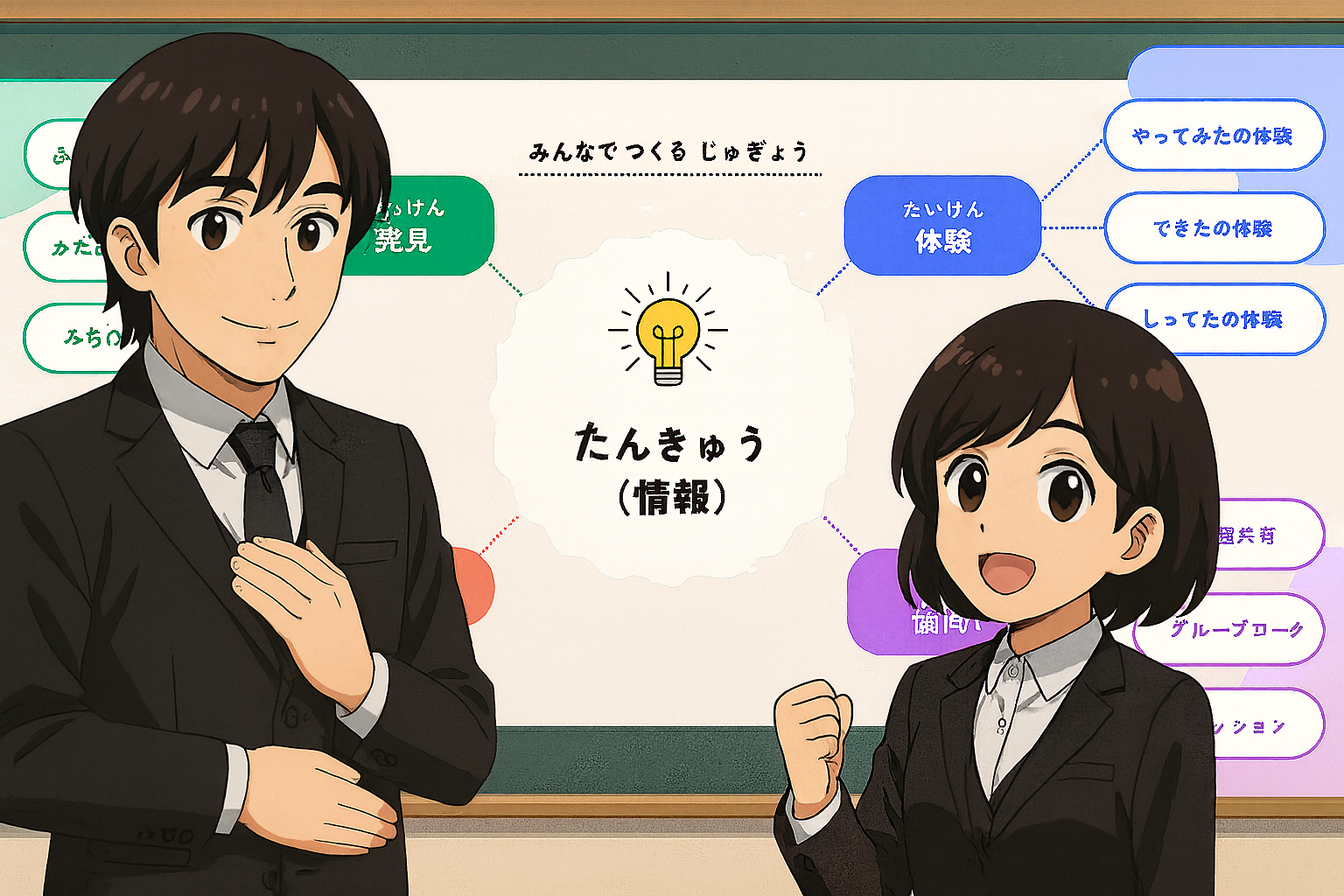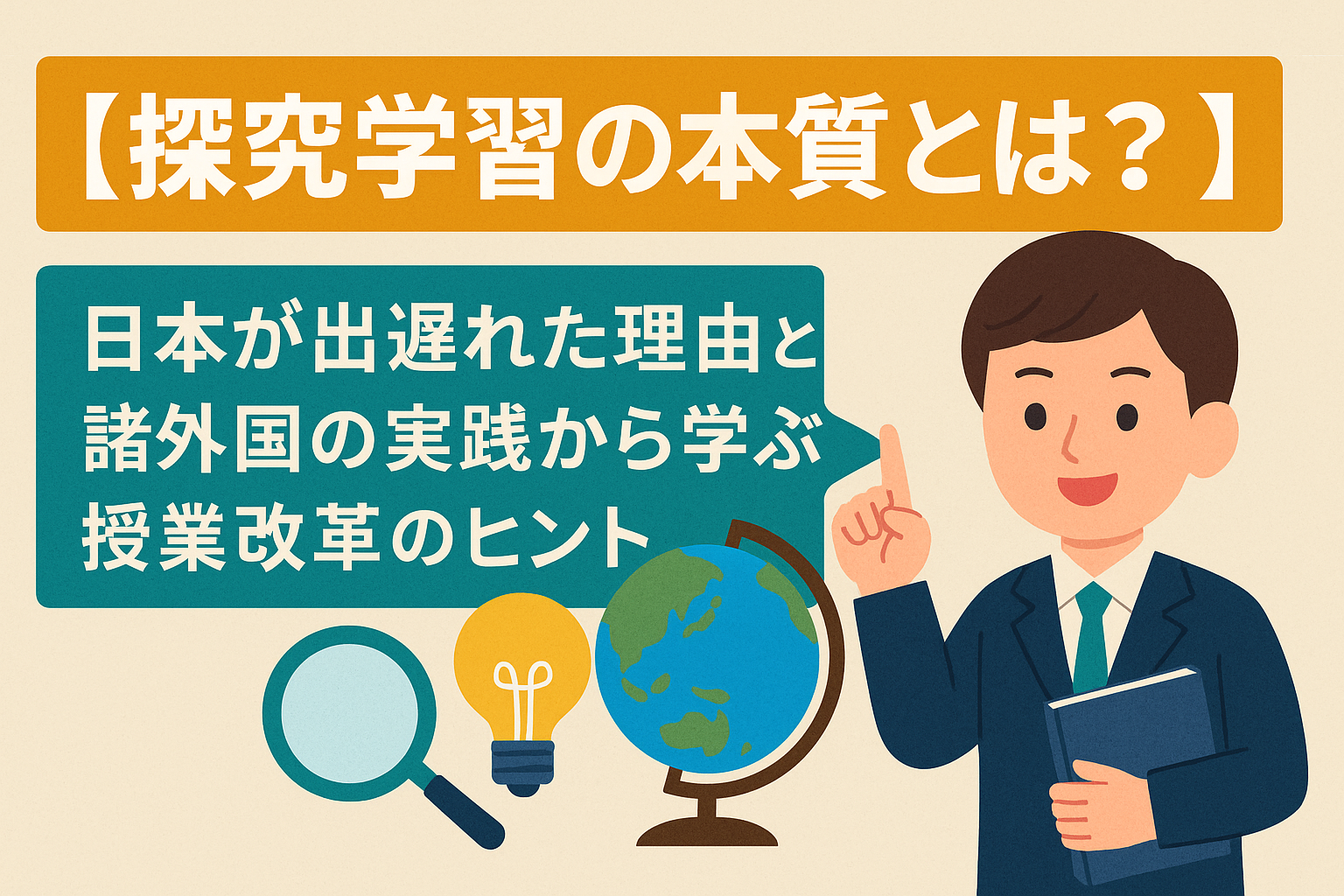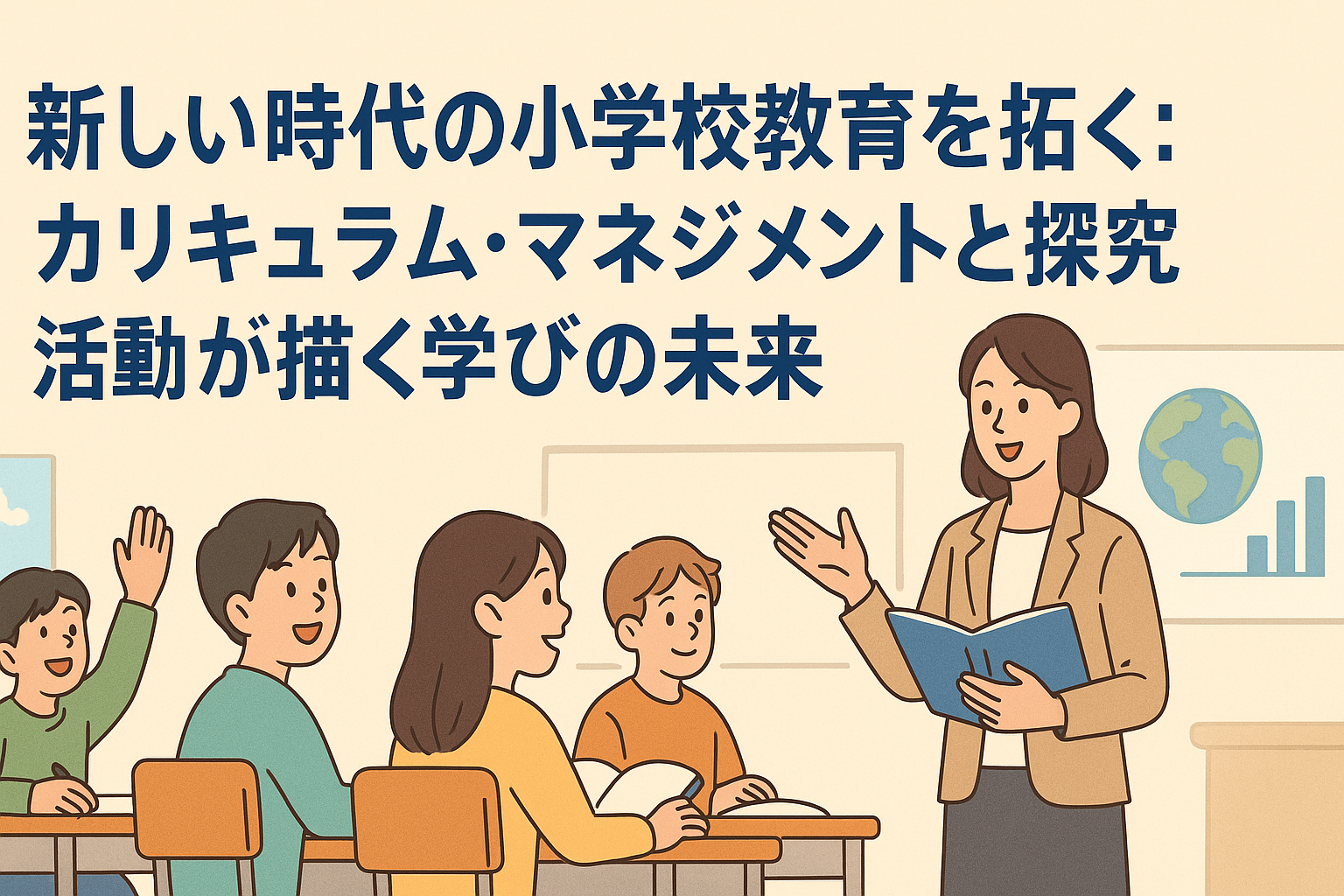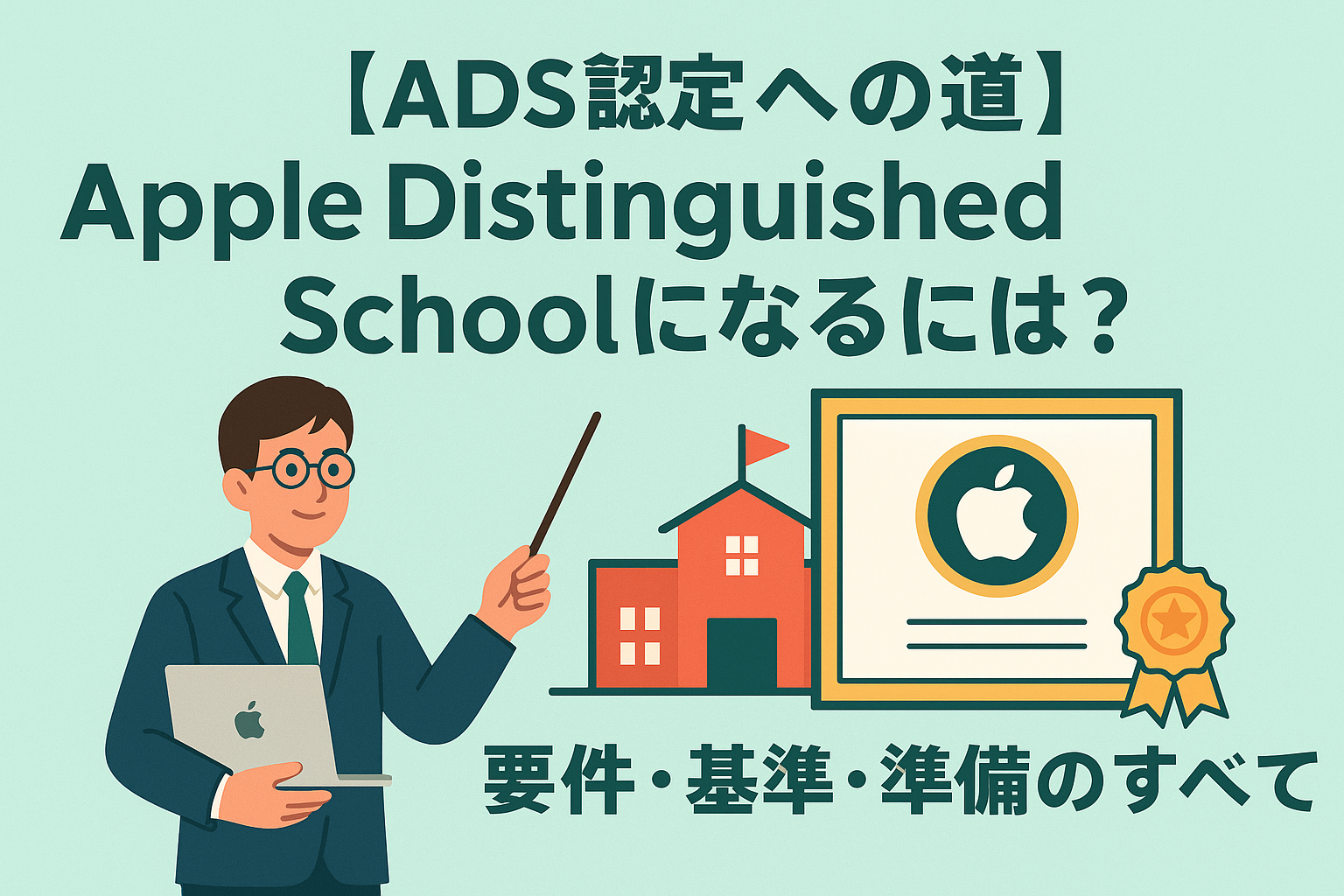【教育比較】諸外国の探究学習と日本の現状|未来の授業づくりへのヒント
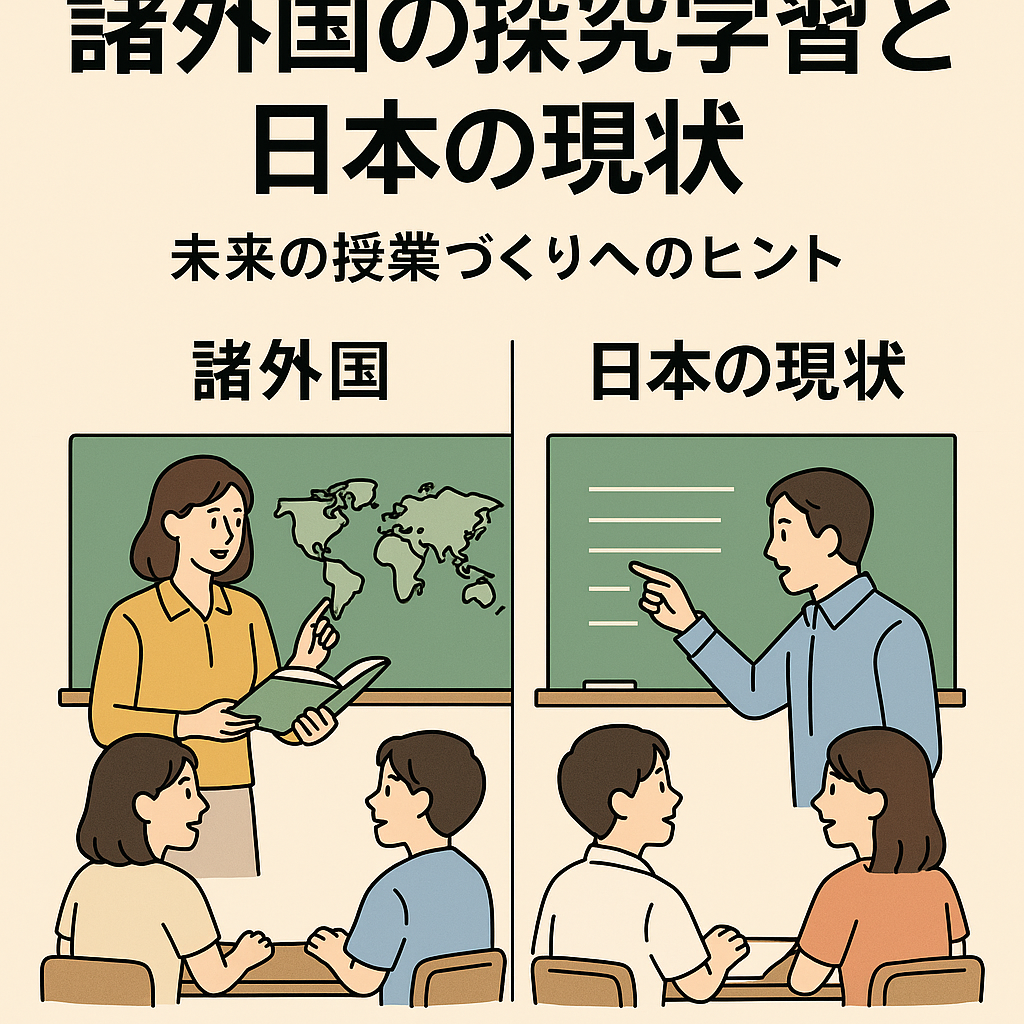
近年、文部科学省が推進する「探究学習」は、子どもたちが自ら問いを見つけ、答えを探していく、これからの時代に求められる学びの形として注目されています。しかし、日本における探究学習の導入は、OECD加盟国38か国中、下位10%に位置しており、他国と比較して遅れが見られるのが現状です。
この記事では、なぜ日本で探究学習の導入が遅れているのか、そしてその課題と解決策は何かを、探究学習で先進的な取り組みを行っている諸外国の事例も交えながら深く掘り下げていきます。諸外国の教育から学び、日本の教育が目指すべき未来について考えていきましょう。
探究学習とは?なぜ今、世界中で必要とされているのか?
探究学習とは、子どもたちが自ら「問い」を立て、情報を集めて分析し、「答え」を導き出す一連の学習プロセスのことです。これは、知識を「教えられる」のではなく、自ら「獲得する」経験を積むことで、以下のような力を育みます。
- 課題発見・設定能力: 普段の生活や学習の中から、自分で「なぜ?」「どうして?」という疑問を見つける力です。
- 思考力・判断力・表現力: 情報を収集・分析し、論理的に考察し、自分の考えを効果的に伝える力です。
- 情報活用能力・ICTリテラシー: 必要な情報を集め、それを分析し、正しく使う力です。
- 協働力(コラボレーション): 他者と意見を交換し、協力しながら課題解決に取り組む力です。
- 自己管理能力・自律性: 計画を立て、実行し、自己を振り返りながら学びを進める力です。
- 自己肯定感・達成感: 自分で発見し学ぶことの面白さを実感し、自信を深めることができます。
これらの力は、現代社会が「VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)」と呼ばれる予測不可能な時代であることから、世界中でその育成が求められています。探究学習は、このような時代の変化に適応するために不可欠とされています。
世界的に育成が目指されている能力には、OECDが2003年に提唱した「キー・コンピテンシー」や、国際団体「ATC21s」が提唱した「21世紀型スキル」(創造性、批判的思考、コミュニケーション、コラボレーションなど)があります。探究のプロセスは、これらの世界の教育潮流に合致しているのです。
世界の教育に学ぶ:探究学習の成功事例
OECD教育局長のアンドレアス・シュライヒャー氏も、教育先進国は探究的学習を優先して行っており、その結果、生徒が主体性や独創性を発揮し、失敗から学ぶ時間的余裕ができていると指摘しています。これらの国々の成功事例を見ていきましょう。
1. カナダ:多文化共生社会で育むグローバル市民
カナダは、多文化主義を国是とし、人口の約25%が移民という社会基盤を持っています。この背景から、教育制度はグローバル市民の育成に深く貢献しています。
- 多文化主義の推進と教育制度: オンタリオ州の教育課程では、「異文化理解」と「移民/多文化共生」が、初等教育から中等教育まで幅広い科目で包括的に扱われています。教育省は、多様な文化や価値観を持つ生徒間の公平性を目指し、その包摂と尊重を促進しています。
- グローバル・コンピテンシーの育成: カナダ教育担当大臣協議会(CMEC)は、「汎カナダ・グローバル・コンピテンシー」を開発し、批判的思考、イノベーション、自律的学習、コラボレーション、コミュニケーションといった能力の育成を目指しています。トロント地区教育委員会(TDSB)は、これを参考に独自のモデルを開発し、実践に活用しています。
- 学習方法とカリキュラム: カナダの教育は、実社会と直結した社会課題解決型のプロジェクト(PBL)が中心です。教科横断的・統合的な学習が重視され、国際交流プログラムや地域社会での奉仕活動などを通して、グローバルな能力を養う機会が提供されています。
2. フィンランド:主体性を尊重する「現象ベースの学習」
フィンランドの教育は、詰め込み教育を避け、子どもの主体的な学びと自己発見を重視する点が大きな特徴です。
- ナショナルコアカリキュラムの柔軟性: 国が定めるナショナルコアカリキュラムはガイドラインとしての役割に留まり、現場の教員に大幅な裁量権を与えています。教員は「情報伝達者」ではなく「助言者であり学習案内者」として、子どもの学びをサポートします。
- 広範囲的な能力(Transversal Competences)の育成: フィンランドのカリキュラムでは、「考え方、学び方を学ぶこと」「マルチリテラシー」「社会参加、持続可能な未来の構築」など、7つの「広範囲的な能力」を挙げています。
- 教科横断的な学習: 「現象ベースの学習」が導入されており、例えば「理科」で宇宙を学んだ後に「図工」で太陽系の絵画を作成したり、「フィンランド語」で台所の単語を学んだ後に「生活」でブルーベリーパイを焼いたりするなど、知識が実生活とどう結びついているかを実感できる学びが実践されています。
3. その他の国々の多様な取り組み
- アメリカ(ハイテックハイ): 課題解決型学習が中心で、決まった教科書がありません。「Got Maps?」プロジェクトでは、生徒が地域の環境問題を選んで調査し、専門家や地域住民にインタビューを行い、調べた内容を地図にまとめ発表します。
- シンガポール(シンガポール国立大学附属理数高校): 6年間の探究プログラム「ダ・ヴィンチプログラム」が行われています。生徒は外部講師やメンターのサポートを得ながら、例えば「水質汚染における生物指標としての米とエビ」といったテーマで独自の研究を進めます。
- コロンビア(Gimnasio Los Caobos): 社会の課題を解決するための探究学習が盛んに行われています。生徒がダウン症の子どもたちが交通ルールを学ぶためのアプリを開発するなど、国内の課題解決に密接に関わるプロジェクトがあります。
- オーストラリア: 「ナショナル・カリキュラム」に「汎用的能力」として、リテラシー、ICT技能、批判的・創造的思考力、異文化理解などを組み込み、21世紀を生き抜く上で不可欠な能力を育成しています。
日本が直面する課題と、諸外国から学ぶ解決策
日本は、探究学習が生徒の学習成果を63%高め、学習意欲も向上させる効果があることが報告されているにもかかわらず、その導入が遅れています。日本が抱える課題に対し、諸外国の事例からヒントを得られる解決策が提案されています。
1. 生徒の主体性を引き出すには
- 探究を「自分ごと化」する: 探究の第一人者である市川力氏が提唱する「Feel度Walk」のように、「なんとなく気になったもの」を写真に撮るなど、シンプルな活動から始めます。
- 探究学習の意義を生徒に伝える: 探究的に学ぶ力が大学や社会に出てから役立つこと、大学入試でも評価される機会が増えていることを周知します。
- 学習段階に応じた適切なテーマ設定: 1年生では取り組みやすいテーマを先生が指定し、学年が上がるにつれて生徒自身がテーマを設定するよう段階的に進めます。
2. 指導・評価方法の転換
- 教師の役割を転換する: 教師は「教える」のではなく、生徒から意見を引き出す「コーチング」や、生徒と同じ目線で対話を重ねる「メンタリング」、探究学習の進行を促す「ファシリテーション」といった役割を担います。
- 多様な評価方法の導入: 最終的な成果物だけでなく、学びのプロセス全体を丁寧に評価することが求められます。「パフォーマンス評価」や「ルーブリック評価」が有効です。生徒の学びのプロセスを記録する「ポートフォリオ」や、活動後に振り返りを行う「リフレクション」も重要です。
3. 時間の確保と連携の強化
- 既存の教材やオンライン学習サービスを活用する: 経済産業省が主催するSTEAMライブラリーなど、探究学習に利用できる無料の教材を活用することで、教材作成の手間を大幅に削減できます。
- コーディネーターの活用: 外部連携を支援するコーディネーターに依頼することで、連携先の探索や協力関係の構築、進捗管理といった課題を解決できます。
まとめ:探究学習は、先生の「学び」から始まる
日本にも探究学習の土壌はありますが、これまでの「詰め込み型・一斉授業」から脱却し、子どもたちの主体性を引き出す教育へとシフトしていくためには、教員の役割転換と、それに伴う評価方法の変革が不可欠です。探究的な学びは、生徒の学習成果と学習意欲を高める効果が報告されています。
この夏休みは、この探究学習をどう授業に組み込むか、じっくりと考える絶好の機会です。先生自身が「探究者」となり、諸外国の事例も参考に、指導や評価の「型」を学び、子どもたちと共に学び、成長する楽しさを、改めて感じてみませんか?