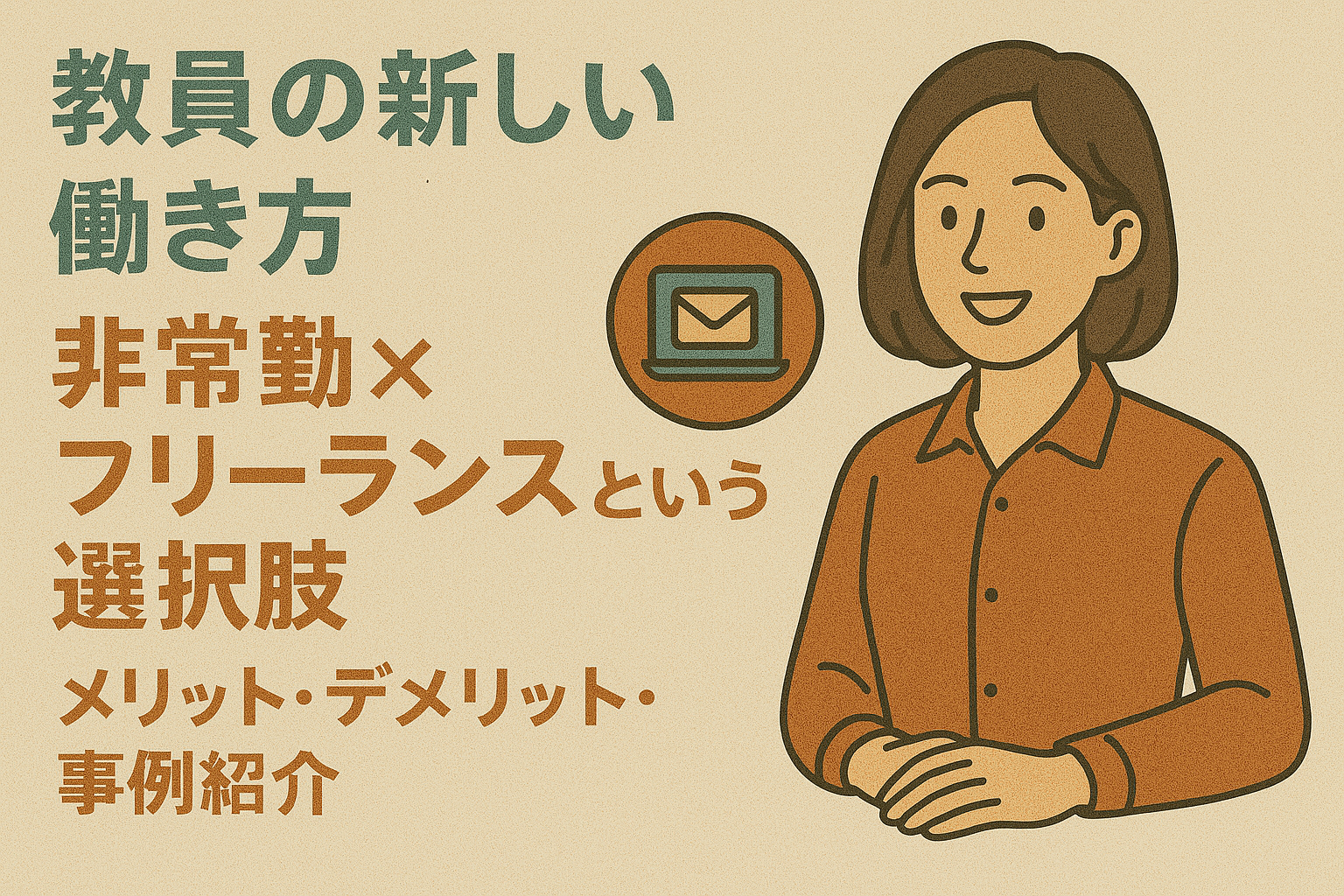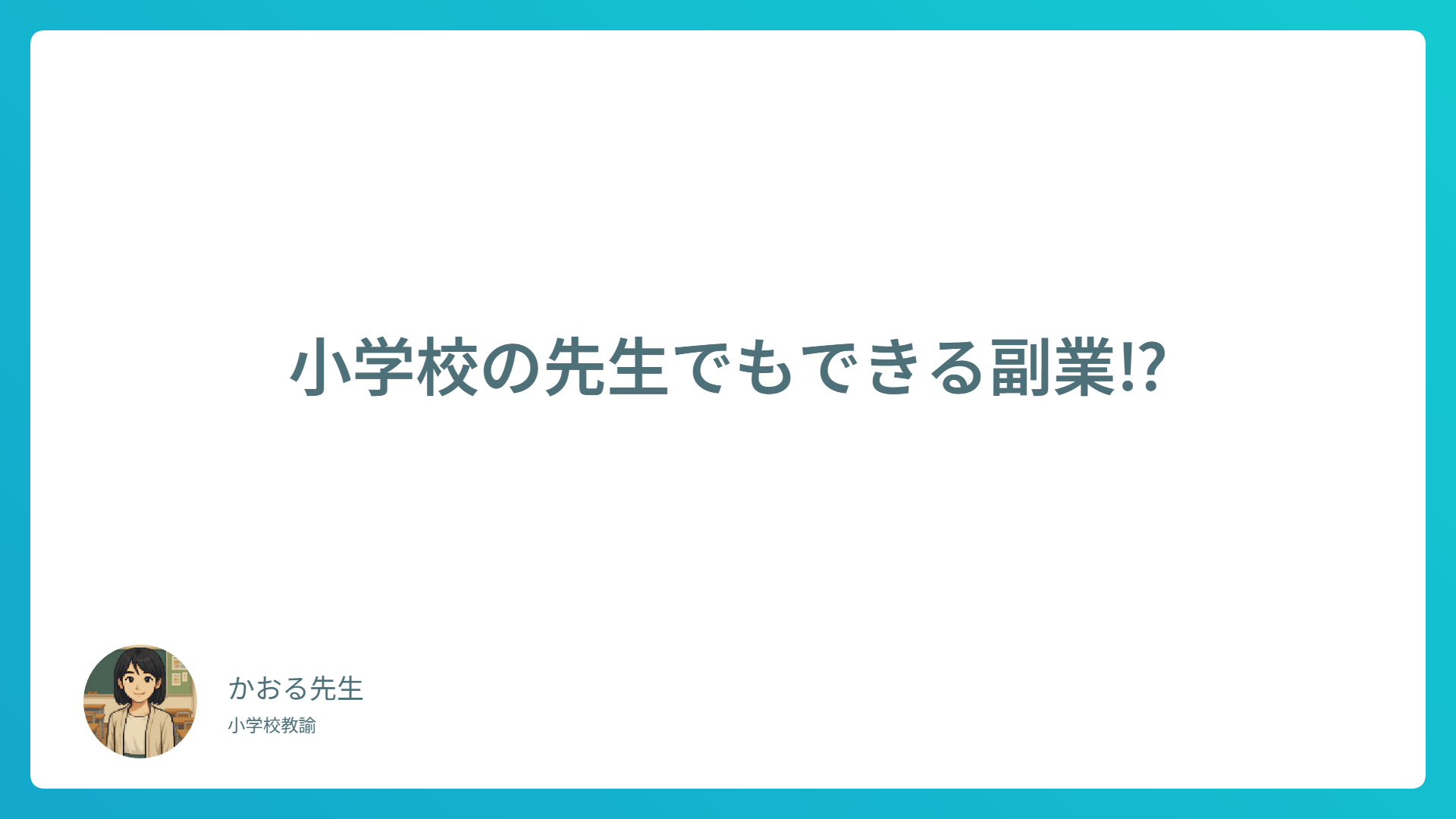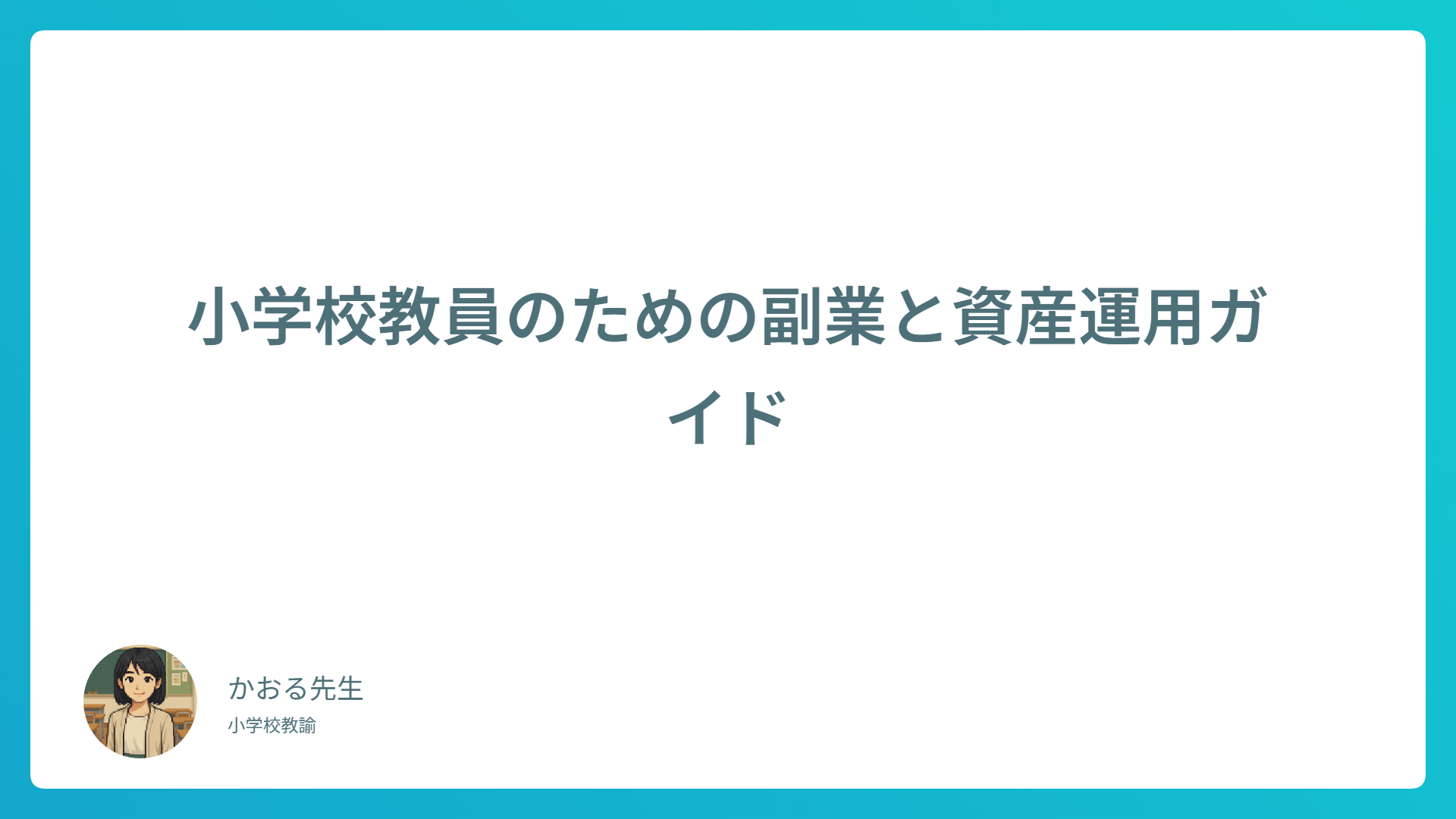教員の未来はこう変わる!長時間労働の改善とキャリアの選択肢、副業のリアル
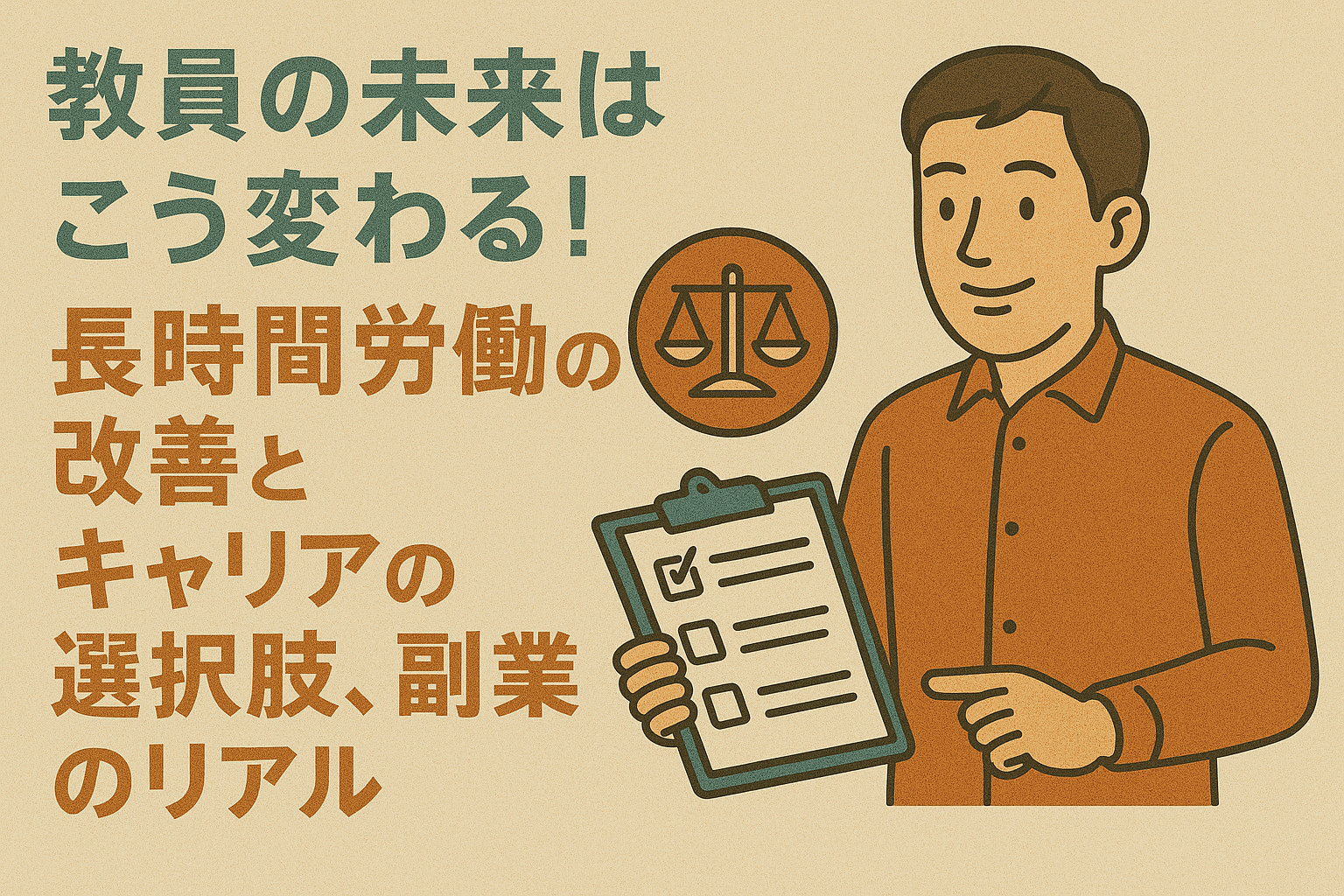
教員という仕事は、子どもたちの成長を支える大きなやりがいがある一方で、近年、その厳しい労働環境やキャリアパスの閉塞感が問題視されています。
「教員不足と採用競争率の低下」 「終わりの見えない長時間労働」 「副業に対する制度と実態のギャップ」
これらの課題は、教員個人の生活やメンタルヘルスに深刻な影響を与え、教職全体の魅力低下にもつながっています。この記事では、教員を取り巻く現状と課題を深く掘り下げ、今後の教育現場が目指すべき方向性、そして教員が自らのキャリアを多様化させるためのヒントを考察します。
教員を取り巻く現状|長時間労働・業務過多の背景
日本の教育現場は、深刻な教員不足とそれに伴う長時間労働という二重の課題に直面しています。
採用競争率の低下と教員不足
公立学校の教員採用試験の受験者数は減少傾向にあり、倍率も過去最低を記録しています。例えば、2025年度採用の佐賀県や宮崎県の小学校教員試験では倍率が1倍を切る状況が見られ、熊本市では追加募集を2度行うなど、人材確保が困難な状況です。
- 教員未配置の問題: 全国で教員の未配置が少なくとも3,644人に上るとの調査結果も報告されており、これは子どもたちに深刻な影響を与えかねない状況です。
- 早期退職の増加: 東京都の新任教諭の約5.7%が1年以内に退職しており、過去10年間で最高となっています。熊本県では2023年度の教職員退職者の半数が教員であり、退職理由の最多は「転職」でした。
- 「ブラック」なイメージ: 教員志望の学生を対象としたアンケートでは、94%が「長時間労働など過酷な労働環境」を、77%が「部活顧問など本業以外の業務が多い」ことを、67%が「待遇(給料)が良くない」ことを理由に挙げています。
長時間労働と給特法の課題
OECDの国際教員指導環境調査(TALIS)によると、日本の教師の勤務時間は参加国中で最長であり、授業時間が短く、学業以外の事務、会議、部活動に多くの時間を費やしていることが明らかになっています。
- 残業の常態化: 2022年度の文部科学省の調査では、国が残業の上限として示している月45時間を超えるとみられる教員が、中学校で77.1%、小学校では64.5%に上り、依然として長時間勤務が常態化しています。日教組の調査では、教員の平均在校時間は1日11時間21分、休憩時間はわずか9.7分と報告されています。
- 給特法の影響: 1971年に制定された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)により、公立学校の教員には時間外勤務手当が支給されない代わりに、給料月額の4%に相当する教職調整額が支給されています。この制度は「定額働かせ放題」と批判されており、労基法違反に該当するとの指摘もあります。この教職調整額は2026年から13%に引き上げられる案が発表されていますが、現場からは根本的な解決には至らないとの声も上がっています。
多忙化の要因
- 部活動指導: 部活動は教育課程外の生徒の自主的活動と位置づけられているにもかかわらず、多くの教員が膨大な時間を費やし、休日出勤が常態化しています。
- 業務量の増加: 国や教育委員会からの調査対応、研修会やレポート作成、保護者からの要望・苦情対応(カスタマーハラスメント)などが多忙化の大きな要因です。
- 学校外の対応: 「学校依存社会」として、本来学校の管理下ではない子どもの問題(SNSトラブル、家庭内トラブル、万引きなど)の解決を学校に求められることもあります。
- 費用自己負担: 教材費や修学旅行費の未納分、家庭訪問の駐車場代などを教員が自己負担する事例も多く報告されています。
働き方改革は進んでいるのか?現場の変化と課題
これらの課題に対し、教員の働き方改革は進んでいるのでしょうか。
- 勤務時間の減少: 令和4年度の調査では、平成28年度と比較して、教員の1日あたりの在校等時間が約30分減少しています。土日の在校等時間も全ての職種で減少しています。
- 業務内容ごとの変化: 「授業」や「授業準備」に要する時間が増加した一方で、「学校行事」、「成績処理」、「生徒指導」などに要する時間は減少しています。
- 勤務管理の改善: ほぼ全ての小中学校で「学校閉庁日」が実施され、多くの学校で「ノー残業デー」が導入されています。
- ICTの活用: ICTを活用した客観的な方法で勤務時間を把握する取り組みが進んでいます。また、学習評価や保護者連絡手段のデジタル化も約9割の小中学校で進められています。
- 支援人材の活用: 教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)をはじめとした支援スタッフの参画が進んでいます。
- 人事評価の反映: 近年では、勤務年数だけでなく、勤務実績や成果に基づいた人事評価が昇給に影響を与える仕組みが全国的に導入されており、評価が高ければ特別昇給も見込めます。
しかし、これらの改革は進んでいるものの、現場の教員からは根本的な解決には至っていないとの声も上がっています。平日の在校等時間は減少したものの、持ち帰り時間が若干増加している傾向が見られ、長時間労働の構造的な課題は依然として残されています。
多様化する教員キャリア|校務分担、専門職、転職という選択肢
教員というキャリアは、必ずしも定年まで勤め上げることだけが唯一の道ではありません。教員不足が深刻化する中で、キャリアの多様性を追求する動機も増えつつあります。
キャリアの多様性を追求する動機
- 経済的ニーズ: 物価上昇や教育費の増加に対する安心感を求めて。非常勤講師の場合、長期休暇中の収入減を補う目的もあります。
- 自己成長と社会貢献: 教室の外の世界を体感し、自身の価値を社会で試し、そこで得た学びを子どもたちに還元したいという意欲があります。
- 現在の仕事への不満や気分転換: 教職への不満、気分転換、あるいは転職・起業の準備として。
キャリア多様化への制約
一方で、教員がキャリアの多様性を追求する上で直面する制約は多岐にわたります。
- 法制度上の制限: 公立の常勤教員は地方公務員法により原則として副業が禁止されており、許可を得るための手続きが非常に煩雑です。
- 過酷な労働環境: 日本の教員の勤務時間は国際的に見て最長であり、副業に充てる時間そのものを確保することが困難です。
- 教員のメンタルヘルス問題: 精神疾患による病気休職者の数は年々増加傾向にあり、過労死や自殺の事例も繰り返し報告されています。
- 文化的な障壁: 「空気」の壁が存在し、副業をしたいという思いを教員自身が心の中にしまい込んでしまう傾向があります。
副業解禁の動きと可能性|教育系・非教育系の事例
教員の副業は、個人のキャリアを豊かにし、教育の質向上にもつながる可能性を秘めています。
副業の法的枠組み
- 公立常勤教員: 地方公務員法により原則禁止ですが、教育委員会から許可が得られれば可能です。
- 公立非常勤教員: 原則として許可なく副業が可能です。
- 私立教員: 勤務先の学校が定める就業規則によって副業の可否が異なります。
許可を得やすい副業の種類
- 教育関連の副業: 大学の非常勤講師、教育書の出版、教育手法のセミナー講師、オンライン家庭教師など。本業で培った「教える」スキルを直接活かすことができます。
- 地域貢献・社会貢献系の副業: NPOなど非営利団体での活動、地域スポーツ指導など。公務員の地域貢献活動制度の対象となることもあります。
- 許可を得ずに可能な副業: 資産運用、フリマアプリでの不用品販売など。
「副業」から「複業」へ
「シン・公務員」の前田ひろあき氏のような実践者は、単に収入を増やすための「副業」ではなく、自分の中に複数の側面を持つ「複業」という考え方を提唱しています。教員が教室の外の世界を体験し、そこで得た学びや経験を子どもたちに還元することで、社会との接点を持つ先生の言葉に説得力が増し、学び続ける姿が子どもたちにとって最高のロールモデルとなると考えられています。
これからの教員に求められるスキルとマインドセット
教員不足が深刻化し、教職離れが進む現状において、教員には従来の教育スキルに加え、以下のスキルとマインドセットが求められます。
- ICT活用能力: 授業準備や校務の効率化はもちろん、子どもの学びを個別最適化し、協働学習を促進するためのスキル。
- マネジメント能力: 限られた時間とリソースの中で、業務の優先順位をつけ、効率的に進めるセルフマネジメント能力。
- 越境する力: 教室の外の世界に関心を持ち、積極的に社会と関わることで、視野を広げ、新たな知見を授業に活かす力。
- 「完璧主義」からの脱却: 全てを一人で抱え込もうとせず、同僚や外部の専門家、ICTツールを頼る勇気。
まとめ|「持続可能な教員人生」を描くためにできること
教員を取り巻く現状は、教員不足、長時間労働、メンタルヘルス問題といった多岐にわたる課題が複雑に絡み合っています。
これらの困難な状況を乗り越え、「持続可能な教員人生」を描くためには、
- 個人の努力だけでなく、学校全体の働き方改革を進めること。
- 法制度の改善や、教員が安心して副業に挑戦できる文化を醸成すること。
- そして、私たち一人ひとりが、自らのキャリアを多様化させること。
が不可欠です。副業や「複業」といった新しい働き方は、教員のスキルアップや視野拡大に貢献し、結果として子どもたちへの教育の質の向上にもつながる可能性を秘めています。教員が自らの人生を豊かに生きる姿こそが、子どもたちの未来に希望を与える最高の教育となるでしょう。